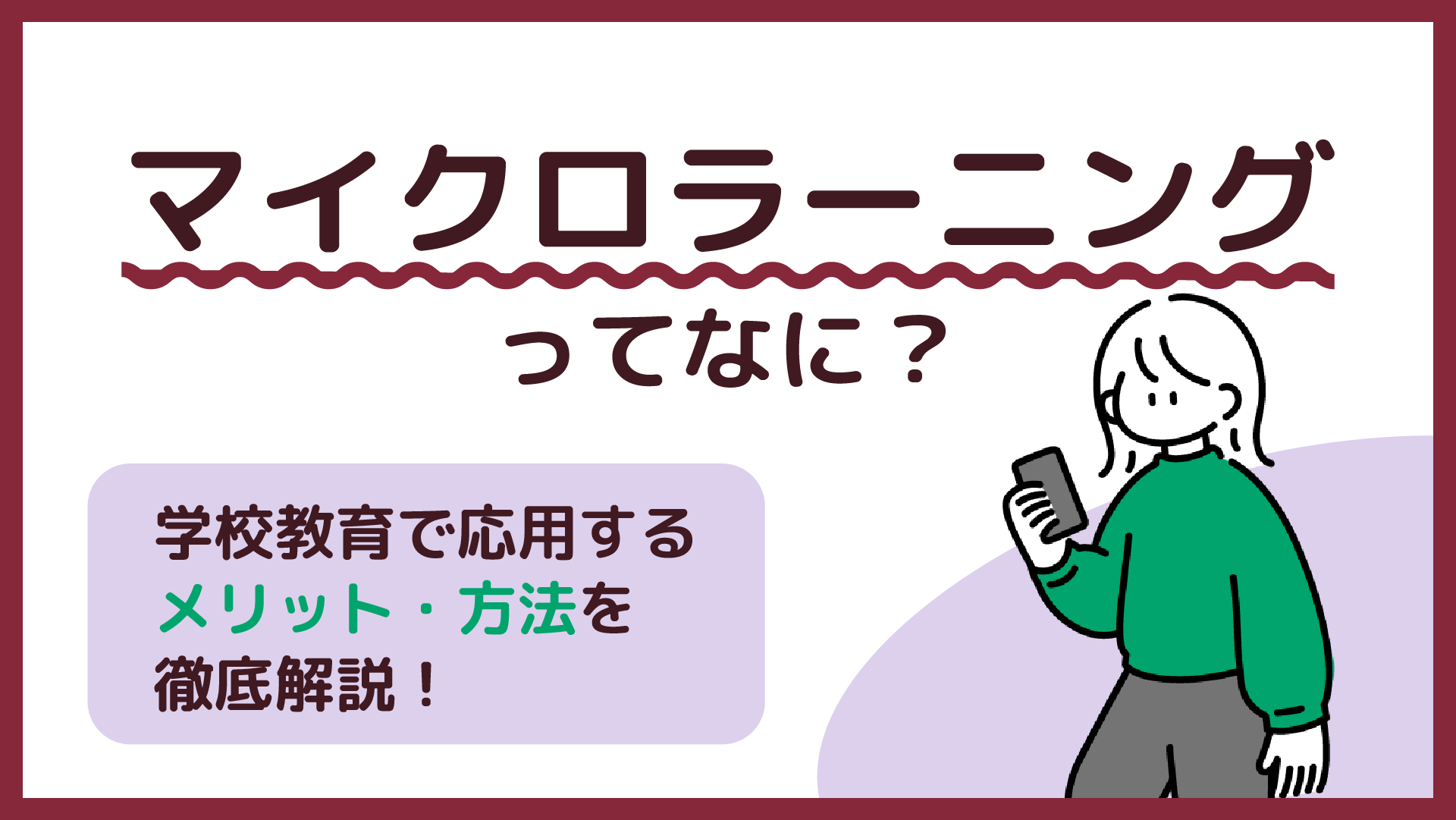みなさんは通勤・通学時間などのいわゆる「隙間時間」に何をしていますか?読書、動画視聴、音楽鑑賞、車窓からの景色を眺める……人それぞれだと思います。
そんな「隙間時間」を活用して、スキルアップを目指そう、という動きの元に生まれたのが「マイクロラーニング」です。もともとは社内研修の一つの方法として生まれ、学生の勉強法にも応用できる「マイクロラーニング」について、今回は現役東大生ライター、碓氷明日香が詳しく解説していきます!
マイクロラーニングとは
マイクロラーニングとは、短い時間で行う、モバイルデバイスを使った勉強法のことです。所要時間はなんと1〜5分!移動時間や仕事と仕事の合間の隙間時間に、スマホやタブレットから動画を視聴したり問題を解いたりして、必要な知識を身につけることができます。
従来の長時間にわたる学習とは異なり、手軽に少しずつスキルアップを図れることが特徴です。
マイクロラーニング登場の背景
そもそも、どのような流れでマイクロラーニングが生まれたのでしょうか。
前述の通り、マイクロラーニングは企業の研修の一つの方法として登場しました。従来の研修方法では、一度にまとまった量を学習するスタイルが一般的でした。しかし、忙しいビジネスパーソンにとってまとまった時間を確保するのは難しい上、一度受けた研修を復習するところまで手が回らず、学習内容を定着させることができていない、という問題がありました。また、数十分にわたる動画を見ていても、途中で集中力が切れてしまい、時間の無駄になりがちでした。
その問題を解決するために、短時間で完結するマイクロラーニングが登場したのです。コンテンツが軽く、わざわざパソコンの前に座らずとも、立ったままスマホやタブレットからアクセスできるマイクロラーニングは、これまでの研修方法と比べて圧倒的に効率がよく、徐々に普及しつつあります。
eラーニングとの違い
マイクロラーニングに似た用語として、「eラーニング」がありますが、この二つにはどのような違いがあるのでしょうか。
eラーニングは、インターネットを利用してスマホやパソコンなどのデバイスで学習するオンライン学習形態のことを指します。そして、一般的なeラーニングは数十分から数時間にわたる動画コンテンツの視聴が基本です。
つまり、マイクロラーニングはeラーニングの短時間バージョン、というわけです。短い時間でサクサクと進む学習を求めるのなら、マイクロラーニングが最適といえるでしょう。
マイクロラーニングのメリット
では、マイクロラーニングを導入するとどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、3つの利点を挙げていきます。
学習のハードルが低い
まずひとつ目は、「学習のハードルが低い」ことです。机に座ってガリガリ勉強したり、パソコンの前で長い動画を見たりする必要がなく、隙間時間にサクッと勉強できるので、そこまで高いモチベーションが必要なわけではありません。
学生にとって、部活や遊び、趣味など、勉強のほかにやること、やりたいことはたくさんあります。そんな中で勉強のやる気を出すのは難しいことです。でも、そこでマイクロラーニングを取り入れたら、少なくとも数時間机に向かうよりは、5分くらいなら勉強するか、という気になる可能性も上がるかもしれません。
学習内容が定着しやすい
ふたつ目は「学習内容が定着しやすい」ことです。長時間のコンテンツを一度見るだけよりも、短時間のコンテンツを繰り返し見た方が、学習内容が記憶に残りやすいのは想像に難くないでしょう。
英単語や数学の公式、日本史・世界史の用語などの単純な知識は、何度も繰り返し目に触れることが大切です。マイクロラーニングはその機会を増やしてくれ、基本問題の正解率を上げてくれます。
また、クイズ形式の問題をコンテンツに組み込めば、気軽にテスト感覚で理解度を確認できます。間違えた問題を復習するシステムがあれば、個人の苦手に合わせて勉強でき、全体の理解度を高めることができるのです。
教材の作成・修正が楽
三つ目は「教材の作成・修正が楽」ということです。これは教材を作る側、つまり教員側のメリットです。
eラーニングでは、長い動画を取ったり、それを編集したりする必要がありましたが、マイクロラーニングではひとつひとつの教材が軽いので、作成が簡単です。
また、数年に一度やってくる学習指導要領の変更に伴い、教材を修正する必要が出てきますが、短くて軽いマイクロラーニングの教材は比較的修正が簡単です。この点も、業務量の軽減につながるでしょう。
近年、教員の業務過多は深刻な問題となってきています。少ない業務で学生の成績を底上げできるのなら、それに越したことはないでしょう。
マイクロラーニングのデメリット
一方で、マイクロラーニングにはデメリットも存在します。ここでは、2つのデメリットを挙げていきます。
複雑な問題の演習はできない
まずひとつ目は「複雑な問題の演習はできない」というものです。マイクロラーニングは短い時間で要点を抑えることに特化した勉強法なので、記述・論述問題や複雑な計算を要する問題、長時間考えて解くような問題は扱うことができません。
マイクロラーニングはあくまで基礎知識を理解し、覚えるためのものであり、それ以外の勉強も必要になってくることは確かです。
導入・運用にコストがかかる
ふたつ目は「導入・運用にコストがかかる」というものです。マイクロラーニングを導入する際は、ほとんどの場合システムを準備する必要があります。多くの機能を使おうとすればするほど、システムのグレードアップが必要になり、一定のコストがかかってくるのです。
もちろん、必ずしもコストがかかるわけでもありません。無料で使えるマイクロラーニングシステムもあります。ただ、使える機能が制限されることもあるので、必要に応じてどのシステムを使うか考えることが求められます。
教育現場における導入のポイント
企業の研修において広がりつつあるマイクロラーニングを、学校教育で効果的に活用するにはどのようなポイントに気をつければいいのでしょうか。
ひとつひとつで完結するコンテンツを作成する
マイクロラーニングが効率的と言われているのは、勉強が「短時間で完結する」からです。それを実現するために、教材をつくる際に気をつけるべきこととして、「ひとつひとつで完結する簡単なコンテンツを作成する」ことが挙げられます。
例えば、歴史の教材を作るときは、地域、時代ごとに細かく単元を分け、用語とその端的な説明をクイズ形式にする。化学の教材を作るときは、単元ごとに出てくる物質とその化学式を1対1対応で一覧にしたり、化学反応式の一部を空欄にして、当てはまる物質や係数を記入するテストにしたりする。こうすれば、とっつきやすく短時間で終わる教材ができるはずです。
あれもこれもと内容を詰め込みすぎたり、一回で終わらないからと複数回に分けたりすると、マイクロラーニングの良さが失われてしまうので、気をつけたいところです。
アクセスのしやすさを損なわない
また、マイクロラーニングの良さとして、「アクセスのしやすさ」というのも挙げられます。場所を選ばず、スマホやタブレットから簡単に勉強を始められる。この良さを損なわないために、使うシステムは簡単でアクセスしやすいものを選びましょう。どの配信ツール・プラットフォームを使うのが最適か、検討することが重要です。
他の学習方法と併用する
前述の通り、マイクロラーニングだけでは複雑な問題の対策はできません。そのため、「他の学習方法と併用する」必要があるのです。
記述や論述の点数を上げるために、マイクロラーニングとは別で添削問題を課したり、その分野の体系的な理解を促すために、マクロな視点から説明する授業を取り入れたりするといいかもしれません。これまでの授業方法やテストなども適宜使いつつ、マイクロラーニングで基礎知識の定着を図るのが最も効率のいい方法といえるでしょう。
まとめ
今回は、短時間の学習を可能にしたマイクロラーニングについて解説しました。もともとはビジネスパーソンの研修に使われていたこの勉強法ですが、隙間時間をうまく活用して勉強することが必要なのは、学生も同じです。他の学習方法と併用しながら、学生が効率よく勉強をできるように工夫してマイクロラーニングを取り入れてみてはいかがでしょうか。
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。