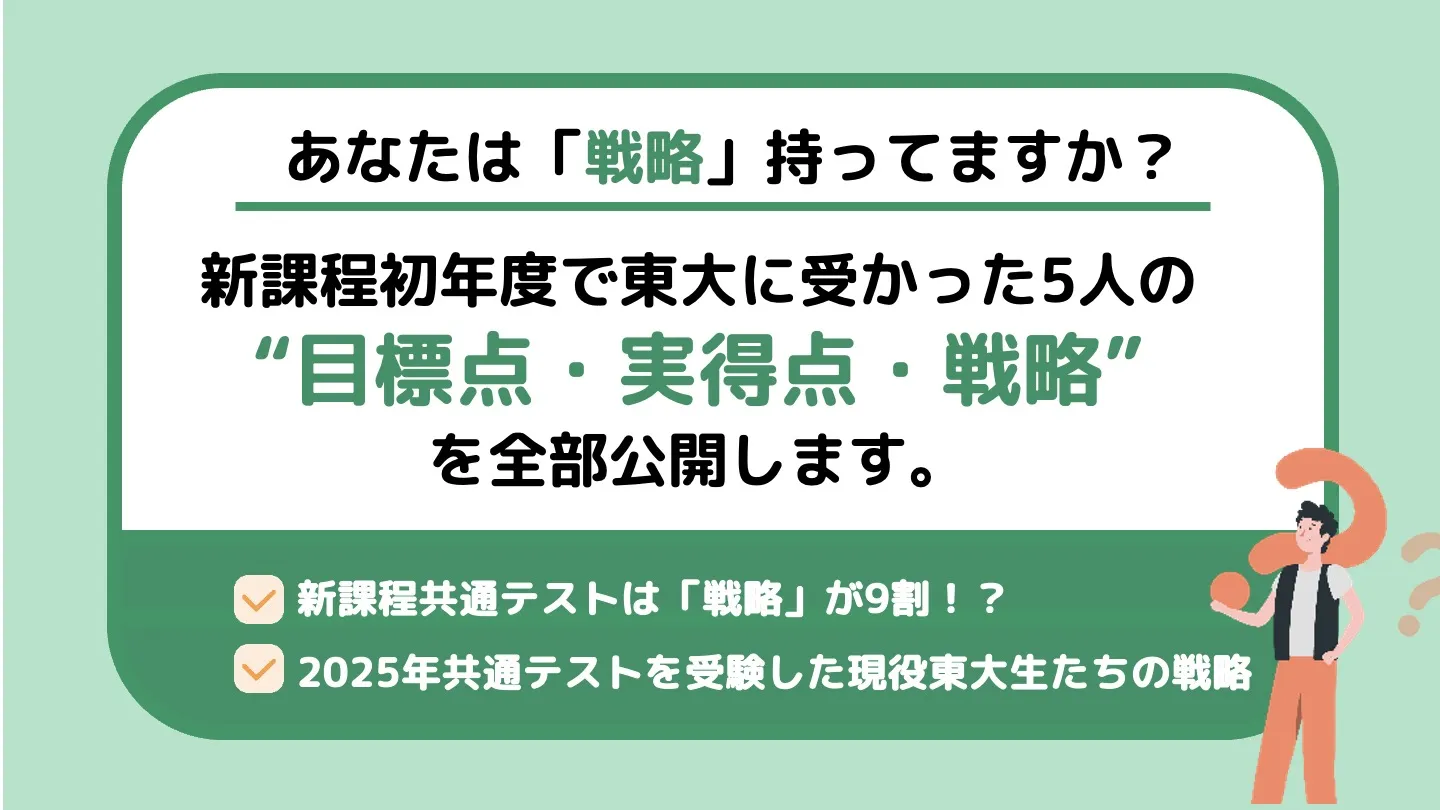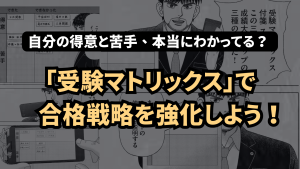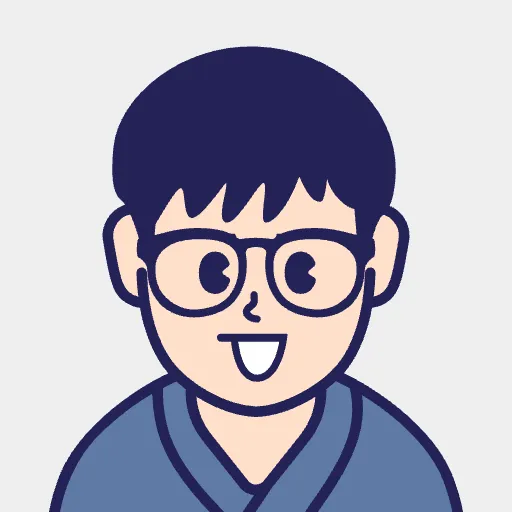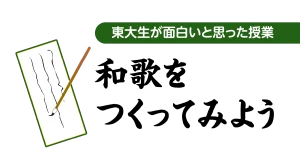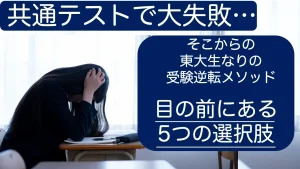2025年より大きく形式が変わった、大学入学共通テスト。
その初年度に挑み、みごと東大に合格した5名の目標点・実際の点数・受験戦略を聞いてきました!
5人それぞれ違ったタイプなので皆さんにも応用できる共通テスト戦略が見つかるはずです。
はじめに:新課程共通テストは「戦略」が9割
2021年にスタートし、2026年に第6回目を迎える大学入学共通テスト。
前回から「新課程」に基づいた内容になり、さまざまな変更が実施されました。
たとえば、「情報」の新設、地歴公民の再編、数学の範囲・試験時間拡大などがその主たる変更になります。
これらの変更は当然、事前に発表されていましたが、実はこれら以外にも変更されたことがありました。たとえば、英語Rの大問構成は全六問から全八問に変更されました(総word数は700語減ったので、レイアウトの変更です)。
このように、変動が起こるかわからない共通テストにおいて獲得点数に大きく影響するものがあります。
それは「戦略」です。
共通テストは出題範囲の広さ、試験時間の長さなど、とてもタフネスが要求されるテストです。
そのためどの科目でどう得点するのかという算段があるだけで、2日間の試験の渡り方が変わってきます。
また、二次試験対策とどのようにバランスをとるか、この戦略も大切です。
そこで本記事では、実際に2025年1月に共通テストを受験し、東大に見事合格した5人の受験生の戦略を見ていきます。
彼ら彼女らは、新課程初年度という難易度の高い年度に受験し合格した面々です。どんな戦略で共通テスト受験に臨んだのか、気になりませんか?
⋯⋯そのまえに、戦略を立てるための基本的な2ステップを確認しましょう。
戦略ステップ1:とにかくまず敵を知ろう!
戦略を立てるには、まず敵を知ることが必要です。
ここでいう敵の情報とは何点満点のテストなのか、試験時間はどれくらいなのか、どのような問題が出題されるのか、志望校合格には何点必要なのか、と言った情報です。
それらを調べた上で共通テストを深く知るためには、過去問や模擬問題を実際に解いてみるのが良いでしょう。
過去問の問題・解答解説はネット上で公開されています(ちなみに、翌年の試験スケジュールは毎年6月ごろに公表されます)。
公開されている問題を自分で時間を計って解くのもいいですが、予備校主催の「同日模試」を受験してみることもおすすめです。通常の模試と同様に偏差値もわかるため、その点でもおすすめします。
過去問を試験前まで取っておきたい方は、模擬問題として模試をうけましょう。試験時間や問題形式の感覚がつかめると思います。
また実際に問題を解くと、敵(共通テスト)についての情報と同時に自分の現在地、得意不得意、敵との距離などを知ることができます。
なんとなく、やるべき勉強が見えてくるはずです。ここまでが、戦略立てのステップ1です。
戦略ステップ2:目標点を高く、具体的に設定しよう!
敵を知り己を知ったら、どう戦うかを本格的に考えていきます。
そのために必須なのが、目標点数です。
例えば「苦手な数学を演習する」「国語で点がとれるようになる!」といった目標は抽象的で、達成度をはかりにくいですよね。
そこで目標を立てる際は具体的に点数で目標を立てるようにしましょう。
「数学ⅠAで80点」「古文漢文はそれぞれ35点」のようにすると、試験や模試の後、達成できたかわかりやすいですよね。
そして、目標点数は「高め」に設定してください。
「合格者最低点+1点でも勝て」というようなスローガンがよくありますが、これは結果論です。目標が無意識のうちに、自分の限界になってしまうこともあります。最低点+1でも合格は合格という話で、そんなギリギリを目指す必要はありません。
ただ、500/1000点の人が「満点を目指します!」というのは突拍子もなさすぎますね。
おすすめは「ちょいムズ」な目標です。「ちょいムズ」くらいが、脳が最も活性化するそうです。
そこで現実的だが難しいラインを目指すようにしましょう。例えば700点の人は800点、800点のひとは900点、900点の人は950点ぐらいにするといいです。
目標点数を決めたら、部屋の目につく位置に貼って、意識するようにしましょう!
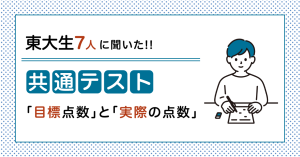
2025年に共通テストを受験した現役東大生たちの戦略
さて、ここからはいよいよ、新課程初年度の共通テストを乗り越えた5人の事例を見ていきましょう。目標点や戦略には三者三様です。
どんなところが参考になるでしょうか。一緒に眺めていきましょう。
「実力を出せれば9割とれる!」文科三類
目標点:
900/1000(930/1000が理想)
結 果:
| 科目名 | 得点 | 補足 |
| 世界史B | 96 | |
| 日本史B | 94 | |
| 国語 | 170 | |
| 英語R | 100 | |
| 英語L | 89 | |
| 理科基礎 | 95 | (化学基礎50,生物基礎45) |
| 数学ⅠA | 95 | |
| 数学ⅡB | 94 | |
| 情報 | 89 | |
| 【合計】 | 921 |
戦 略:
各科目9割をとって全体9割を目指しました。9割を意識したのは、東大合格者がだいたいそれくらい取ると聞いたからです。
僕は模試ごとに、点を取れる教科とそうでない教科がまちまちでした。ある時は国語で高得点を出したり、ある時は情報でオオコケしてしまったりと、どこかの教科が伸びても他の教科が下がることが課題でした。
しかしこれは、逆に言えばすべての教科で全力を出せれば9割も取れるかもしれない、という自信になりました。
ポテンシャルを出し切るため、教科ごとの気持ちの切り替えを意識しました。
体験記:
高3夏頃までは、特に数2Bや英語Rが苦手だったので、そこに注力しました。そのおかげで数2Bはだんだんと成長していきました。
英語Rに関しては明らかなターニングポイントがありました。8月の全統模試の過去問を夏休みに解いたときです。その問題がかなり簡単で、初めて9割を超えたんです。この演習で時間内に解き切る感覚をつかむことができました。
また国語は、漢文の句法と古文単語を冬におさらいしたら格段にペースが上がりました。数学2Bも、統計の典型問題を覚えた事で時短に成功しました。
日本史、世界史は文化史や年号などの細かいところをやった事で、点数自体はあんまり変わってないですが、解いている時の解答への自信が変わりました。理科は直前の短期記憶に頼ると決めて、ほどほどにしていました。情報はほとんどやっていません。
感 想:
1日目の国語の時、現代文で考え込んだときにとても頭が熱くなって、文章を読んでも何も理解できない時間がありました。その時はかなり焦りました。特に有効な手も打てずに、心を落ち着かせるのに時間を割いてしまいました。
また、普段はかなり早く終わらせられていた化学基礎で、計算ミスを連発し、40分使ってしまったのは想定外でした。本番はこわいですね。
「目標に届いていなかったので⋯⋯」文科二類
目標点:
900/1000
結 果:
| 科目名 | 得点 | 補足 |
| 世界史B | 90 | |
| 日本史B | 94 | |
| 国語 | 184 | |
| 英語R | 96 | |
| 英語L | 94 | |
| 理科基礎 | 97 | (地学基礎50,生物基礎45) |
| 数学ⅠA | 83 | |
| 数学ⅡB | 83 | |
| 情報 | 78 | |
| 【合計】 | 899 |
戦略:
東大受験生と差がつかぬよう、9割を目標にしました。
共テ対策に集中したのは12月以降です。
それまで9割の目標を達成した事がなかったので、周りより早く共通テストにフォーカスしたわけです。
勉強の中心は予想問題でした。予想問題をやって、わからないところを適宜確認するといった感じです。
感 想:
今年の共通テストは易化した気がしました。情報のプログラミングはわかりませんでしたが、模試でも情報は取れていなかったので、さほど気にしませんでした。
「しっかり点を取る!」理科一類
目標点:
910/1000
| 科目名 | 目標点 |
| 地理総合、地理探究 | 88 |
| 国語 | 170 |
| 英語(リーディング) | 95 |
| 英語(リスニング) | 87 |
| 物理 | 97 |
| 化学 | 93 |
| 数学Ⅰ、A | 92 |
| 数学Ⅱ、B、C | 95 |
| 情報 | 93 |
| 【合計】 | 910 |
結 果:
| 科目名 | 得点 | 補足 |
| 地理総合、地理探究 | 87 | |
| 国語 | 197 | (近代以降の文章107/110 古文45/45 漢文45/45) |
| 英語(リーディング) | 100 | |
| 英語(リスニング) | 100 | |
| 物理 | 100 | |
| 化学 | 89 | |
| 数学Ⅰ、A | 95 | |
| 数学Ⅱ、B、C | 100 | |
| 情報 | 97 | |
| 【合計】 | 965 |
戦 略:
高3になってから共テ模試を受けていくなかで、自分は比較的共通テストが得意な方だと感じました。それなら、共通テストでしっかり得点しておきたいと思ったんです。
東大の圧縮後の共通テストの得点で100/110を取りたいと考えたので、まず合計点で910点(圧縮後:100.1点)を設定しました。そのあとで、各科目の目標点を割り振っていきました。
体験記:
本格的に共通テストの対策を始めたのは、2学期の期末テスト後(12月上旬)に全ての教科の高校の授業が共テ対策に切り替わってから。それまでは二次試験の対策に集中していました。共テに触れたのは、先生が授業の題材に使ったときくらいです。
冬休みに入ってから、もう少し演習を積みたいと感じた教科(英語リスニング、物理、化学、数学ⅠA、ⅡBC)は市販の予想問題集(Z会)を購入しました。それらを全て解き切ったわけではなく、不安の残る教科・単元のみを演習しました。
予想パックは、学校専売品の代ゼミのもの(白パック)を年明け解きました。
演習は、ちゃんと時間を計って解いていました(一旦本番と同じ制限時間で解き、残った部分はその後解く)。
そして自己採点をして復習をします(間違えた問題が中心。なぜ解けなかったのか、どうすれば解けたのかを考えることを常に意識し、必要に応じて教科書などに戻り知識をインプットし直す。正解した問題についても解説を一読し、思考・解答プロセスが最適であったかを検討する)。
感 想:
概ね、事前に想定していた通りに進めることができました(時間配分など)。マークチェックも全ての科目で行えました。
同じ高校の人がかなり多い会場だったので、余裕があるときには友達と話したりなどして、比較的リラックスして受験することができました。
「背水の陣」文科三類
目標点:
| 科目名 | 目標点 |
| 世界史B | 95 |
| 日本史B | 100 |
| 国語 | 175(現代文95、古文40、漢文40) |
| 英語R | 85 |
| 英語L | 85 |
| 理科基礎 | 85(物理基礎40,生物基礎45) |
| 数学ⅠA | 80 |
| 数学ⅡB | 80 |
| 情報 | 85 |
| 【合計】 | 870(現実的に850くらいまでの下がり幅は想定) |
結 果:
| 科目名 | 得点 | 補足 |
| 世界史B | 88 | |
| 日本史B | 100 | |
| 国語 | 166 | (現代文82、古文45、漢文39) |
| 英語R | 92 | |
| 英語L | 80 | |
| 理科基礎 | 83 | (物理基礎36,生物基礎47) |
| 数学ⅠA | 70 | |
| 数学ⅡB | 61 | |
| 情報 | 76 | |
| 【合計】 | 816 |
戦 略:
まず得意な1日目(英国社)でできるだけ稼いで9割、苦手な2日目(数情理)は「この点は下回らない」ラインを8割に決めました。本格的な対策に入ったのは12月からで、各科目の戦略は以下の通りです。
〈日本史・世界史〉
得意なため強気に目標設定。演習は非効率だと思い、直前は知識を詰めるだけにしました。
〈英語〉
対策にもっとも時間を割いた科目。85点くらいを目標にして、毎日一回分は演習するようにしました。特にリスニングは耳慣れするために欠かしませんでしたね。リーディングも毎日しないと読む速さが落ちてしまうので、本番と同じ分量・時間での演習をこころがけました。
〈数学〉
苦手だったので、あまり目標点は吊り上げませんでした。演習でも時間が足りなかったので、最初の比較的簡単な問題を確実に解いて、最後の難しく時間がかかる問題は飛ばす戦略に。75~80点は死守しようと。結果を見ると、もっと早くから演習を始めておくべきだったと感じます。
〈国語〉
ブレが大きい科目でした。170くらいをコンスタントに取れていたので、目標は175に。古文漢文で落とさない戦略で対策しました。
〈理科〉
物理は計算が多く難しいので、知識問題の多い生物でどれだけ落とさないかが重要でした。演習は直前に詰めました。
感 想:
最初の科目:社会が得意だったので、スタートダッシュができ、かなり心に余裕ができました。
目標通りにいかなかった理由は、数学と情報でコケたことです。対策したことを活かせませんでした。数学の大問一個解き忘れていたのは大失敗でしたね。
あとは、事前に会場の下見をして、自販機とかコンビニの場所を把握しておくのが大切だと思います。
「二次試験優先で」理科三類
目標点:
950/1000
結 果:
| 科目名 | 得点 |
| 日本史B | 86 |
| 国語 | 187 |
| 英語(リーディング) | 100 |
| 英語(リスニング) | 98 |
| 物理 | 95 |
| 化学 | 97 |
| 数学Ⅰ、A | 97 |
| 数学Ⅱ、B | 100 |
| 情報 | 100 |
| 【合計】 | 960 |
戦 略:
二次試験の対策を優先しました。得意な理数・英の目標は満点。これらに比べて点が取りにくかった国語と社会は、失点をあわせて25点におさえる計算でいました。
共通テスト対策を本格化させたのは、年が明けてからです。国語の過去問5年分、日本史の過去問・模試各5年分、情報を5セットくらい解きました。古文と漢文と情報の知識も、この時期に詰めました。
それ以外の科目は、二次対策をしていれば特に問題ないだろうと思い、共通テストを意識したことはしませんでした。
感 想:
初年度だからか、情報は対策がいらないくらい簡単に感じました。国語が187日本史86。その他の科目では、共テ問題特有の感覚を忘れていて、ちょいちょいミスって960。
実際に入学してみて、周りの理IIIのなかで平均くらいだと思います。
まとめ
タイプの違う5人の共通テスト戦略がわかりましたね。
しかし全員、共通テストや自分の志望校のことを分析し、自分がどうすべきかという対策をしっかりと立てていたことが軸にあります。
全員その上で自分の得意、不得意や使える時間に応じて戦略を立てています。
これらの戦略を参考に自分なりの合格戦略を立てて、共通テストを掌握しましょう!

公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。