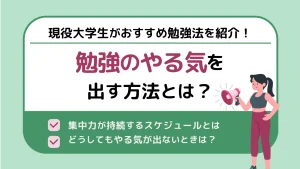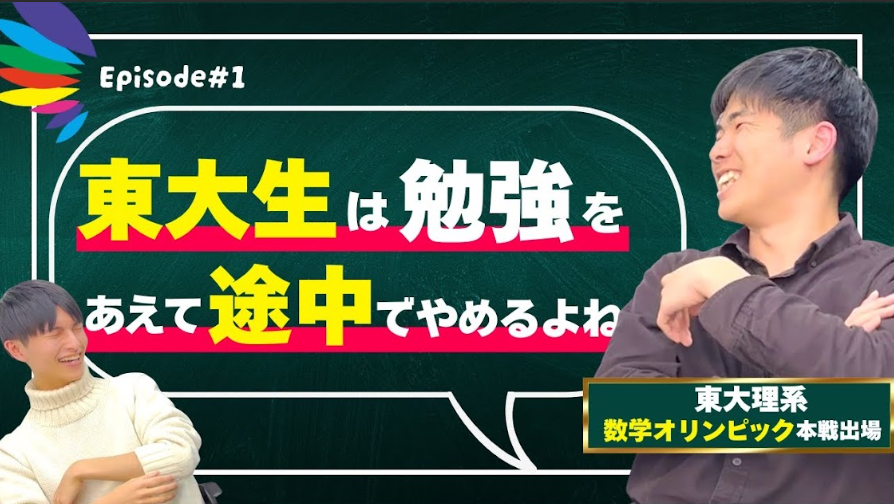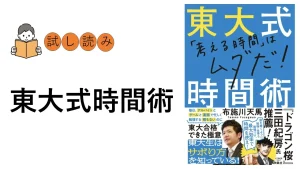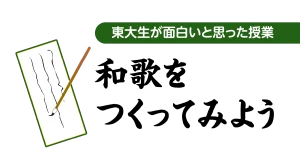一般的に、勉強はやる気があるからできる、というイメージがありませんか?やる気とは、物事を「やるぞ」と頑張る強い気持ちのことですから、勉強に限らず、スポーツや家事など、何事においてもそう感じるのは当然かもしれません。しかし、東大生の間では、「実はやる気なんてなくても勉強はできるのではないか」という噂が広まっています。本当にやる気がなくても勉強はできるのでしょうか?
動画サムネイル右 永田耕作:東大理系 計算の申し子
動画サムネイル左 清野孝弥:東大文系 外国語マスター
東大カルぺ・ディエム公式チャンネル動画はこちらから。
永田耕作が教える!〜「やる気」の出し方〜
東大生講師として数多くの高校の教壇に立ってきた永田さん、やる気の出し方について質問されることが多くあるそうです。そこで学生時代から永田さんがやる気を出すために行っていたことについて解説します。
どうやったら「やる気」は出るの?
清野:まず、永田さんは「やる気信者」ですか?
永田:どうだろう。「(やる気が)あった方がもちろんいい」というのは大前提ですが、でも「とりあえずやれ」という考え方もあります。私は部活動を長くやってきたので、「とりあえずやる」派かもしれません。
清野:例えば、学校の課題などでやる気が出なくても、夢中でできるタイプですか?
永田:どちらかと言えば、「今はつまらないけど、将来のために」とゴールを見据えて頑張るタイプですね。
清野:学校現場で、「やる気が出ません」「モチベーションが上がりません」といった相談はよくあります。その際、どのようにアドバイスされていますか?
永田:お伝えしているうち一つは、先ほどの「ゴールを見据えてやる」方法です。もう一つは、そもそも「やる気が出ないのは当たり前」だと捉えることです。
「やる気」を出すにはまずやろう
清野:何か永田さんが「とりあえずやる」で行っていた具体例はありますか?
永田:例えば、野球の素振りです。1日に300回、500回とやるのはきついですよね。地味な練習は気が進まないものです。バッティングセンターで100回打つのとは違います。300回素振りをするには50分かかりますが、「とりあえず30回だけ」と外に出ると、意外とできてしまうものです。さらに、30回やるつもりが、気づけば120回くらいやっている、なんてこともよくあります。
清野:それは、優等生ですね。(笑)
永田:これは勉強でも同じことが言えます。ノートの1ページ目を書き始めると、「次の問題も頑張ってみようかな」「(答えを見て)なるほど、これも理解できたから、もう1問やってみようかな」となります。
しかし最初の「始める」という行為が一番きついのです。
清野:ゲームも同じですよね。少しやり始めると、もっとやりたくなってしまいます。だから、勉強のやる気が出ない人が多いのではないでしょうか。
時間の解像度をあげよう
永田:そうですね。そういう人には、時間を区切ることをお勧めします。常に時間で動くという習慣が大切です。自分がどれだけスマホを見ているか把握していますか?スクリーンタイムを見ると、1時間だと思っていても、実際はもっと長い場合が多いのです。
清野:東大生はスマホやゲームをしないのですか?
永田:そんなことはありません。しかし、自分が「いつからいつまで何をやっているか」という意識、つまり時間の使い方の解像度が非常に高いのです。「この1時間は休憩で、YouTubeを見る時間だ」と割り切っています。問題は、昨日何をして過ごしたか、と聞かれたときに、具体的な行動で埋まらないことです。
清野:確かに、そういう生徒は多いですね。
永田:1日をきちんと時間を区切って考えると、意外と長いものです。だから、サボるなと言っているのではなく、やる気スイッチを切り替えるためにも、「何時になったら勉強しよう」「この時間まではリフレッシュしよう」と時間を区切ることが有効です。
清野:これは個人的に罠だと思っていることですが例えば、「2時間YouTubeを見る」と決めていても、残り2分になった時に面白い動画を見つけてしまい、つい見てしまう。そして、「勉強のやる気が出ない」と、そのままYouTubeを見続けてしまう。
これが、今日のテーマである「やる気」とは何か、という話に繋がっていきます。
実は、「東大生はやる気がないのに勉強ができる」のではなく、そもそも「やる気」という概念がない、という説があるのです。
「やる気」のあるなしに関わらずに行動する方法
そもそも「やる気」という概念はふわっとしていますね。永田さんも清野さんも実はやる気に頼らずに勉強する方法を高校時代から実践していたようです。
やる気はフィクション?
清野:「やる気」という言葉は、やる気のない人間が作り出したフィクションだ、という東大の教授がいるそうです。
永田:それは面白いですね。
清野:「やる気」のようなものはなく、人間は何か行動しているうちに、「もっと続けたい」という意欲が湧いてくる。しかし、後から「これって、いわゆるやる気だったのでは?」と都合よく解釈しているに過ぎない、というのです。
永田:なるほど。
清野:YouTubeをあと2分しか見れない時に、「やる気がないから」という理由で勉強の行動を起こさなければ、それはそれで都合が良いわけですね。レトリック(巧みな言い回し)として使われている側面がある、という話です。
この話を聞いて信じられますか?
永田:あまり疑っていません。私は時間を区切って動くタイプなので、「やる気があるから」「やる気がないから」という日があまりなかったのです。
清野:まるで機械人間ですね(笑)
永田:私は仕事でも大学でも、時間を決めれば動けます。私のカレンダーには、「9時23分に最寄り駅に到着」といった具体的な予定が書かれています。逆に、「10時に渋谷集合」と言われても、それだけだと遅れてしまいます。
清野:それは、先ほどの話と矛盾しませんか?9時23分に到着できるのに、10時では遅れるというのは。
行動を分解しよう
永田:10時に渋谷集合、というのは、10時に渋谷にいることだけが決まっている状態です。具体的に何時に家を出れば間に合うか、まで調べていないと遅れてしまうのです。渋谷までの到着時間はなんとなく分かっていても状況によっては到着時間が10分以上変わることもあります。
清野:以前、変な場所に集合になって、駅には着いたものの、逆方向だったりして遅れたりということがありましたね。
永田:そのため、私は「9時何分に、この電車で、渋谷駅のこの改札に到着する」と具体的に決めます。そして「9時23分に家を出よう」と逆算するのです。9時23分に出ると決まれば、絶対に動けます。ダラダラして出発時刻やその後の移動がずれてしまう事態をなくすために、事前に調べて具体的に決めているのです。だから、待ち合わせに遅れることも、早く着きすぎることもありません。ぴったりに到着します。
清野:なるほど。私も高校時代、似たようなことをしていました。電車内での単語学習です。「1単語9秒」と決めて、200単語なら30分。電車に乗って降りるまでの30分で、ちょうど200単語見終わると、「今日は調子がいいな」と思えました。逆に197単語しか見られなかった日は、「最悪だ」と感じていました。
永田:それはすごいですね。
具体的な目標を設定し、行動を細かく分解することで、取り組みやすくなるのは確かだと思います。例えば、「英単語を200個覚えなさい」と言われると大変ですが、「1単語9秒で、この単語を見て、この単語を見る」と決めて、それが30分で終わると分かれば、取り掛かりやすくなります。
清野:確かに、英単語を覚えるという抽象的な話ではなく、具体的な行動に分解されているから分かりやすいのですね。
他の勉強に関しても勉強の内容が具体的に分かれば、取り組みやすくなりますね。「カバーを開く」「ペンを取る」「机のどの位置に座る」といった誰でもできるレベルまで分解すれば「勉強するしかない」という状況になるのではないでしょうか。
行動心理学を応用せよ!
やる気の有無に関わらず、行動を始める際に色々と工夫をしてみることがどうも良さそうだとわかってきました。ここでは行動心理学を応用した工夫を紹介します。
「認知的負荷」を減らす
永田:その「分解」が面倒くさい、と感じる人もいるかもしれません。面倒くささが、勉強から「分解」へとずれただけではないか、と。勉強にやる気は必要なくても、分解にやる気が必要になってしまう。
清野:それには行動心理学で言われる「認知的負荷」という理論を応用してみてはどうでしょうか。この理論曰く、タスクの難易度が高いほど、脳は多くのエネルギーを消費し、動きたくなくなってしまいます。そこで、タスクを細かく分解することで、認知的負荷を減らし、行動しやすくするのです。
ただ、「分解せよ」と指示されると、それ自体が認知的負荷になる可能性もあります。
24時間の行動全てを分解しようとすると、それはそれで大変です。東大生も誰もそんなことはしていません。その分解だけで1日が終わりそうです。
そこで、自分が「億劫になる行動」だけを分析すればいいのかもしれません。例えば、家に帰ってすぐに勉強机に向かえばいいのに、ベッドに転がってスマホをいじってしまう。この「フェイント」を分解して、「机に向かうまでに、何が必要だったのか」を分析するのです。
永田:ベッドに腰をかけない、リュックを勉強机の近くに置く、といったルールを作るのも有効ですね。リュックを勉強机に置けば、そこから筆箱を出すなど、自然と勉強モードに移行できます。
ナッジ理論
清野:これは「ナッジ理論」という概念にも通じます。人間は、望ましい行動へと、そっと後押しされることで、意外と行動できるものです。例えば、トイレに「綺麗に使ってくださってありがとうございます」と書かれているのは、トイレを綺麗に使いたいという気持ちを後押しするためです。
先ほどの「フェイント」状態も、ベッドに寝転がらないように、机の上に何か障害物を置くなどナッジ理論で後押しされれば、行動が変わるはずです。
あるいは、否定的な行動を避けるのではなく、机に「すぐに学習机に向かえて偉い」と肯定的な言葉を書いておくのも良いかもしれません。
私は、眠い朝に単語帳を見るのが億劫だったので、靴の上に単語帳を置いていました。靴を取る時に必ず単語帳を手に取るので、そのまま学校に持っていき、電車の中で見ることができるのです。
永田:それは画期的ですね。リュックの中にしまうと、取り出すのが面倒になりがちですが、靴に置いておけば、必ず手に取る機会が生まれます。
清野:ナッジ理論と行動分解を組み合わせて自分が分析した結果、「靴に置く」という行動にしたのです。この方法で、私の英語力は格段に上がりました。
永田:細かいですが、非常に重要なポイントですね。朝の30分が変われば、1年で180時間以上変わります。ほんの少しの後押しで人間の行動が変わることを考えると、「やる気」に頼るのは馬鹿らしくなってきます。
清野:単語帳を取り出す「やる気」を出すのではなく、取り出すのが面倒くさいという外部要因を取り除けばいいのです。意外と人間は単純なので、環境を変えるだけで行動が変わります。
あえて中途半端にする
永田:人間の脳の構造や考え方を利用するのは非常に有効ですね。例えば、参考書や教科書を勉強する際、多くの人はキリの良いところまで終わらせようとしますよね。
清野:それが普通だと思いますが。
永田:しかし、キリの良いところで終わらせてしまうと、翌日、また「始める」のが一番しんどい状況になってしまいます。人間には「途中までやったものを最後までやりたい」という心理が働くので、あえてキリの悪いところで終わらせるのです。そうすると、「昨日の続きからやらなければ」と、翌日の勉強に取り掛かりやすくなります。
清野:本当ですか?中途半端で終わらせてしまうと、自己肯定感が下がりませんか?
永田:だから、「あえて」です。時間を区切ることで、だらだら勉強しなくなるという効果もあります。例えば、「18時まで」と決めていたのに、キリの良いところで英語をやっていて、思ったより進まなかったとします。そうすると、英語を延長してしまい、数学が始められなかった、ということになりかねません。
清野:確かに、そういうことはよくあります。
永田:そして、英語は終わっていますが、数学は始まっていない。どちらもキリが良い状態なので、翌日「どっちからやろうか」となり、どちらも嫌だな、と感じてしまう。
清野:なるほど。
永田:しかし英語が中途半端なところで終わっていたとします。すると、次の日は「まず昨日の続きからやろう」となり、英語の勉強に取り掛かりやすくなります。復習にもなりますね。
清野:言われてみれば、そうですね。
永田:キリが悪いということは、ちょうど良いのです。グータラなのではなく、むしろエリートかもしれません。
清野:納得しました。今まで「キリの良いところまでやるのが正義」だと思っていましたが、革命が起こりそうです。
今日お話しいただいたことが、全て頭の中で繋がりました。キリの良いところまでやりたいと思うから、時間通りに動けないのですね。
そして、永田さんが時間通りに動けるのは、全て「適当に」終わらせているからだと。(笑)
永田:嫌な結論ですね(笑)。しかし、適当にも「良い方の適当」と「悪い方の適当」があります。私は「適切に」終わらせる方です。
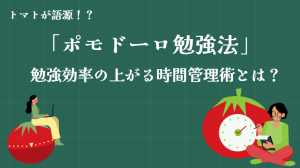
まとめ
行動心理学などのテクニックを用いることで、やる気がなくとも勉強ができることがわかりましたね。他にもこのようなテクニックを発見するのも面白いかもしれません。
私が個人的に行っていることとしては顔を洗う、換気をする、おやつ休憩を挟むなどがあります。このように肉体面からアプローチしてみるのもどうでしょうか?
ぜひ色々と試してみてください!