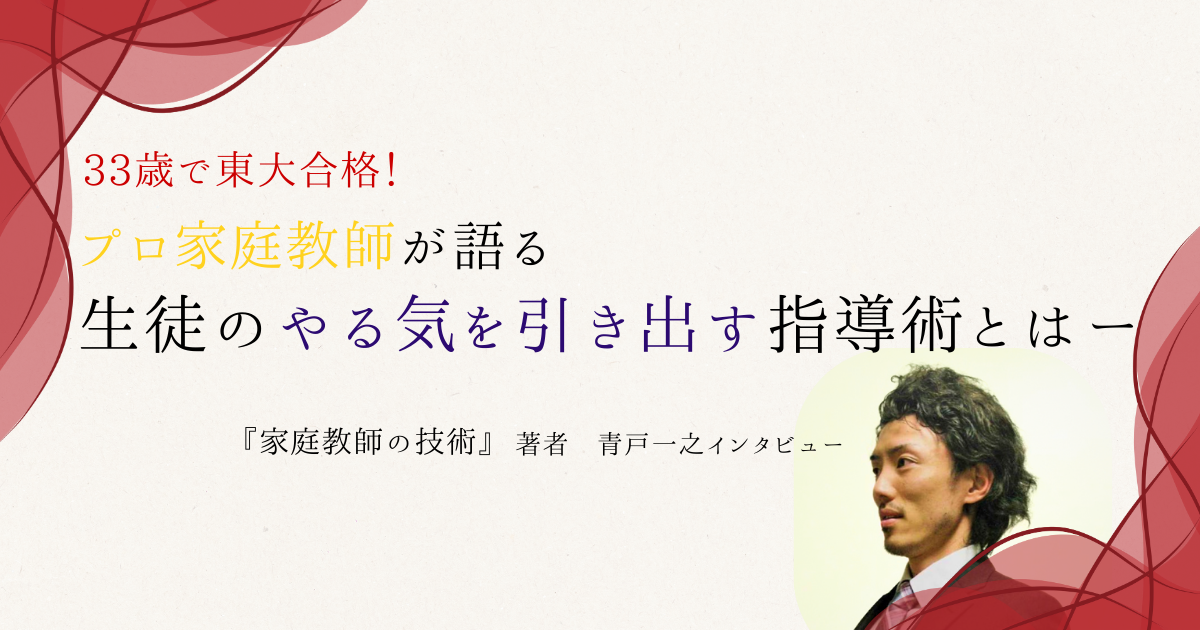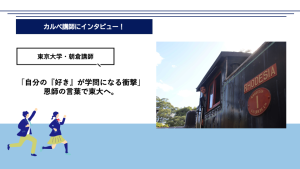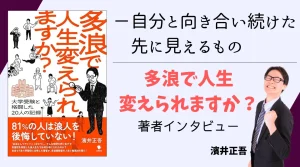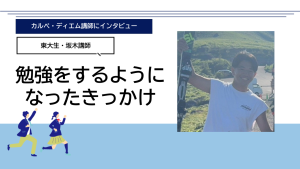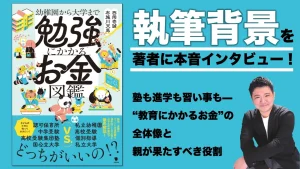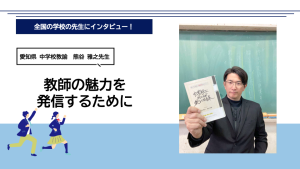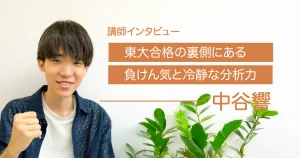家庭教師としての、生徒との接し方が書かれた『家庭教師の技術』。
執筆されたのは塾講師をしながら33歳で東大に合格し、プロ家庭教師・塾講師としてキャリア15年の青戸一之さんです!今回はそんな青戸さんに、この本の執筆に至った経緯や本の内容をインタビューしてきました!
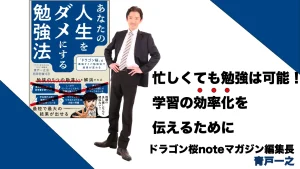
東大生は意外と〝教えること〟が下手!?
——はじめに、この本の内容について簡単に教えてください!
勉強の教え方だけでなく、生徒のやる気や能力を引き出すコミュニケーション術、コーチング法など「前向きに勉強に取り組むサポートの技術」全般を紹介しています!
——なるほど!青戸さんがこの本を書かれた背景はどのようなものだったのでしょうか?
私は社会人になってから東大受験を志しました。もともと地元の鳥取県で塾講師をしていましたが、なかなか苦戦することが多かった。当時の生徒は学校の授業についていけない子やマニュアル通りではなかなか伝わらない子など、「教える」だけでは不十分であると気付かされました。どうすれば伝わるか、理解度に合わせた工夫が求められた。
私が東大受験を志したのは、塾講師としての限界を感じたところにあります。当時受け持った東大志望の生徒を、最後まで完璧にサポートしきることができなかった。私自身、大学受験を完走した経験がなかったんです。このままではいけないと思いました。生徒の過酷な旅路を応援するならば、自分もその経験を背負うべきでしょう。だから、東大受験にチャレンジすることにしたんです。30歳のときでした。
33歳で東大に合格して、ようやく「真正面から生徒と向き合える」と思い、再び塾講師として働き始めました。そこの塾は講師が全員東大生でした。東大生って、頭がいいイメージがありますよね。勉強法に工夫を凝らして東大までたどり着いた人たちなのだから、教えるのもうまいと思い込んでいました。だから、その塾で働きはじめたときは、期待に胸を膨らませていたんです。ところが、実際に東大生と一緒に教える立場に立ってみて、何度も「あれ?」と思わされた。一番基本的な「目線を合わせる」ことが、できていないんです。
例えば、中学生向けの数学の授業中に、いきなり「これは演繹的に考えると〜」と言っても、伝わるわけないですよね。「演繹って何?」って、大人でも思いますよ。でも、彼らは「知ってて当然」みたいな顔をして、どんどん授業を進めていく。質問しても「これの何が難しいの?」って顔をされてしまう。これでは、信頼関係も築けません。ですが、東大生講師には、こういう子は少なくない。
教える側が思い描く「ここまではわかっている」の前提がずれていると、当然ながら生徒も理解できない。このとき初めて、「学力が高いことと教えるのが上手いことはイコールじゃない」と気づきました。
勉強の教え方だけでなく、まずはどのように生徒との信頼関係を築くか。生徒のモチベーションをどう上げるか、どうスケジュール管理をして導くかは、その後の話です。ですが、こうした基本はまだまだ広まっていないように見える。ときにはメンタル面のサポートも含めた”教える技術”が必要になります。そうした気づきや思いから、この本を書こうと思ったんです。
——『家庭教師の技術』というタイトルからは、家庭教師や塾の先生をしている方たちに向けたものという印象を受けますが、それら以外の人にも役に立つ内容なのでしょうか?
「教える」のは先生だけの仕事ではありません。部下に仕事を教えたり、子どもに勉強を教えたり、誰もが「教える」経験を避けては通れないんです。下手な教え方は、教える側と教えられる側両方にとってストレスになりうる。信頼関係の築き方や、相手の気持ちを汲み取りつつどう自分の考えを伝えるかが重要です。本書には「人に何かを伝える力」や「人との関わり方のコツ」がたくさん収録されています。人と向き合うあらゆる場面で使えるヒントが詰まった本になっていますよ!
東大受験を経験して生徒に伝える「言葉の力」が変わった
——家庭教師・塾講師に対する青戸さんなりの信念や情熱、やりがいは何ですか?
私の信念は、「生徒が自分の頭で考え、自分で主体的に勉強できるようになること」です。
これってなにも勉強に限ったことではなく、大人になっても役に立つことなんですよね。勉強って、辛いことも多いでしょう。でもその過程で悩んだり、壁にぶつかったりした経験が、自分を強くしてくれる。大人になってから「あのとき勉強を頑張ってよかった」といってもらえる、そのときのために私自身、家庭教師を頑張っている部分もありますね。
そしてやっぱり一番嬉しいのは、生徒が「自分でやれるようになった」と感じたとき。そして、それを保護者の方が喜んでくださったときです。
——青戸さん自身が東大受験の前後で塾講師として具体的に変わった点はありますか?
一番変わったのは言葉の力ですね。
東大受験を経験するまで私は、高校卒業後にゲームの専門学校に通って、その後はフリーターとしてオーストラリアにワーキングホリデーに行ったり、肺の病気を患って一年間家に引きこもったりしていました。大学受験の経験がなかった当時は「努力は裏切らない」みたいな、どこかで聞いたようなことを生徒に言っていました。
でも東大受験を経験したことで、「結果がすぐ出なくても、自分が積んだ努力は人生の中のどこかで回収されるから大丈夫」って、実体験に根付いた励ましができるようになったんですよね。もちろん、東大に合格したことも自信になりました。東大受験の経験が僕の家庭教師人生に大きな追い風となっています。
大人になってからの勉強の楽しさをこれからも伝えていきたい
——今作は、「教え方の技術」を軸にした企画でしたが、今後の展望をお聞かせください。
私自身、社会人になって大学受験を経験してから、人生の道が開かれました。勉強は自分の視野を広げて、新しい世界を見せてくれるものだと思います。実際、大人になってから勉強の楽しさが分かる人は多いでしょう。
大人になってからの勉強の楽しさを伝えられるようなコンテンツをこれからも作っていければと思います!
——青戸さん、インタビューありがとうございました!
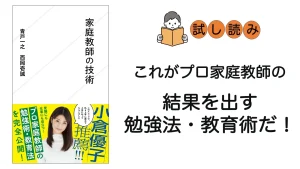
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。