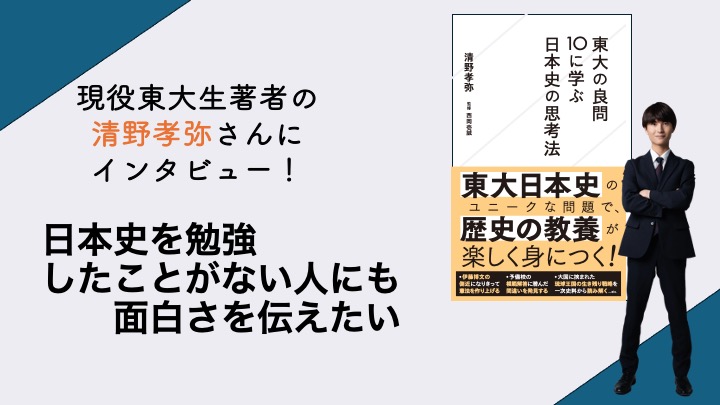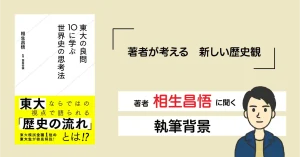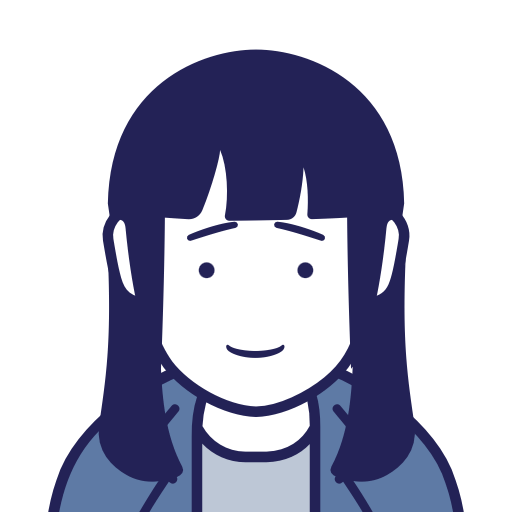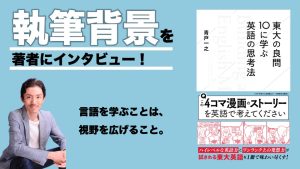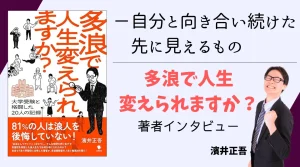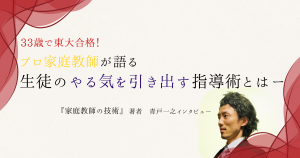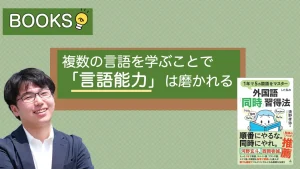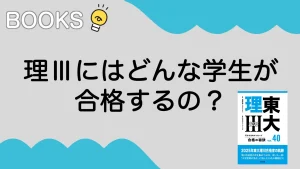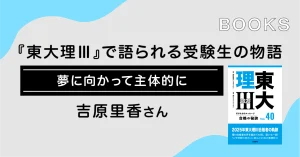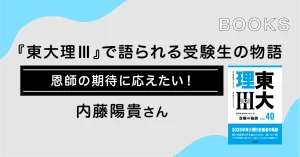東大日本史の入試問題は、単なる知識の暗記ではなく、与えられた資料を読み解き、深く思考する力を求めることで知られています。この特徴的な入試問題から、現代を生き抜くための思考法を学ぶ一冊『東大の良問10に学ぶ日本史の思考法』を執筆された清野孝弥さんに、本書の魅力や歴史を学ぶ意義について伺いました。現役東大生で、塾講師の経験もある清野氏が、本書に込めた思いとは。
本書について
ーー本日はよろしくお願いいたします。まず、本書の内容について簡単にご説明いただけますでしょうか。
本書は、日本史を勉強したことがある人も、そうでない人も、歴史の思考が学べるように執筆しました。今出ている日本史の参考書や本の多くは、細かい人物名や事件名などの暗記か、その情報を入手するために読む方が多いと思います。しかし本書は、知識がなくても、「資料や文章から何を読み取れるか」を考えていただき、日本史以外の分野にも応用できる考え方を学んでもらうことを目的にしています。できるだけ知識に頼らず、考えることによって日本史の面白さを感じてもらえるような本になってるんじゃないかなと思います。
ーーありがとうございます。このような本を書こうと思った背景はなんですか?
東大日本史の入試問題は、全国でも非常に特徴的で、知識が一切問われないと言っても過言ではないです。むしろ、与える資料から読解を重ねていって、日本史の裏側にある思考を探求する。そんな入試問題に、より多くの人たちに触れてもらいたいという思いがあり、このスタイルにしました。
「知識よりも思考」というメッセージは、数十年前から東大日本史の入試問題に受け継がれているような考え方です。ただ実際、他の大学の入試や、一般的な学校の日本史教育では、あまりそういった問題に触れる機会がないので、もったいなさを感じます。軽くでもいいので、みんな東大日本史の問題に触れてみれば、歴史の面白さを改めて感じることができるんじゃないかなと。そのような想いもあり、東大を受ける人以外の人に向けて、入試問題をわかりやすく書き出しました。
本書のポイント
ーー入試問題の10問は何を基準に選びましたか。
3つポイントがあります。
1つ目は、資料読解の力がどれだけ試される問題かです。前提知識で解けてしまう問題は極力避けて、純粋に与えられた資料を読解するだけで解ける問題を選びました。
2つ目は、日本史範囲の網羅性です。本書を第1問から第10問まで全部読み通していくと、なんとなく日本史の全史が分かるようになっています。問題の背景となっている内容が被らないように調整しました。例えば、第2問から第5問にかけては、飛鳥時代や平安時代から、戦国時代、江戸時代にかけての歴史を扱っているのですが、問題を1個1個解いていくと、つながりが感じられるんです。1冊読み終わったら日本史自体もわかるのが、嬉しいポイントです。
3つ目は、単純に面白い問題かどうか。例えば第9問、第10問は結構ユニークな問題です。第9問の「歴史の人物になりきって政策を考える問題」は、今の推薦入試にもつながるような、面白い思考が隠れています。また、第10問の「日本国憲法の弱点を考える問題」は、日本史というより、倫理や公共に近い気がします。一般の読者の方が取り組みやすく、興味を持ちやすいテーマを考え、この10問を選定しています。
ーー日本史の思考は、何かに応用できると思いますか?
歴史には法則性があり、似たような事象を繰り返す性質があります。歴史全体を通貫するルールが分かってくると、現代を生きていく上でも役に立つ時があります。
例えば、カリスマ的な政治家が出てきた世の中が、その後どうなるか。国民の暮らしが苦しくなった時、国はどのような財政政策をすれば良いのか。2020年にコロナが始まった時は、みんな第1次世界大戦の頃のスペイン風邪を振り返って考えました。今を生きる上で参考になるものが日本史にはたくさんあるので、そういう意味でも日本史の思考を身につけることは重要だと思います。
第1問をピックアップ
本書の第1問は、特に外交のメカニズムが分かるのが面白いところだと思います。外交における本音と建前が両方とも存在するような局面は、1300年前に限った話じゃないんです。今の日常生活やビジネスの世界、もしかしたら友達関係でも、同じことが起きていて、応用できる局面がたくさんあります。歴史と現代のつながりが感じられて面白いのではないでしょうか。
実はこの第1問って、昔、僕が塾講師として小学生に東大入試問題を解説する時に、よく使っていたんです。つまり小学生でも分かるぐらいのシンプルなロジックを扱っているわけです。ではなぜこれが東大入試になっているのかというと、そのロジックを資料から読み取る必要があるから。そのため読み取る過程ではさまざまな応用が散りばめられていますが、最終的に判明するものは、実は結構わかりやすいんです。だからこそ、最後まで読んだ時に腑に落ちる部分は多いと思います。
著者の日本史勉強法
ーー次に東大日本史の勉強方法についてお聞きします。清野さんは日本史の受験勉強をどのようにしましたか。
日本史における重要な論点を理解する必要があったので、まずは駿台文庫さんの、「日本史の論点」という本を読みました。
日本史の論点ー論述力を鍛えるトピック60ー (駿台受験シリーズ)
この本では、日本史の中でも特に重要なテーマが取り上げられています。例えば本書(東大の良問10に学ぶ日本史の思考法)で言うと、外交問題における新羅と日本の関係性や、時代ごとの幕府と天皇家の関係性など。このような論点を知らずに勉強すると、日本史が全部重要に思えてきて、同じ「濃淡」で勉強することになってしまいます。だからこそ、このような参考書を活用しながら、教科書の中でも特に知らなければいけない点を学び、かなり効率的に勉強できたと思います。
さらに、東大入試の日本史は、最新の日本史研究をある程度知らないと対応ができないという難しさがあります。今何が研究されているのかを分析して、東大教授たちがどんなことを問題に出しそうなのか、ある程度山を張った勉強をすることがあります。裏を返すと、大学水準の日本史を知らないと対応ができないぐらい、東大日本史はかなり奥深く、難しいんです。6割7割ぐらいまでは資料の読解力で解けても、最後の3割は、歴史学において論点になっているポイントを抑えておかないと、裏まで読解しきれないんです。
そのため本書でも、「助詞や表現1つ1つにもこだわって読解しましょう」と口を酸っぱくして述べました。それは、1個1個の表現の裏側に、いろんな学説の対立や、最新の研究の動向が秘められているからなのです。その情報を高校生の時に知るためには、例えば日本史リブレットのような雑誌があります。
こちらは、最新の学説や、研究者の興味関心が分かる本です。どこまで勉強するかは学習の進捗によって異なりますが、私や周りの受験生は、こういったものを読みながら、「教科書にはこう書いてあるが、本当は教授たちはこう思っているのではないか」まで含めて勉強してました。そのぐらい深く勉強すると、東大日本史の問題を見た時に、何を読解しなければいけないのかが、ある程度分かるようになってきます。
著者について
ーー初めての執筆でしたが、こだわった点はありますか。
細部までこだわって原稿を作り切ったところです。東大日本史の問題が、資料を一字一句細かく読み取ることを理念に掲げてる問題なので、その解説も、一言一句にこだわって、丁寧に伝えるのが重要だと思いました。
また、自分が日本史を勉強する前の初心に戻って書きました。今、歴史に興味がない人が、どうすれば興味を持てるようになるか考えてみました。ある程度知識があることを前提に書かれている本を読むと、「日本史を勉強していない自分は受け付けられていない」と、壁を張られている感覚になってしまいます。そのため、壁をできるだけ取り除きつつも、内容はハイレベルで東大入試を使えるようなレベルまで落とし込むことを意識しました。
ーー本書の読者に伝えたいことを、一言で教えてください!
単純に、「歴史に興味なかった人も手に取ってほしい」です。歴史に興味がない・歴史が嫌いなのは、もしかしたら暗記が苦手なのが原因なのかもしれません。歴史は、暗記が全てではありません。むしろ、数学や英語の勉強のように、頭を使って考える点に、歴史の魅力があることを知ってほしいです。
ーー最後に、今後挑戦したいことを教えてください!
中高生や、学び直しをする社会人に向けて、日本史のみならず、世界史や歴史総合などの歴史科目について、より分かりやすい本を書いていきたいです。歴史を上手に体系的に翻訳・整理しながら、いろんな本を通して代弁していければ、より興味を持つ方が増え、進路の広がりにもつながるのではないでしょうか。
ーー清野さん、ありがとうございました!!
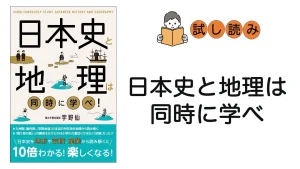
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。