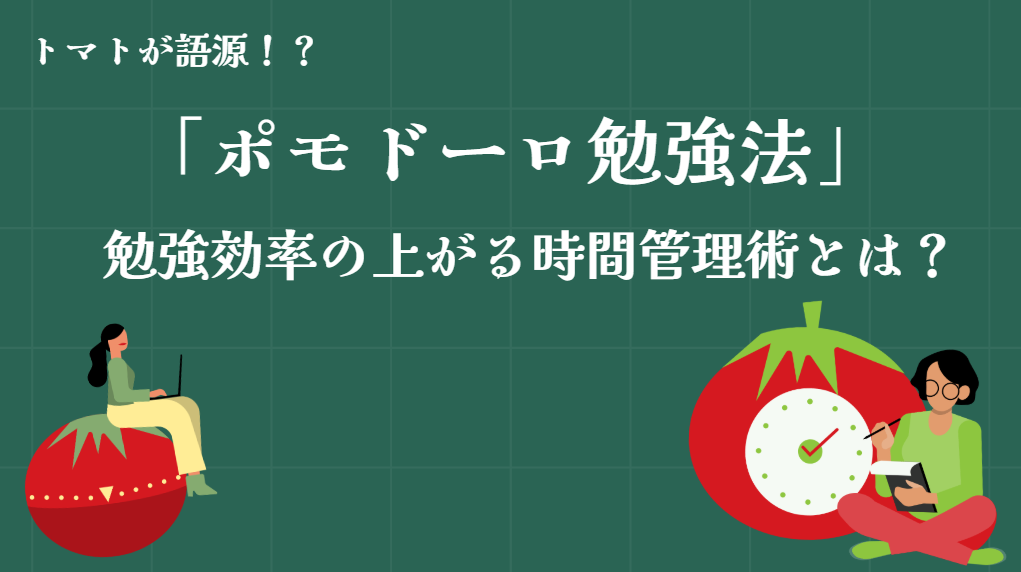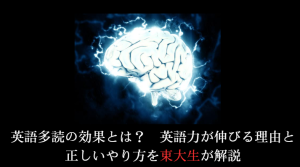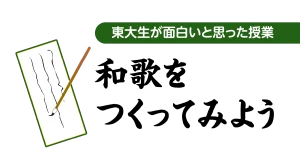みなさんは「ポモドーロ勉強法」を聞いたことがありますか?この名前を聞いたことがなくても、「時間を区切って勉強すると効率がいい」なんていう話は聞いたことがあるかもしれません。実際はどうなのでしょう?そして、ポモドーロ勉強法とは何なのでしょうか?
今回は、時間を区切って休憩を挟みながら勉強する「ポモドーロ勉強法」について、そのやり方からメリット・デメリット、そして適切な使い方まで、現役東大生ライター、碓氷明日香が徹底解説します!
ポモドーロ勉強法とは?
そもそも、「ポモドーロ勉強法」とは何を指しているのでしょうか。ここでは、その名前の由来とやり方について説明していきます。
「ポモドーロ」ってどういう意味?
「ポモドーロ」とはイタリア語で「トマト」を意味する単語です。トマトソースの意味もあり、さらに派生してトマトソースパスタの意味で使われることもあるようです。
ポモドーロ法は、イタリア人のフランチェスコ・シリロが提唱した時間管理術で、シリロが大学生時代に使っていたキッチンタイマーがトマトの形をしていたことにちなんで名付けられました。
詳しくは下で説明しますが、25分間集中して作業し、5分間休憩する、計30分を1ポモドーロとして、それを繰り返して勉強するのがポモドーロ勉強法です。単位がトマトだなんてかわいらしいですよね。
基本のやり方
①今日やるべきタスクを書き出し、キッチンタイマーを用意する。
②タスクの優先順位や自分のモチベーションを踏まえて、どの順番でこなしていくかを決める。
③タイマーを25分にセットして勉強をスタートする。
④タイマーが鳴ったら5分計って休憩を挟む。これで1ポモドーロ終了。
休憩の間は娯楽に手を伸ばすというよりも、瞑想をしたり部屋の中を歩いてリフレッシュしたりするのがオススメです。
また休憩の終わりを告げるタイマーの音で次のタスクに取り掛かります。これを繰り返していけばいいのです。非常にシンプルで取り入れやすいですよね!
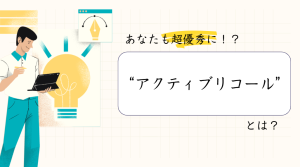
ポモドーロ勉強法のメリット
では、ポモドーロ勉強法をやることによって、どんな効果が得られるのでしょうか。ここでは、この勉強法のメリットを3つに分けて説明していきます。
勉強効率が上がる
まず、勉強効率が格段に上がります。時間を決めることで、タスクを時間内に終わらせようという意識が働き、普段はダラダラとやっていることもテキパキと進めることができるのです。実際、生活の中でこのようなことを体験したことがある方も多いことでしょう。
そして、適度に休憩を挟むことで、メリハリがつきます。25分間は没頭モードになって、集中して机に向かい、休憩の5分間は頭を休ませ、のんびりする。これを繰り返すだけで、机に向かっている時間が一気に充実したものになります。
どうしてもダラダラ勉強してしまう、問題集と向き合っていても別のことを考えてしまって手が止まってしまう……。そんな方にオススメな勉強法、というわけですね。
達成感を感じられる
次に、タスクをこなすことで達成感を感じられるようになります。1ポモドーロを終えるごとに、勉強した、という実感が湧くのです。ノルマを一つ一つ目に見える形で消化していけるので、モチベーションにつながります。
勉強をし続けるには、根気が必要です。人間の意思は弱いことも多いので、すぐに誘惑に手が伸びてしまいます。そんな中、苦しい勉強を続けるには、「モチベーションの維持」が非常に重要です。そして、このポモドーロ勉強法こそがその役割を担ってくれるのです。
頭と心の休憩になる
長時間頭を使うと、段々疲れてきてしまいますよね。テスト終わりなどに、体を動かしたわけではないのに疲労を感じるのは、頭が疲れているからです。このいわゆる「脳疲労」は、少しの休憩を挟むことで解決できます。25分間集中した後に5分間ぼーっとするだけで、また次の25分間、頭をフル回転させることができるのです。
また、勉強が楽しいと思っている方は長時間ぶっ続けで問題を解いていても何も感じないかもしれませんが、そうではない方が多いと思います。5分の休憩があることで、精神的にも少し余裕が生まれますよね。また次の1ポモドーロに集中しようという気になるはずです。つまり、この勉強法は頭と心の休憩をしながら勉強ができるというわけなのです。
ポモドーロ勉強法のデメリット
一見、利点ばかりのように見えるポモドーロ勉強法ですが、実はデメリットもあります。どこに注意すればいいのでしょうか?
集中力が途切れてしまう
まず1つ目は、25分という区切りが集中を切らしてしまう可能性がある、ということです。今日は調子がいいな、ノっているな、と感じる時があると思います。そんな時、もっと長く解き続けられそうなのに、25分でタイマーが鳴ると、せっかくの集中が途切れてしまうかもしれません。
では、どうすればいいのでしょうか?
答えは簡単!調子がいい日、やる気に満ち溢れている日は1ポモドーロの時間を長めに設定すればいいのです。40分や1時間でタイマーをセットして取り組めば、途中で邪魔されることはないですよね。その日のモチベーションや体調などを踏まえて、自分に最適な1ポモドーロを見つけるようにしましょう。
時間の区切り方が適していない場合もある
2つ目は、勉強の内容によって、25分という時間の区切りが適していないことがあることです。例えば解答時間の目安が50分の長文読解の問題があったとして、それを25分で切り上げるのは適切とは言えませんね。また、逆に10分で終わるプリントに25分取るのも時間の無駄です。他にも、過去問を25分に区切ってやっても意味がありません。そもそも過去問というのは、試験時間を通して集中を保ち、時間内に全ての問題を解き終える練習ですからね。
これの対処法も1つ目と同じ。1ポモドーロの時間を変えましょう。教材や内容によって適切な時間設定をして取り組むことが大事になってきます。
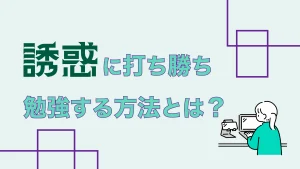
ポモドーロ勉強法の適切な取り入れ方
ここまでメリットとデメリットを見てきましたが、では、どうすればポモドーロ勉強法は真価を発揮するのでしょうか?
そもそも、このポモドーロ勉強法は、「ぶっ続けで勉強すると疲れるし効率が悪いから、適度に休憩を取りましょう」ということを一番伝えたいのではないでしょうか。そして、その最適なやり方は25分作業して5分休憩するセットを繰り返すこと。つまり、この時間は1つの目安なのです。
その上で、重要なのは「1ポモドーロに対して目的意識を持つこと」「状態・内容に応じて時間を変えること」です。最初にタスクを書き出して優先順位を決め、1ポモドーロの中でこれを終わらせる(理解する)ことを目標に、しっかり集中する。その時間は、単語や計算といった単純なタスクなら25分に則り、数学の大問や英語の長文読解などをやる時は40分なり1時間なり(過去問なんかは2時間3時間になることもあるでしょう)、適切な時間にする。そしてしっかり休憩を取る。これが、ポモドーロ勉強法の適切な使い方なのです。
一つだけ注意が必要なのは、タイマーとしてスマホを使用しないということです。5分の休憩時間にスマホを見るのもやめた方がいいでしょう。スマホのアラームが鳴っても、娯楽に一切見向きもせず、休憩後すぐに切り替えて勉強できます、という方は使ってもいいですが、そんな強靭なメンタルの人は相当少ないはずです。時間を計る機能しかないキッチンタイマーを使ってください。そして、休憩時間もスマホを見ず、ぼーっとするといいでしょう。
まとめ
今回は、ポモドーロ勉強法について解説しました。ポモドーロ勉強法だけでなく、どんな勉強法も提唱されている理由があります。それを理解し、適切な形で日々の勉強に取り入れていけば、成績アップ間違いなし!
まずは、すぐにキッチンタイマーを買ってきましょう。トマトの形のものが売っているといいですね。ぜひ、今日のこの後の勉強から、ポモドーロ勉強法を取り入れてみてはいかがでしょうか。
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。