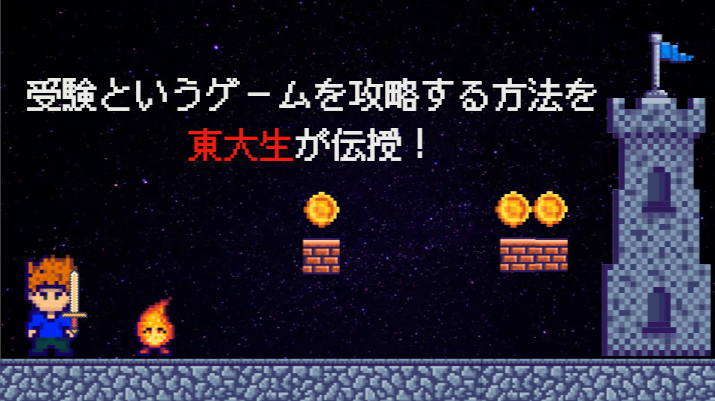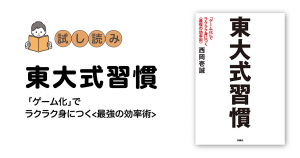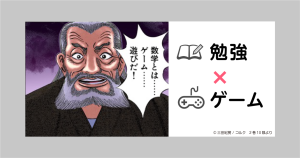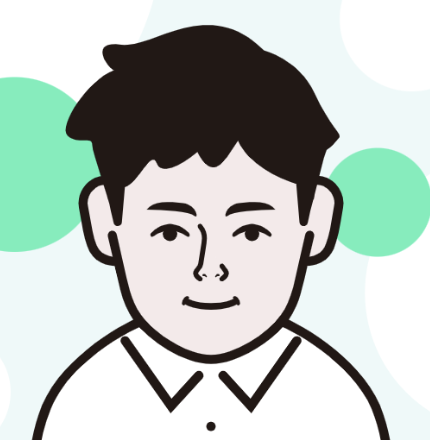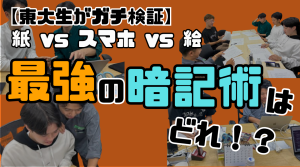ゲーム好きのみなさん、こんにちは。みなさんは受験勉強を「ゲームの時間を削ってくる邪魔なもの」と思っていませんか?実は、受験勉強、ひいては受験そのものは、とても競争的で魅力的な“魔のゲーム”なのです。真のゲーマーなら、受験も見事に攻略できるでしょうし、受験勉強をうまくやりくりできれば、他のゲームも上達するはずです。
実際、プロゲーマーやRTA走者の中には高学歴の方が多くいます。
この記事では、受験というゲームの魅力と、なぜ受験勉強をすると最終的にゲームの腕前が伸びるのかについて、現役東大生が解説します!
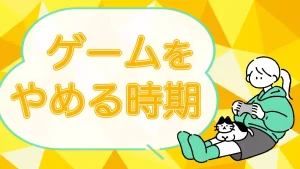
受験は魔のゲーム
受験や受験勉強がゲームだと思える理由
どうして受験や受験勉強がゲームのように思えるのでしょうか?
これは受験の流れを分解してみるとよくわかります。
受験は、「ラスボス」である本番の受験と、その前段階の「準備パート」である受験勉強に分かれています。
受験(ラスボス)に挑めるのは年に数回だけで、結果は合格か不合格の二択。非常にシンプルです。
また、このラスボス戦は、これまでの勉強成果を実践で試す「対戦ゲーム」のような要素と、上位何%に入らなければ生き残れない「レースゲーム」の要素を含んでいます。
準備パートの受験勉強は、どのように勉強するか(=ビルド)を最適化し、自分のレベルを上げていく「ハクスラゲーム」的な要素が強いです。
受験は超大人数が参加するゲーム
受験をゲームと考えると、実は非常に多くのプレイヤーが参加しているゲームだとわかります。
例えば、令和7年度の共通テストの受験者数は約46万人。これは鳥取県の人口(約52万人)に匹敵する人数が一斉にプレイしていることになります。
さらに特定の大学の一学部だけを受験する人数でも、数十〜数百人のプレイヤーが一斉にレースを行っているわけです。
これは一年あたりの参加人数であり、過去の総人口を考えれば、日本の大卒率が約2割であることから、少なくとも2000万人はこのゲームのプレイヤーといえます。
大量のプレイヤーの中でどれだけランキングを上げられるかが、受験攻略の肝となります。
受験というゲームをクリアして得られる報酬
受験に合格したゲーマーが得られるメリットは多岐にわたります。
まず、生涯年収が高く、余暇の多い職業に就ける可能性が広がること。
こうした職に就ければ、ゲーム機やゲームソフトを買う際の金銭的な心配が減り、社会人になってもゲームをプレイする時間を確保しやすくなります。
また、大学のサークルに所属し、ゲーム仲間が増えることも大きなメリットです。
高校の部活よりも幅広いジャンルのサークルがあり、学内やインカレのゲームサークルで、チームを組んで大会に参加したり、仲間と交流したりできます。
多くのサークルは「大学生であること」を参加条件にしているため、受験というゲームをクリアすることは、このメリットを得るための必須条件なのです。
受験勉強の途中にもトロフィーがいっぱい
受験の最終報酬は合格ですが、受験勉強の道中にも多くの中間報酬があります。
模試で順位が上がった時、苦手科目の点数が伸びた時、参考書をやり切った時など、ゲーム内で新しい称号やトロフィーを獲得した時の喜びに似た達成感があります。
こうした小さな成功を積み重ねるうちに、気づけば自分のレベルが大幅に上がっている。これも受験の楽しみのひとつです。
受験勉強をうまくできる人はゲームもうまいわけ
受験や受験勉強をゲームとみなせることをお伝えしましたが、このゲームを攻略し楽しむためには、ただひたすら勉強するだけではなく、戦略的思考を持ってプレイする必要があります。
ここでは、そのコツを3つ紹介します。
これを知れば、受験勉強に真剣に取り組むことがゲームの腕前向上につながる理由がわかるはずです。
コツその1 挑むボスについてしっかり観察すること
受験というゲームをプレイする際、まずはラスボスである志望大学・学部を決めることが必須です。
そして、そのラスボス攻略のために、受験方式、必要科目、合格に必要な点数などの情報を徹底的に調べましょう。
例えば、社会科目が2科目必要ない大学に対して、世界史も日本史も両方勉強するのは無駄ですよね。
さらに、科目ごとの出題傾向や問題の難易度なども、参考書や模試を通じて事前に把握しておくことが重要です。
現役生は皆初見プレイヤー。受験は失敗した場合、再挑戦まで時間がかかるため、攻略情報は隅々まで確認すべきです。
コツその2 自分のレベルを把握すること
攻略情報があっても、プレイヤースキルがなければクリアは難しいもの。
受験攻略に必要なスキルは、テストや模試を受けて初めて点数という形で確認できます。
そのため、模試やテストを手を抜かずに受け、点数をもとに振り返りを行い、次にどうレベルアップするかの作戦を立てることが大切です。
コツその3 環境を選ぶこと
受験勉強の効率を上げる「バフ」には、集中できる環境に身を置くことが挙げられます。
逆に集中できない環境は「デバフ」になってしまいます。
ゲームをする時間を確保するためにも、勉強の効率化は重要です。
ここでいう環境とは「場所」「人」「教材」の3つです。
- 場所は、うるさい場所やスマホ・パソコンなど誘惑が多いところを避ける。
- 人は、一緒に勉強する友達や教えてくれる先生を選ぶ際、真剣に自分を支えてくれる人や高め合える人を選ぶ。
- 教材は、自分のレベルに合った適切なものを選ぶ。
周囲に良い仲間がいれば、教材選びの相談もできるはずです。
受験を“やらされるもの”から“攻略するもの”へ
受験勉強は、自分というプレイヤーを成長させ、限られた時間で最高の結果を出すための総合戦略ゲームです。
攻略の鍵は、敵(志望校)を分析し、自分のレベルを正確に把握し、最適な環境を整えること。
これは、あらゆるゲームで上達するために必要な基本戦略と共通しています。
だからこそ、受験を真剣に攻略しクリアしたとき、あなたは単に合格証を手に入れるだけでなく、自分を分析し、努力を積み上げ、困難を乗り越える総合力を持ったプレイヤーになるのです。
さあ、ゲームクリア目指して頑張っていきましょう!!
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。