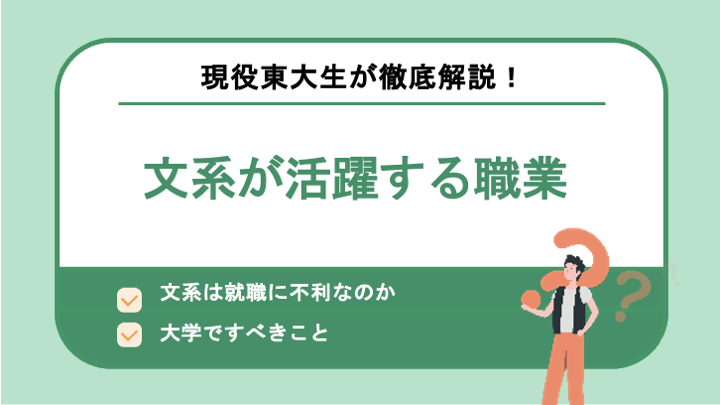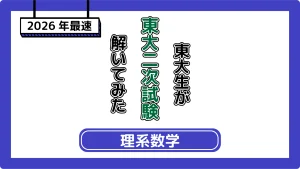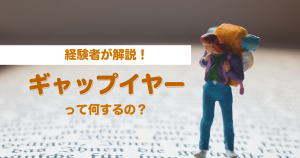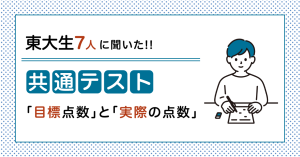大学生は夏休みに入り、就職活動が本格化していく時期になりました。
多くの大学生は大学3年生になると就職活動を開始し、サマーインターンなどに参加したり、自己分析を始めたりしていることでしょう。
さて、昨今では「理系が就職に強い」といったような風説がよく見られます。
確かにインターネットやITが発達した現在において理系分野の勉強内容は「働く」というイメージにマッチしやすいのかもしれません。
しかし、文系の学生にも有利に働くスキルが存在し、理系分野の学生と十分にわたりあうことができるでしょう。
今回は就職活動に悩みを抱える文系の学生、あるいは文理選択において文系学生の就職状況が気になる方々に向けて、文系の強みとそれを活かすための勉強法についてご紹介していきます。

文系が活躍する職業と有利な勉強法
さて、一言に文系の活躍することのできる職業といっても専攻する分野によって全く就職先は異なると言えるでしょう。
そもそも文系の学部には、どんな学部があるのでしょうか?
人文科学であれば哲学、言語学、文学、歴史学などがあります。
社会科学であれば、政治学、法学、経済学、社会学、心理学、メディア学、教育学などが存在しています。
その他にも近年人気の学際的な学問分野である、国際関係学や文化研究に関する学問なども存在しています。
このように一口に文系といっても強みや想定されるキャリアパスというのは全く異なるのです。
ここでは人文科学、社会科学の2つの専攻に分けてお話ししていきます。
人文科学専攻について
人文科学は歴史学や哲学など一見就職にはあまり結びつかないような学問分野だと捉えられがちです。
しかし、人文科学を専攻する人間が重宝される場合も当然存在します。
人文科学の強み
まず、そもそも人文科学分野で養われる力とはなんでしょう?私は以下のようなものを考えます。
言語力
1つには言語力があるでしょう。全ての人文科学分野の研究、勉強は過去の資料や文学作品を読むことから始まり、その解釈を行ったり、さらに発展させることで学問として進化を遂げています。
人文科学を専攻していれば、必然的に大量の書物を読み、解釈し、それを現代に即して伝えるという作業が必要になります。
その過程で知っている言葉の数や伝える能力は格段に飛躍すると考えられます。
批判的思考
次に挙げられるのは批判的思考です。ここでいう批判的思考というのは、ロジックを組み立て、その真偽を判断する能力をいいます。
例えば哲学において言えば、過去の文献や主張の解釈をする際、大切なのは全てを鵜呑みにすることなく、その説の強み、そして弱みを議論することです。
様々な言説や主張においてプロコンを考えることは、ビジネスの分野においても必須の力となります。
発想力
発想力も強みと言えるでしょう。
ここでいう発想力というのは奇抜な考えを一から生み出せるということではなく、知っている考え方や言葉が多様なため、そこから新しく生み出すことのできるフレーズやアイデアが多様化しているのではないかということです。
出版社やテレビ業界、広告業界においては高い言語能力に加えて発想力が重宝されます。
人文科学専攻の考えられるキャリアパス
次に人文科学専攻のキャリアパスについてご紹介していきます。
まず1番に考えられるのは教育に携わる企業や職業に就くことです。
学校の先生であったり、リクルートといった教育系の会社に勤めることが考えられます。
これらの会社や職業においては、哲学や歴史学を深く知っているといった人文科学分野専攻の強みをそのまま職業に活かすことができるかもしれません。
次に考えられるのは出版やメディア系です。
これらの職業では、あなたの独自の専攻が重宝される機会が巡ってくる可能性が高いでしょう。
テレビや本では、頻繁に哲学や歴史に関する特集やコーナーを見かけることがあります。
それを考えると、こういった学問を専攻している人材は重宝されやすいかもしれません。
ほかには公共や行政においての就職も考えられます。
国家公務員であれば文化庁、地方公務員であれば観光振興などにおいて、歴史的な知識を活かすことができるかもしれません。
社会科学専攻について
続いては社会科学専攻についてお話しいたします。
社会科学専攻は経済学や法学部など、「実際に社会に出て役立ちそうな学問」だと思われがちです。
しかし自分は「経済学部だから大丈夫」とたかを括り、あぐらをかいている方は要注意です。
社会科学専攻の強み
社会科学専攻の強みは様々考えられますが、大きく以下のようなことが考えられるでしょう。なお、専攻分野によってある程度異なることはご了承ください。
社会の仕組みを理解する力
1つは実学ならではの社会の仕組みを理解する力です。法学であれば、現代の世の中にどのような法律があり、仕組みがどうであるのか、経済学であれば商品の売れ方から、需要と供給の理論まで幅広く学ぶことができます。
結果として世の中の仕組みについてより詳細に、単純化された状態で理解を進めることができるでしょう。
この幅広い社会に対する理解能力は国際機関や、世界をまたにかける大企業において重宝されることでしょう。
データ理解能力
社会科学分野においてデータや統計学を扱わない学問はほとんど存在しないといっても過言ではないでしょう。
これによりデータに対するリテラシーが向上するため、様々な政策や企業方針を立てる際に役立つことは間違いないでしょう。
現代では多くの意思決定場面において、数値的根拠が求められるため、データリテラシーが高い人材の確保は必須となっているのです。
また、データの使用に伴い、プログラミング言語やExcelなどの技能も向上させることができます。
多様な観点を生み出す力
社会科学を専攻する分野の人間には、それぞれの学問に即した思考の型というものが存在すると私は考えます。
例えば、社会学であれば人間関係や社会構造、経済学はインセンティブや市場原理、政治学は権力やガバナンス、心理学では個人の行動や認知などの観点から物事を見ることがしばしばです。
そのため、それぞれの学問分野を専攻する人を集めることができれば、全く異なった視点から物事を検討することができるのです。
社会科学を専攻することによって思考フレームが構築されることは、その人独自の発想が生まれることをサポートしてくれることでしょう。
社会科学専攻が気をつけるべきこと
さて、ではこの章の文頭で述べた社会科学専攻の方が就職において気をつけるべき点とは何でしょう?
それはズバリ「差別化」だと言えます。
自分の周りの文系の友人を見渡してみてください。おそらく経済学部や法学部の友人が多くを占めることでしょう。
人文科学専攻の人間に比べて社会科学専攻の人間は差別化を図ることが難しいのです。
〇〇大学経済学部や〇〇大学経営学部だと述べる就活生が無数にいる中で、どれだけ中身のある勉強をしたかどうかが本当は大切なのです。
日本においては、「ガクチカ」というものが就職活動において非常に重要視されます。
もちろん持ち合わせのスキルなどが多いに越したことはありませんが、就職後の教育が重視される日本においては、生半可な知識を持っているだけでは評価されません。
むしろ現代においてはある程度の経済学や経営の理論などは知っているのが前提で、そこからどれだけ自分の色を出すことができるのかが勝負になってくるのです。
たとえ、経済学を専攻していようとも相当分野に精通していない限りにおいては、むしろ差別化において不利だと言えるでしょう。
ビジネスにおける文系
ビジネスにおいて文系の学生や学問というのはどういった立ち位置にいるのでしょうか?
実際のところ、文系の知識が実用化レベルにまで届くことは、ほとんどの場合残念ながらないでしょう。
特に文系の学生は大学院に進学する割合が低く、学部レベルの勉強で止まってしまいます。
このように考えると文系のビジネスにおける強みというのは「言語能力」と「多様的思考能力」のただ2点に収束することでしょう。
BtoCであれDtoCであれ、どんなビジネスにおいても伝える力というのは必要になってきます。
文系学問特有の数値ではない言葉でロジックを繋げるという特徴は、数値だけでは表現することのできないビジネスの世界でより重宝されることでしょう。
社会のトレンドを考え、それを表現し伝える能力が高いビジネスマンはきっと成功することでしょう。
また、理系と違い文系の学問には「正解」という概念が比較的少ないと考えます。
理系分野においては当然分野によって異なりますが、絶対的な真実であったり普遍的な事実というものを研究します。
そこには明確な白と黒が存在し、それを解き明かすのが理系学問の真髄だと言えます。
一方で文系の学問では、様々な「観点」を探求します。1つの考え方についてメリットデメリットを検証し、対立する考え方をぶつけ合い、昇華させるのが文系学問の面白さだと私は考えます。 時代や文化により正解や正義が変動したり、その変化を受容することができるのも自然科学との大きな違いだと言えます。
こういった柔軟な思考能力は全てを絶対的に定式化することのできない社会を相手にするビジネスにおいては活躍することでしょう。
文系が学生時代に取り組んでおくべきこと
さてでは、文系の学生が就職を考えた時に取り組んでおくべきこととはなんでしょうか?
当然、部活動やサークル活動、インターンなどに勤しみ、成果を出すことは文系、理系を問わず全ての学生に求められます。
しかし、あえて文系の学生に様々な情報を踏まえた上でアドバイスをするのであれば、真剣に専攻する学問に取り組むことです。
なんとなく「文系の学生は遊んでばかり」といったような印象が強く、確かにこれは緩やかな傾向として存在しているのかもしれません。
そんな中で、しっかりと1つの学問に向き合い、それを極めた人間は必ずどこかしらの分野で重宝されることでしょう。
就職活動において周りと差別化するという意味合いでも、自分の学問分野や研究内容については深く語れるようになっていることが必要だと言えます。
まとめ
さて今回は文系に関する就職についてまとめていきました。
ざっくりとした枠組みにおいて語ってしまったため、それぞれの専攻分野や研究内容を深くみていった際に就職先は異なっていくのかもしれません。
例えば、言語学においてコンピューターやAIの言語を研究してる人はそういった分野に就職される方も多くいることでしょう。
何より大切なのは自分の専攻分野にしっかりと向き合うことです。
たとえそれが必ずしも就職や働くということと直接的にマッチしなくとも、そこで得られた基礎的な素養や思考能力は必ず役立つはずです。
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。