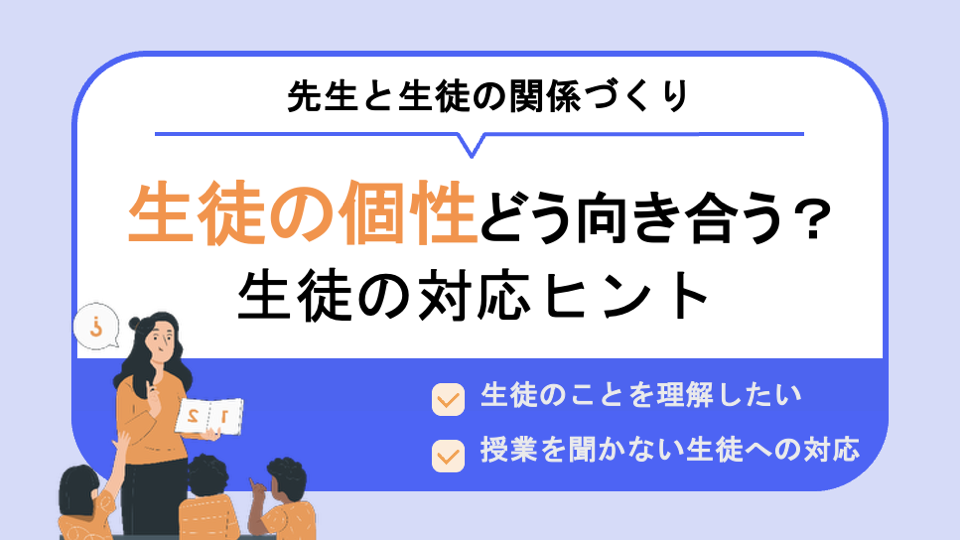生徒たちは皆、それぞれ違う背景や性格、能力を持っています。同じ教室にいても感じ方も学び方も違うのが当たり前です。だからこそ先生は、生徒一人ひとりの「個性」とどう向き合うかが問われます。本記事では、主に中高の先生に向けて、生徒の多様な特性を理解し、それに応じて信頼関係を築く方法を、現役東大生の視点から解説します。
生徒の個性を理解することの重要性
先生が生徒とより良い関係を築き、適切な指導を行うためには、まずその生徒の個性・特性・背景を理解することが不可欠です。学習が得意で積極的な生徒もいれば、静かで人前で話すのが苦手な生徒もいます。また、家庭の事情や発達特性など、本人の力だけではどうにもならない事情を抱えていることもあります。これらを知らずに全員に同じ指導をしても、うまくいかないのは当然のことです。
個性を理解することで、先生は「なぜこの生徒がこの行動をするのか?」と、行動の背景に目を向ける視点を持つことができます。そして、生徒にとって無理のないアプローチを選び、必要な支援や声かけを行えるようになります。生徒の個性を理解することは、生徒をひとりの人間として尊重することの第一歩でもあります。個性を受け入れ、一人ひとりに合った関わり方を見つけることが、学級経営や日々の教育実践の質を大きく高める鍵となるのです。
生徒との信頼関係を築くためのステップ
生徒と信頼関係を築くことは、先生として最も大切なことの一つです。良い信頼関係を築くためには年齢、性別問わず、生徒を1人の人間として尊重する姿勢が最も重要です。ここでは、実際に取り組むべきコミュニケーションや、生徒を理解する上で注目するべきポイントについて解説します。
日常的なコミュニケーションの活用
日常的なコミュニケーションの場において、生徒と接するときに心がけることを、4つのポイントに分けて紹介します。
「笑顔」で接する
自分が子どもだった頃を思い出してみてください。年齢差も体格差もある大人の人が無愛想な仏頂面をしていると、なんとはなく怖かったのではないでしょうか。良い表情、特に笑顔でいることは、生徒と仲良くなるための第一歩です。毎日、自分の表情には気を遣いましょう。
毎日笑顔でいるには、まず先生自身が幸せな状態でいることが重要です。小学校教諭の乾倫子先生は、「先生自身がまず幸せになることが大切」だと主張され、ペップトークという方法を全国に広めています。乾先生へのインタビュー記事も、ぜひお読みください。

1人1人と対話する機会をつくる
関わる生徒一人ひとりのことを、知ることができていますか?生徒全員のことを把握するのは、簡単なことではありません。おすすめなのは、生徒と関わるごとに、コミュニケーションが取れるツールを用意することです。たとえば高校教諭で社会科担当の前田圭介先生は、授業中に回収するプリントに自由記述欄を設けるようにしているそうです。「授業や勉強に関係ないことも記入して良い」と生徒に事前に伝えていて、生徒の最近の流行や悩みを知ることができます。次の授業の仕掛けの参考にもできるので、何かと役に立っているそうです。このように、回収するプリントやノートを通して生徒を知る機会をつくるのも、有効な方法の一つです。

愛情を持って接する
これは「本当に」生徒のためになることを考えて行動するということです。例えば指導の際に、感情をぶつけて怒っていませんか?生徒の将来を考え、良い方向に導くためには、感情的に「怒る」のではなく、何が悪かったかが生徒に伝わるように「叱る」ことを意識しましょう。これは褒める際も同様です。忙しい日々の中で、直接生徒を褒めること機会は意外と少ないかもしれません。生徒を一個人として尊重する姿勢は言葉や行動にあらわれます。
生徒から話しかけられたり相談を受けたりしたら、できる限り注力して話を聞くように心がけましょう。具体的な解決策を提示しなくても、ただ聞いてあげることで生徒の中で勝手に解決していく悩みや問題は意外とあります。必ずしも「アドバイスをしよう」というモードに入らず、生徒の気持ちを聞いて受け止めてあげることで、生徒との信頼関係を徐々に築いていけることもあります。
「尊敬」される行動を心がける
教師として、一人間として、尊敬される行動を心がけましょう。まず前提として、約束を守ることが大切です。これは自分の言動に責任を持つということです。たとえば生徒に普段から5分前集合するように言っているのであれば、事情がある場合を除き、5分前には集合しましょう。先生がまず生徒の模範となり、約束を果たす姿勢を見せることが重要です。
学力以外の能力(非認知能力) を見極めるポイント
学力だけは、生徒の全体像は見えません。生徒の性格や感情の動き、ストレスの受けやすさを理解することで、生徒を評価の対象ではなく、関係を築く相手として接することができるようになります。学力以外の能力で、生きる上で役立つとされているものを、「非認知能力」といいます。ここでは、生徒の非認知能力を見極めるために、どんな部分に注目すれば良いかについて解説します。
自身と向き合うための能力
目標に向かって努力を続けたり、感情や衝動をコントロールする力のことです。この力が十分にあると、目標に向かって最後まで粘り強く取り組む、イライラしても冷静に行動する、やるべきことを先にやるといったことができるようになります。この力が育つと、勉強や部活動で「継続する力」「失敗に負けない力」につながり、社会に出ても仕事などに生かせることでしょう。課題を毎回丁寧にする生徒や、自己学習を継続してできる生徒、何か一つのことに努力を続けられる生徒などは、この力が成長しているといえます。
自身を高めるための能力
自己認識・自己肯定感といった、自分を理解し受け入れる力のことを指します。自分の得意・不得意を理解しており自己肯定感の高い子は、たとえ失敗しても「自分には価値がある」と思えるため、再挑戦する意欲が生まれやすく、学習や人間関係に前向きに取り組めます。日本人は自己肯定感が低い傾向がありますが、生きていく上で非常に重要なポイントです。
他者と協力する能力
人と適切に関わる力である対人関係能力・社会性、協調性やコミュニケーション力がこれに当てはまります。学校生活だけでなく、社会に出てからも必要不可欠な能力です。この能力が十分高いことが、人と信頼関係を築く上で重要となります。友人とのコミュニケーションの取り方や、先輩後輩・先生との関わり方などに注目すると、発見できます。
生徒の性格を観察する方法
生徒の性格を観察する際は普段の行動を観察することが重要です。ここでは行動観察のポイント、そして性格特性を判断する際に役立つ分類理論を紹介します。
行動観察のポイント
まず行動観察をする際の心構えとして、「評価」ではなく、「理解」のために行うようにしましょう。また特定の場面だけでなく、複数の場面で一貫性があるかどうかに着目するようにしましょう。
観察を行う際に着目する点は、次のようなものがあります。
- 発言の頻度はどれくらいか
- 発言の内容はどのようなものか
- 授業中の集中のしかたはどうか
- 集団活動でどのような役割を果たしているか
- 誰と仲が良いか
- 同級生や先生とどのように関わっているか
- トラブルが起きた時はどのように対応しているか
性格特性の一般的な分類
ここでは性格を5つの主要因で捉える「ビッグファイブ理論」の要素表を、参考用に載せます。生徒の強みや課題を把握し、個に応じた関わりを考える際に活用してください。
外向性(Extraversion)社交的・積極的・エネルギッシュ
協調性(Agreeableness)思いやりがある・協力的・信頼されやすい
誠実性(Conscientiousness)責任感・計画性・几帳面
神経症傾向(Neuroticism)不安になりやすい・ストレスを感じやすい
開放性(Openness to Experience)想像力が豊か・好奇心旺盛・新しいことを受け入れやすい
課題のある生徒との関係づくりのヒント
学校現場には、さまざまな課題を抱えた生徒がいます。その背景には性格、家庭環境、発達特性、過去の体験など、多くの要素が関係しています。教師として関わる際に大切なのは、「問題行動」ではなく、その奥にある理由や本人の気持ちに目を向けることです。表面に現れる行動だけを見て判断せず、「なぜそうなるのか?」という視点を持ちましょう。そして、生徒を指導の対象ではなく、一個人として尊重し、信頼関係を築いていく相手として捉えることが、支援の第一歩となります。ここでは、よく見られるケースごとに、対応のヒントを紹介します。
授業を聞かない
授業を聞かない生徒に対しての指導方法としては、授業に集中できない理由を取り除くという方法があります。その1つとして現在の席順が妥当であるかを考えましょう。周りの生徒との関係性、黒板からの距離、そして換気や湿度、温度の管理がしっかりなされているかなどを観察し、必要であればテコ入れを行いましょう。
また生徒とのコミュニケーションを通し、なぜ授業が聞けないのかを探りましょう。例えば「授業が難しすぎる、もしくは簡単すぎてやる気が出ない」「家で夜更かしをしてしまうため眠気が止まらない」など原因がわかれば、対処法を考えられます。授業のレベルが合っていなかったり、「授業はつまらないもの」という固定概念を持っている場合は、授業の内容自体を更新する必要があるかもしれません。
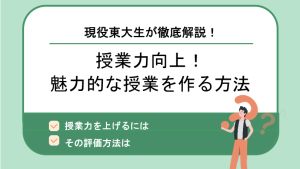
勉強の理解が遅い
勉強の理解が遅い生徒と接する際に、まず大切であることは、「理解の速さ」を問題視しないことです。間違っても大丈夫と思える雰囲気をつくることで、安心感を提供するようにしましょう。授業についていけない場合は、授業中に気にかけ、授業後に個別に指導することも有効です。学級全体で授業の理解速度にばらつきがある場合は、レベル別の少人数のクラスに分ける方法も良いでしょう。また、簡単な問題から段階的に取り組ませ、成功体験を積ませたり、最後までやり抜いた努力を褒めたりして、挑戦できる姿勢を育めるようにしましょう。
理解が早く、次に進みたがる
理解がとても早い生徒に対しては、生徒の興味関心を生かせるように関わり方を工夫しましょう。たとえば、全体に課した問題を解き終わったら、応用問題や調べ学習に取り組ませることで、知的好奇心を刺激できます。このように他の生徒と違う対応をする際は、特別扱いではなく、「挑戦の機会」を与えるというやり方で尊重するようにしましょう。また周囲とのギャップで孤立しないように、他の生徒に教える機会を与えることも重要です。これにより、他の生徒の理解も深まり、協調性も育まれるでしょう。
やる気が出ない
やる気がなかなか出ない生徒に対しては、小さな関心から始めて、やる気のきっかけを一緒に探すようにしましょう。進路・趣味・将来の夢といった目的意識へとつながる声かけが重要です。たとえば、勉強のやる気がなくても、ゲームであれば楽しんでできる生徒がいたとします。その場合でも、「勉強もゲームと同じ」「ゲームに関わる仕事もある」「ゲームを作るには数学が必要」などの情報を徐々に提供し、自然と勉強したくなるような声かけができると良いです。無気力の背景には、自己否定や不安があることも多いため、否定的な声かけは行わないようにしましょう。
人前で話すのが苦手
人前で話すのが苦手であることは、自信のなさ、失敗を極端に恐れる気持ちが原因であることが多いです。段階的に話すことに慣れさせていきましょう。まずは1対1で話し、次は少人数のグループ、そして全体へと、少しずつステップアップするようにしましょう。ここで注意すべきこととしては無理に発言させないことです。うまく話せなかった恥ずかしい体験は、逆効果となってしまいます。本人の「できた」という感情に合わせて、ゆっくりと進むサポートをしましょう。
遅刻や忘れ物が多い
遅刻や忘れ物が多い生徒は、時間管理・準備が不得意な場合があります。そこでチェックリスト、準備物カード、リマインダーなど、「どうしたら忘れ物をしないか」を一緒に考え、しくみとして導入するようにしましょう。家庭の支援が不十分な場合もあるため、必要に応じて保護者・支援担当と情報を共有し、連絡を取るようにしましょう。
家庭学習の習慣がない
家で勉強する習慣を身につけさせるためにはスモールステップで行うようにしましょう。具体的には宿題の量やレベルを一時的に調整し、「やり切れる体験」を作りましょう。また、色やシール等で、自分が勉強した軌跡の「見える化」をすると、継続的に勉強する意欲がつくことがあります。
親が無関心・過干渉
家庭でのサポートがほぼない生徒にとって、先生との関係が「居場所」になりえます。スクールカウンセラー、養護教諭、特別支援担当などの学校内支援と連携し、学校がその生徒の心の支えとなるように、サポートの環境を整えましょう。また声かけを通して、生徒の存在を尊重していることを伝えるようにしましょう。
転校生
転校生は環境が急に変わり、不安を抱えがちです。すぐに安心できる友達、頼れる先生が見つかるよう、転校直後の人間関係には特に配慮しましょう。またクラスのルールも丁寧に教えましょう。転校生を迎える学級の他の生徒に対しては、転校生とどのように接するのが望ましいか指導しておき、暖かく迎える準備をしましょう。
高学年女子
高学年女子は思春期に入り、感情が不安定になりやすいです。一歩引いた距離感で接しながらも、必要な時に頼れる存在になることを目指しましょう。たとえばトラブルが起きた時は、すぐ介入せず、集団での関係性を観察し、感情や悩みに共感する姿勢で接するようにしましょう。ただし、いじめなどの大きな事態に発展しそうな場合は、先生という立場を利用し、しっかりと介入することも必要です。
発達特性を持つ・特別学級
これらの生徒の特徴として感覚や行動、学び方に個人差が大きいということが挙げられます。そのため、まずは特性を理解することから始めましょう。こだわりやパニックなどの感情・行動には、背景となる理由があります。どうしてそうなったのかを、丁寧に振り返りましょう。また、担任・支援員・他の生徒の支えを通じて、安定感が生まれます。安心できる人との繋がりに重点を置いて、サポートするようにしましょう。
まとめ
生徒たち一人ひとりの行動には、必ず背景があります。勉強が苦手な子も、やる気を出せない子も、話したくても話せない子も、皆それぞれ理由や特性があります。教師にできることは、それを問題として切り捨てるのではなく、理解し、適切に関わっていくことです。さらに、生徒の非認知能力や性格特性に目を向けることで、学力だけでは見えない力を育てる関わりも可能になります。信頼関係は、指導の土台であり、成長のエネルギーになります。生徒ととの関係に悩んだ時、本記事が解決の一助となれば幸いです。
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。