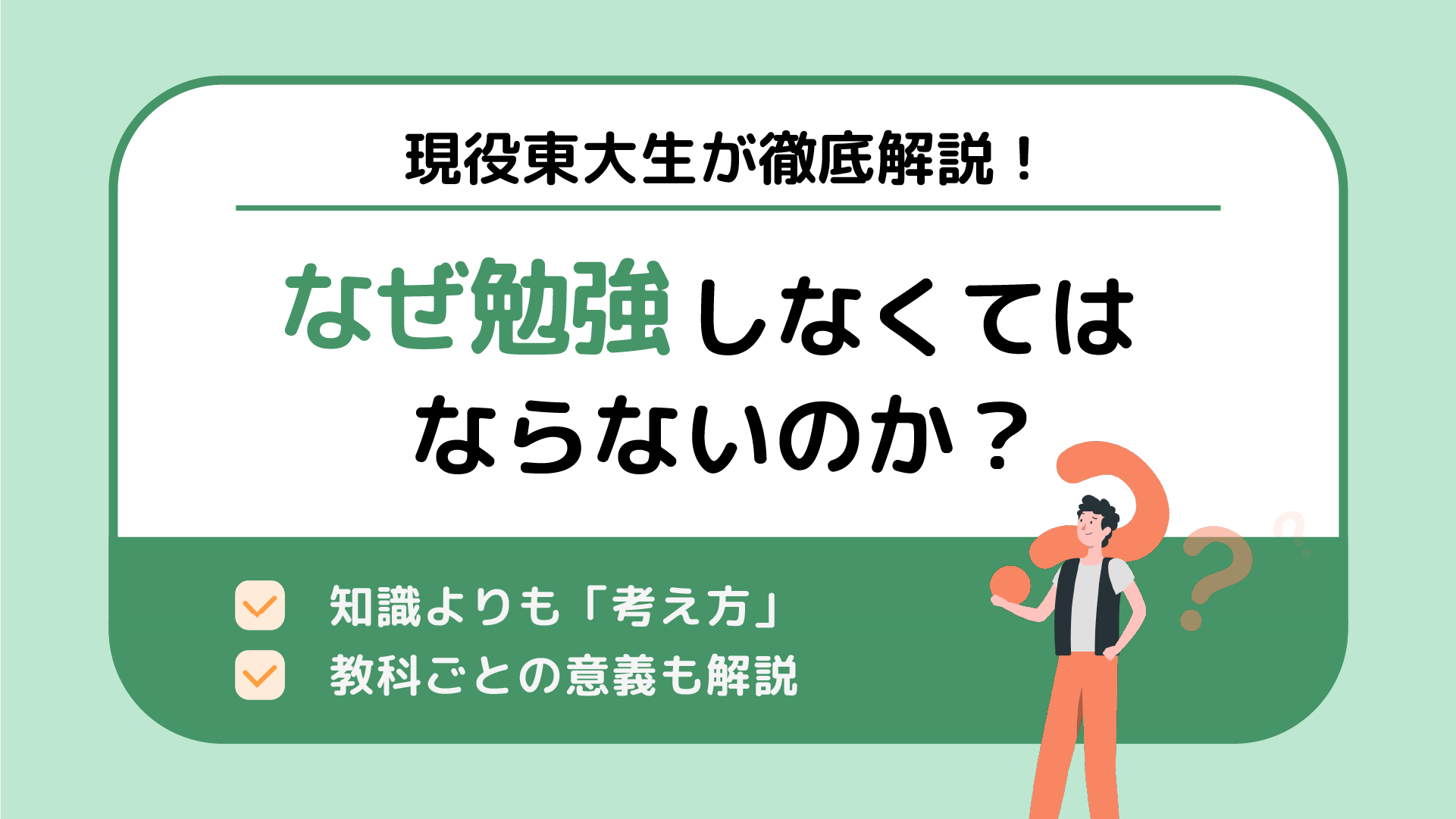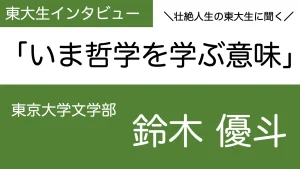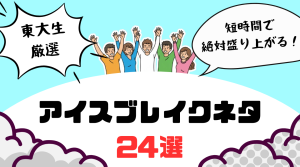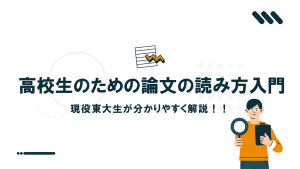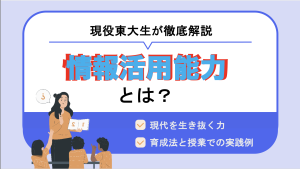以前、とある政治家が「sinやcosなんて習っても将来使わないんだから、学校はもっと役に立つことを教えるべき」という主旨の発言をSNS上でしていました。
みなさんも、課題をやっている時、授業を受けている時、ふと考えたことがあるでしょう。こんなの習っても絶対使わないじゃないか。何のためにやらされているんだろう——? 受験で使わない科目を勉強している暇があったら、将来の夢のためのスキルアップに時間を使いたい……と。
今回は、そんなみなさんの疑問にお答えすべく、現役東大生ライター碓氷明日香が、「勉強することの意義」を徹底解説します!
勉強することの意義
では、早速。勉強することの意義を4つ挙げていきます。
「知識」より「考え方」を養うため
上記の「sinやcosは社会に出てから使わない」という話に代表されている考え方は、「学校では将来使う知識を習う」というものですね。政治の仕組み、お金の回り方、メイクの仕方。これらの知識を学生のうちに手に入れておけば、社会に出た時に役に立つはずだ、という考え方です。
知識が大切なのは間違いありません。何も知らなければ、会話は成り立ちませんし、日常生活でも社会の中でも困ることは多いでしょう。
ですが、勉強の本質は知識を増やすことだけではないのです。より重要なのは「考え方」を養うこと。確かに社会に出てから三角関数を使う人は一部に限られますが、三角関数の問題を解く上で使った「論理的思考力」や「問題解決能力」は日常の至るところで誰もが使うことになる力なのです。
論理的思考力がなければ、例えば、会社のプロジェクトで失敗した時に原因を考えることができません。原因がわからなければ解決するのは不可能です。他にも、条件を整理する力がなければ、契約で損をするかもしれませんし、確率を計算できなければ、リスクとリターンを比較できず、無謀な賭けに手を出してしまうかもしれません。
つまり、「三角関数を使って計算ができるようになる」というのは目的の一つに過ぎず、より大切なのは問題を解く過程で手に入れることができる「考え方」の方なのです。もちろん、これは数学に限った話ではありません。詳しくは、「各科目を学ぶ意義」のところで説明します。
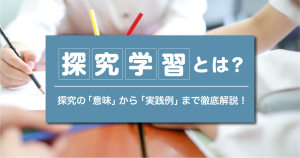
ゴールに向かって計画的に効率よく進む方法を学ぶため
日本では6-3-3-4制が取られており、小学校、中学校、高校、大学にそれぞれ一定の年数をかけて通いますね。多くの人は高校受験、大学受験をして、社会に出ることになるでしょう。これらを踏まえると、高校受験のためには中学校の3年間、大学受験のためには高校の3年間(中高一貫の場合は6年間)だけ「準備期間」が与えられていることがわかります。
受験というゴールに向かって、決められた「準備期間」をどのように過ごすか。その「計画性」によって、受験の結果は大きく左右されます。いかに効率よく複数の科目の成績を上げていくか、試験当日までに志望校のレベルにまで自分の点数を持っていくその道筋が、受験の成功のためには非常に重要です。
そして、それは社会に出てからも変わりません。「受験」のような明確なゴールは少なくなりますが、「何日までに仕事の成果をこれくらい出す」「この日の試験で資格を取る」など、細かい目標が次々にやってくるのです。優先順位をつけて、計画を立て、効率よく進めることが、学生の身分を卒業しても永遠に必要とされます。
すなわち、勉強することを通して、私たちは「ゴールに向かって計画的に効率よく進む方法」を学び、社会に出てからもそれを応用することが求められているのです。こう考えると、学生のうちにしっかり計画性を身につけておくべき、勉強するべきだ、という考えに至りませんか?
人生の選択肢を広げるため
これはよく言われることですが、幅広い教養を身につけておくことで、人生の選択肢は広がります。これも勉強することの意義の一つです。私たちは成長するにつれて、進学、就職、結婚、転職など、さまざまな選択を迫られます。そのときに、自分の可能性を広げる武器となるのが、それまでに手に入れた「知識」と「考え方」です。
最も想像しやすい例を挙げましょう。例えば、英語の勉強に真面目に取り組んでいれば、海外で働くという選択肢が視野に入ってきます。一方で、英語が嫌いだから、苦手だから、と最初から諦めて勉強を怠れば、その選択肢は取れませんね。
これが、「人生の選択肢を広げる」ということです。もっと細かい選択肢だって数えきれないほどあります。
将来の夢が明確に決まっている人にとっては、あまり魅力的に聞こえないかもしれませんが、その将来の夢を最後まで追い続けることは決まっていませんし、残酷な話ではありますが、その夢が100%かなう保証もありません。もちろん、夢を全力で追いかけることはすてきなことではありますが、万が一の時のことを考えておくことも大切です。その時のために、自分の興味のある分野だけでなく、幅広く学んでおくことが必要なのです。
人生において強いカードを手に入れるため
勉強すれば、いい大学に入ることができて、いい会社に就職できる。みなさんもよく聞くことではないかと思います。そして、このことは圧倒的に正しいです。
日本の学歴社会批判はずっと行われてきましたが、それでも、いまだに日本は学歴社会です。いい大学に進学すれば、いい会社に就職しやすいという構造は大きくは変わっていません。高学歴というカードが、その後の人生において強い効力を発揮する社会なのです。
そのために勉強する、というのは本質をつかめているとは言い難いですが、一つの考え方としては正しいでしょう。考え方を養う、計画性を身につける、選択肢を広げる、これらのどの考え方も、実際に成長して経験を積まないと簡単には納得できないかもしれません。その点、この「強いカードを手に入れるため」という目標は一番単純明快で納得しやすいものだと思います。ある意味とても現実的な「勉強の意義」なのかもしれません。
各科目を学ぶ意義
ここまでは勉強全体で意義を考えてみましたが、大雑把で想像しづらかったかもしれません。そこで、ここからは各科目に焦点を当てて、意義を見つけていきましょう。自分の苦手な科目はやる気が出にくいと思うので、特に注意して見てみてください。
国語
評論文や小説などの文章を読むことで、読解力や批判的思考力が身につきます。相手の言わんとするところをつかんだり、それを自分の言葉で再度言語化したり、世間に出回っている文章を批判的に考え、真偽を見抜いたりするための訓練です。このあたりは比較的想像しやすいのではないでしょうか。
よく聞くのは、国語の中で古文や漢文を学ぶことの意義がわからない、という声です。確かに一見役に立たないような知識ですが、これは「先人たちの知恵を学ぶ」ための勉強です。
「巨人の肩の上に立つ」という言葉があるように、私たちはこれまでを生き抜いてきた先人たちが積み重ねた知恵を利用して生きていくことができます。代を重ねるごとに、有利になるのです。ですが、その知恵を利用するためには、文献を読み、当時の社会的・文化的な背景と現代のそれを比べて、知恵を現代に適用する方法を模索する必要があります。そのために、古い文章の読み方や当時の時代背景を学ぶのです。
数学
理系の仕事に就く場合はもちろん、数学的な思考力や計算力が必須なのは自明なので、ここではあえて、そうでない人に向けた意義を解説しましょう。
高校数学では、ロジックジャンプが起こらないように丁寧に論理を積み上げ、それを採点官に伝わるように言語化することを求められますよね。これがまさに、数学の勉強を通して私たちが学ぶべきことです。
上述の通り、論理的思考力は日常生活・社会生活の至るところで使うことができます。自分が損をしないため、失敗しないため、より良い生活を送るため、そして社会に貢献するため、全てにおいて論理的思考が欠かせないのです。
また、「採点官に伝わるように言語化」する力も、社会生活で活きてきます。順を追って丁寧に正しく説明することができなければ、伝えたいことが相手に伝わらず、意思疎通が図れません。人間が会話をせずに生きていくことは不可能なので、このロジックの説明力は必ず役に立ちます。
英語
英語を学ぶ意義は主に2つあります。これはどちらも聞いたことがあることかもしれません。まず1つ目は、「国際コミュニケーションを可能にする」ことです。英語は世界で最も広く使われている国際共通語であり、旅行やビジネス、学術の場など、さまざまな場面で必要とされます。仮に英語を話せるところまで辿り着かなくても、読解ができれば、英語で書かれた論文は読むことができますね。そうすれば、先人たちの知恵をより多く知識として身につけることができるはずです。それだけでも、十分すぎるほどに意味があります。
2つ目は、「異文化を理解し、自国について詳しくなる」ことです。英語を学び、言語の成り立ちを理解したり、英語の文献を読んだりすることで、他国の価値観や文化を知ることができるでしょう。それだけでも価値のあることですが、他国について理解を深めることが、日本に対する理解をさらに深めることにもつながるのです。他国の文化を新しく知れば、その時必ずと言っていいほど、私たちは「日本ではこうだな」と国際比較をするでしょう。それによって日本的な価値観の新たな側面に気づくことができるのです。
理科
理科という教科を通して学ぶべきことは「問いを見つけ、仮説を立てて、検証する」という科学的思考の流れです。自然や身近なものに対して、これはどうなっているのだろう?という問いを積極的に生み出し、すでに明らかになっている法則や自分の経験を踏まえて、きっとそれはこうだからだ、と仮説を立てる。そして実際に実験してみる。なぜその結果になったのか、考察する。この流れが、真理の探究においては非常に重要です。この姿勢を学ぶために理科の勉強をしています。
また、高校理科は、物理・化学・生物・地学の4科目に分かれていますが、そのそれぞれにも意義があります。例えば、物理の力学を知らなければ、家具を動かす時に効率が悪くなってしまいますし、化学の酸性・塩基性を知らなければ、洗剤を混ぜたらどうなるかわからず、大事故につながってしまうかもしれません。人体を知らなければどんな栄養を摂ればいいかわからないし、生態系への理解がなければ、希少な生物が絶滅してしまうかもしれない。これらは生物という科目で学べることです。そして、災害大国日本において、その原因がわからなければ、私たちは自然に翻弄されるだけで何もできませんし、天気を予想できなければ、少し先の予定を立てるのにも影響します。これらは地学で学べることですね。
このように、どの科目にも、日常で役に立つ知識・考え方が含まれているのです。問題を解いている時、実際にどのような場面に利用できるか考えたり、調べたりしてみると、モチベーションにつながるかもしれませんね。
社会
社会は日常に直結していて想像しやすいでしょう。地理を学べば、天気や災害、農産物の産地、エネルギー資源の分布など、自然現象や社会の仕組みが理解でき、日常生活を豊かにすることができます。歴史を学べば、社会の流れや背景を理解でき、それは戦争や経済格差など現状ある問題を考えるヒントになります。公共を学べば、今まさに政治・経済はどのように回っているのかを知り、自分はそれに対してどのような立場を取るのか決めることができるでしょう。
こうして、現代を生き抜くための知識と考え方を身につけることができるのが、社会の勉強です。
情報
高度情報社会の中で、情報に翻弄されず、自ら情報を使いこなすためには、情報リテラシーが欠かせません。現代社会を生き抜く術として、新課程で新しく取り入れられた科目ですが、これから間違いなく必要な力です。
情報の授業で学んだことは、仕事に直結します。情報収集の仕方、情報の真偽を見抜く力、pcを使いこなす技術……。少し想像してみれば、情報を勉強する意義は簡単に見えてくるはずです。
まとめ
現役東大生が考える、勉強することの意義、そして各教科の存在意義を解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
意義を考えることは大切ですし、モチベーションにもつながります。ですが、意義がわからないことを「こんなの勉強したって将来使わないんだし、意味ないじゃん」と勉強しないことの言い訳に使っていませんか?どの科目も意義があってカリキュラムができているのですから、言い訳せずに、やるべきことをきちんとやりましょう。
この記事が、勉強の目的を見つけるきっかけになれば幸いです。
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。