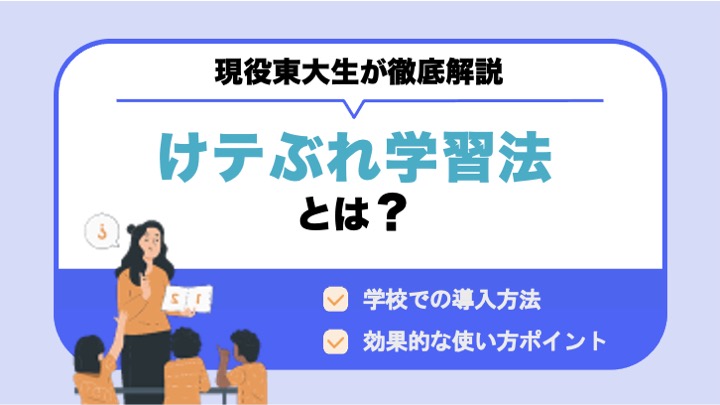子どもたちを自立的な学習者へと成長させる「けテぶれ学習法」。近年、教育界で少しずつ広がりつつあるこの学習方法は、一体どのようなものなのでしょうか。
今回はこの「けテぶれ学習法」について、導入方法やメリット・デメリット、効果的に使うポイントなどを、東大教育学部生の碓氷明日香が徹底解説します!
けテぶれ学習法とは
そもそも「けテぶれ学習法」とはどんな学習方法なのでしょうか?
この節ではその名前の由来からはじめ、その目的について説明していきます。
「けテぶれ」の意味
「けテぶれ学習法」とは、「け=計画」「テ=テスト」「ぶ=分析」「れ=練習」の4つのステップで学習を進める方法です。
最初に目標を立て、その目標を達成するための勉強計画を作成し、それに沿って学習を進めます。次に小テストや確認問題に取り組み、間違えたところやつまずいたところを分析。最後に分析をもとに足りないところを重点的に練習します。このサイクルを繰り返すのが、「けテぶれ学習法」なのです。
こうしてゴールに向かって自分で道筋を立て、結果を受けて軌道修正していくことで、これまでの「やらされる勉強」ではなかなか身につかなかった、「学んだ知識を確実に定着させ、自分で学びを改善していく力」を育てることができます。
PDCAサイクルとの違い
「けテぶれ学習法」は、企業でよく用いられる「PDCAサイクル」に似ています。PDCAサイクルとは、Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)を繰り返して業務の質や効率を継続的に改善していくフレームワークです。
中身は非常によく似ていますが、名前のつけ方に特徴があります。
英単語の頭文字からなる「PDCA」とは異なり、「けテぶれ」は英語学習が始まっていない小学校低学年の児童でも親しみやすいように、簡単な日本語で構成されているのです。教育現場で使いやすいように工夫されているということですね。
けテぶれ学習法導入のメリット
では、「けテぶれ学習法」を用いるとどのようなメリットがあるのでしょうか。
この節では「けテぶれ学習法」の4つの利点を紹介していきます。
利点①自立につながる
けテぶれ学習法では、生徒自身が「次に何をするべきか」を意識しながら学習を進めます。
自分には何が足りないのか、目標を達成するためにはどうすればいいのか、自分の学習を自分で管理できるようになるのです。
こうした習慣は、学力の向上だけでなく、将来役に立つ自己管理能力の育成に直結します。
直近の未来ですら予測が困難な変動の時代を生きていく今の生徒たちにとって、この力は必須でしょう。そのため、普段の学習から自立を促すことができるのは、大きなメリットと言えます。
利点②自信につながる
勉強ができない、苦手だと感じて自信をなくし、「自分はダメな子だ」と思ってしまう生徒がよくいます。
そんな中、このけテぶれ学習法を授業や課題に積極的に取り入れることで、テストでできないことが見つかっても、それを自分の弱点と捉えるのではなく、「これは伸び代なんだ」と前向きに考えることができるようになるのです。
課題を見つけ、それを練習して克服する体験を積み重ねることで、生徒は着実にできることを増やしていけます。
こうした成功体験が生徒の自信を生み出し、次の挑戦へとつながるのです。
利点③勉強の楽しさに気づく
けテぶれ学習法では、不足している部分を重点的に学ぶため、比較的効率よく成果が出ます。できなかったことができるようになったという体験は大きな達成感をもたらし、勉強の楽しさに気づくきっかけとなるでしょう。
一度楽しさを知ってしまえば、生徒は自主的に勉強するようになります。
すると、さらに成績が目に見えて上昇し、また達成感を味わい、やる気が出る……というポジティブな循環に入ることができるのです。
利点④個別最適な学習につながる
従来の画一的な指導では、その教科や単元の得意不得意に関係なく、みな同じ問題を解くため、学習効果に偏りが出てしまいがちです。
そこで、このけテぶれ学習法を導入すれば、生徒一人ひとりの得意不得意、学習進度に合わせて最適な学習を自然に実現できます。これは、文部科学省が近年掲げている「個別最適な学習」につながり、公教育の方針とも親和性が高い方法と言えるでしょう。
学校での導入の方法
実際に「けテぶれ学習法」を学校で導入するには、どうすればよいのでしょうか。
この節では、「けテぶれ学習法」を課題に取り入れる方法と授業の中で取り入れる方法を提案します。
課題に取り入れる
「けテぶれ学習法」は、日々の課題に継続的に組み込むことで効果を発揮します。
これまでのように、先生が一律に同じ課題を課す形式ではなく、生徒自身が自分の目標を設定し、その達成に必要な課題を自分で決めて取り組む形式にするのです。
「このチャプターの新出英単語を使った例文を作る」「二次関数の応用問題を自力で解けるようにする」など、生徒が自ら学習の方向性を決めることで、課題は「やらされるもの」から「自主的にやるもの」へと変わります。
これを継続すれば、現状を分析し、適切な道筋を立てる力が身につくでしょう。
授業に取り入れる
授業の中に「けテぶれ学習法」を取り入れることも可能です。
例えば、新しい単元の授業を一通り終えたあと、グループごとに「どの内容を中心に復習・演習するか」を話し合い、計画を立ててそれぞれ学習する時間を取ります。そのあとテストで理解度を確認し、計画を改善して再度取り組むというサイクルを実践する、という方法が挙げられます。
課題は個人ベースで進める場合がほとんどなので、授業内で取り入れるときはグループ学習を意識すると、自立的に学ぶ力と協働的に学ぶ力の両方を並行して育むことができるでしょう。
けテぶれ学習法の導入における課題と解決策
メリットがたくさんある「けテぶれ学習法」ですが、従来のやり方から変えるとき、うまくついて来られない生徒が出てきてしまう危険性もあります。
この節では、「けテぶれ学習法」導入時に起こりうる課題とその解決策について解説します。
面倒くさがる生徒が出てくる
これまで与えられた課題をこなすだけでよかったのに、「けテぶれ学習法」では自分で考えて行動しなければならなくなります。その結果、面倒だと感じて反発する生徒が出てくる事例もあるようです。
そんなときは、「けテぶれ学習法」のサイクルの大切さや目的を根気強く伝えることが大切です。自分で考えることが、この先の人生でどんなふうに活きてくるのか、先生自身の言葉で説明してあげてください。
さらに、最初のうちは先生が一緒に計画を立てるなど、伴走する姿勢を見せると効果的です。ただし、計画を提示するのではなく、あくまでヒントを出して、本人のやる気を引き出すことを意識しましょう。
やるべきことがわからず学習が止まる生徒も
いざ自分で決めるとなると、何をすればよいのかわからず、手が止まってしまうこともあるかもしれません。結局何もやらないまま時間だけが過ぎていく……なんていうことは避けたいですよね。
そんなときは、「けテぶれ学習法」をうまく活用できている生徒の計画表を共有するとよいでしょう。教室に貼り出したり、ICTツールを活用して紹介したりすれば、他の生徒がそれを参考にしながら計画を立てることができます。
ただし、同じ生徒のものばかりを取り上げると、特定の子を贔屓していると思われる可能性があるため、さまざまな事例を挙げることが重要です。
多様な参考例があった方が、生徒も自分に合った学習スタイルを見つけやすくなります。
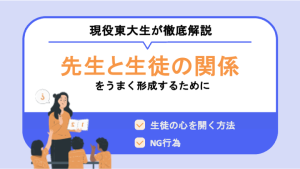
けテぶれ学習法を効果的に使うポイント
「けテぶれ学習法」を導入する際、どのような点に気をつければ、より効果を発揮できるのでしょうか。
この節では、「けテぶれ学習法」の効果を高める3つのポイントを紹介します。
ポイント①ゴールと道のりを明確にする
「けテぶれ学習法」を成功させるためには、生徒一人ひとりが自分の現状を正しく把握し、それぞれに見合った学習のゴールを掲げることが重要です。
そしてさらに、ゴールから逆算して「何を」「どれくらいの量」取り組めば達成できるのかを考え、その道筋を記録に残してから勉強に入ることも大事になってきます。
そのため、計画表のフォーマットを工夫し、「ゴール」「やること」「進捗」を分けて具体的に記入できるようにしておくと効果的です。
ポイント②ICTを活用する
計画とその実行内容の記録は、「けテぶれ学習法」において必須です。
紙に書くだけでは、紛失したり記録が散逸したりするリスクがあります。そこで、ICTを活用して、データとして学習の足跡を残すのがおすすめです。
タブレットやクラウドを使えば、生徒自身も進捗を振り返りやすく、先生も生徒一人ひとりの学習状況を把握しやすくなります。
ポイント③生徒同士で評価し合う
生徒同士の相互評価を取り入れるのも、有効な手段のひとつです。
計画やテストの分析を互いに見せ合い、点数をつけるのではなく「よかった点」や「改善点」をフィードバックし合うのです。
こうした交流によって、学習への新たな視点を得ることができ、さらには学び合いの文化も育ちます。
そして最後に生徒が自分の学習を再度見直して自己評価につなげれば、さらなるステップアップも可能です。
まとめ
「けテぶれ学習法」について、内容や導入方法、メリット・デメリットなどを解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
この学習法は、「計画→テスト→分析→練習」というシンプルな流れを繰り返すことで、生徒が自分の学習を主体的に進められるようにする方法です。
これからの時代を生き抜く術を身につけさせる教育のキーとなるシステムと言えるでしょう。
導入には課題もありますが、先生の伴走や生徒同士の学び合いを工夫することで乗り越えられるはずです。
ぜひ、日々の教育実践に取り入れ、生徒が自ら主体的に学び、成長する力を身につけられる環境づくりを進めていきましょう。


公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。