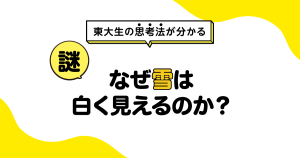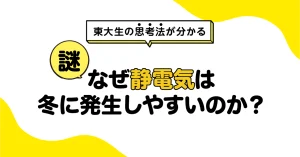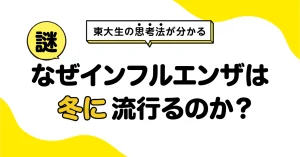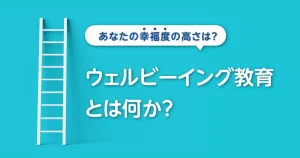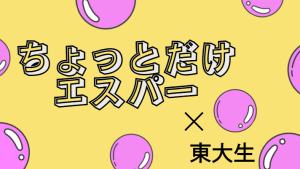現在、大阪・夢洲では大阪・関西万博が開催されています。今回は東大生が実際に万博に行って感じたことや、予約の裏技などを紹介します。(2025年8月8日 更新)
31個のパビリオンを回った方法
この記事のタイトルの通り、私は大阪万博で一日に39個のパビリオン、約100の国家をみることに成功しました。一般には10カ国くらい回れたら良いとされていますので、かなり良い成績であると自負しています。ここでは、この方法について紹介します。なお予約の方法等の詳細などは後半で紹介しているのでぜひご覧ください。
事前に準備
万博会場内はインターネットが通じにくい場合があるので、会場マップを印刷して持っていくことがおすすめです。また予約が不要なパビリオンの一覧なども公開されているので、それらも確認しながらどのパビリオンを回るのかをある程度決めておくのが良いでしょう。
あまりメジャーではない国を訪問
日本の企業が出しているパビリオンなどは予約必須のものも多いですが、各国のパビリオンはほとんどが予約なしで入れます。並ぶ場合も比較的スムーズですし、入り口で立っているスタッフに聞けばどれくらいの待ち時間があるのか教えてくれます。
またG20に加盟する国など、日本において知名度が高い国のパビリオンは総じて混雑しています。一方でそれ以外の国については比較的空いていることが多いようです。特にタイプXと呼ばれる方式で建設されたパビリオン(外装がシンプルなもの)は並ばずに入ることのできる場所も多いので狙い目です。私はこのタイプXのパビリオンをかなり多く回りました。
あと、流れの良いパビリオン(スペインやサウジアラビア)なども時間に対する満足度が高いです。
コモンズ館を訪問
自国でパビリオンを作ることが難しい国のために、様々な国が入る「コモンズ館」と呼ばれる施設があります。コモンズ館は面積がかなり広く、小国が多いこともあり比較的スムーズに入場することができます。コモンズ館一つで10カ国以上見ることも可能なので、かなりコスパが良いのではと思います。
東大生が万博を見た感想とおすすめパビリオン
コモンズ館
私が訪問した中で特に印象的だったのが、上でも紹介したコモンズ館です。アフリカの内陸の国々や、太平洋の島国など、発展途上国が多く紹介されています。
展示
各国が自国の楽器やアクセサリー、工芸品などを持ち込んで、自国の文化を紹介したり、その国の課題について紹介したりしています。そのような展示を見ていると、戦乱や食糧不足、識字率の低さや教育機会の不足など、現代の日本ではあまり見ることのできない課題を多く発見することができます。日本がいかに恵まれているのか、他国がどのようなことを必要としているのかを、実感することができるのです。また日本が現在抱える問題を思い返せば、見ている国が将来どのような課題を抱えるのか、そのために我々はどうあるべきなのかなどを考えさせられます。例えば人口が増加して困っている国と、人口がもうすぐ減りそうで困っている日本、といった見方です。
人間
現地から民族楽器を持ってきている国もあり、現地の方が非常に元気よくパフォーマンスをされていたのが印象的でした。しかし午後にもう一度訪れてみると、ぐったりと疲れて「話かけるな」モードに変わっていました。そういう場面をみるのも文化の違いを感じられて面白いです。また海外に行ったらよく見かける路上商人みたいな人たちもコモンズ館内で出店しており、値切り交渉や押し売りなどが行われています。旅行したような気分になれるのが面白いですよね。ただ、手首を出すと謎のブレスレットを勝手につけてきたりするので気をつけてください。
またパビリオンをほとんど見ることなく、ひたすら万博スタンプラリーに没頭している日本人を見るのもなんとも感慨深いです。パビリオン内にあるスタンプラリーの列は常に混んでいます。
比較する楽しみ方
コモンズ館は多くの国が入っており、かつ地理的に近い国がパビリオン内でも近くに設置されています。「このあたりの地域は打楽器が人気なのか」とか「またこの宗教の文化が出てきた」みたいな感じで、俯瞰してみるとさらに理解が深まります。また「この国はこういうことを隠したいのだろうな」といったことに気づくこともあります。
ウクライナのパビリオン
ウクライナのパビリオンは上記のコモンズ館の中にありますが、特に印象的だったので紹介します。ウクライナのパビリオンは、入場者が専用の機械でバーコードを読み取って映像を見るという形式になっています。ご存知の通りウクライナはロシア連邦との交戦状態にあるため、万博の展示もほとんどが紛争に関する内容です。しかし、必ずしも軍事的な内容や戦争の状況のみならず、「紛争下でどのように教育を維持継続しているのか」など、言われてみないと考えもしなかった、戦時下での日常などが紹介されています。メディア報道で扱われないようなことに気づくことができ、ハッとしました。
スペインのパビリオン
スペインパビリオンは入り口が大きな階段になっており、すごく迫力があります。また入り口のモニターも「情熱の国」という感じがあり、テンションが上がります。この情熱や元気さに関する展示もあるのですが、メインで展示されているのが「海」や「水」に関する内容です。スペインは歴史上、船を使って世界史に大きな影響を与えてきました。アメリカ大陸を発見したりといった大航海時代の歴史なども紹介されていました。さらに現在も海に面する国であるからこそ、洋上発電に関する紹介や生き物に関する紹介、さらには海藻などを用いた薬の開発など、先端技術に関する紹介もありました。海を通して過去から現在までの流れを感じられる、面白いパビリオンです。また現在の最新技術も知ることができるので、学びにもなります。
大阪ヘルスケアパビリオン
大阪ヘルスケアパビリオンは大阪府が出すパビリオンで、大阪府内の多くの企業が参加しています。筆者は関西出身ですが、私の周りにもこのヘルスケアパビリオンに関わっている人や、勤めている会社が関わっている人など、よく耳にします。私自身も少し関わっているのですが、情報管理の都合上、割愛させていただきます。
ヘルスケアパビリオンの目玉と言われるのが「リボーン体験」です。体に関するデータを測定した上で、25年後の自分のアバターに会うことができるという内容ですが、予約の競争率が高く、私はまだ行けていません。
一方ヘルスケアパビリオンは予約なしで入れるエリアがあり、そこでは培養したヒトiPS細胞の実物をみることができたり、最新版の人間洗濯機の実演を見れたりします。iPS細胞についてはこれまでの研究の過程や活用方法、将来の展望などが紹介されており、非常に興味深いです。また人間洗濯機は予約をすると実際に体験することもできるそうです。
他にも、大阪各地の中小企業の商品などが週替わりで展示されており、ココナッツから作った航空機燃料や、金物屋が作ったポン酢など、大阪らしく中小企業らしいエネルギーを感じることができます。
大阪万博について
2025年日本国際博覧会、通称「大阪・関西万博」は、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、2025年4月13日から10月13日までの184日間、大阪市の夢洲(ゆめしま)で開催されています。
「未来社会の実験場」として、健康・医療、都市開発、環境・エネルギーなどの分野で最先端技術やアイデアが集結し、人類共通の課題解決に向けた取り組みが世界中から発信されます。多様な文化交流を通じ、持続可能な開発目標(SDGs)達成への貢献や、未来への希望を共有することを目指しています。
万博のチケットについて
販売されるチケットには以下の種類があります