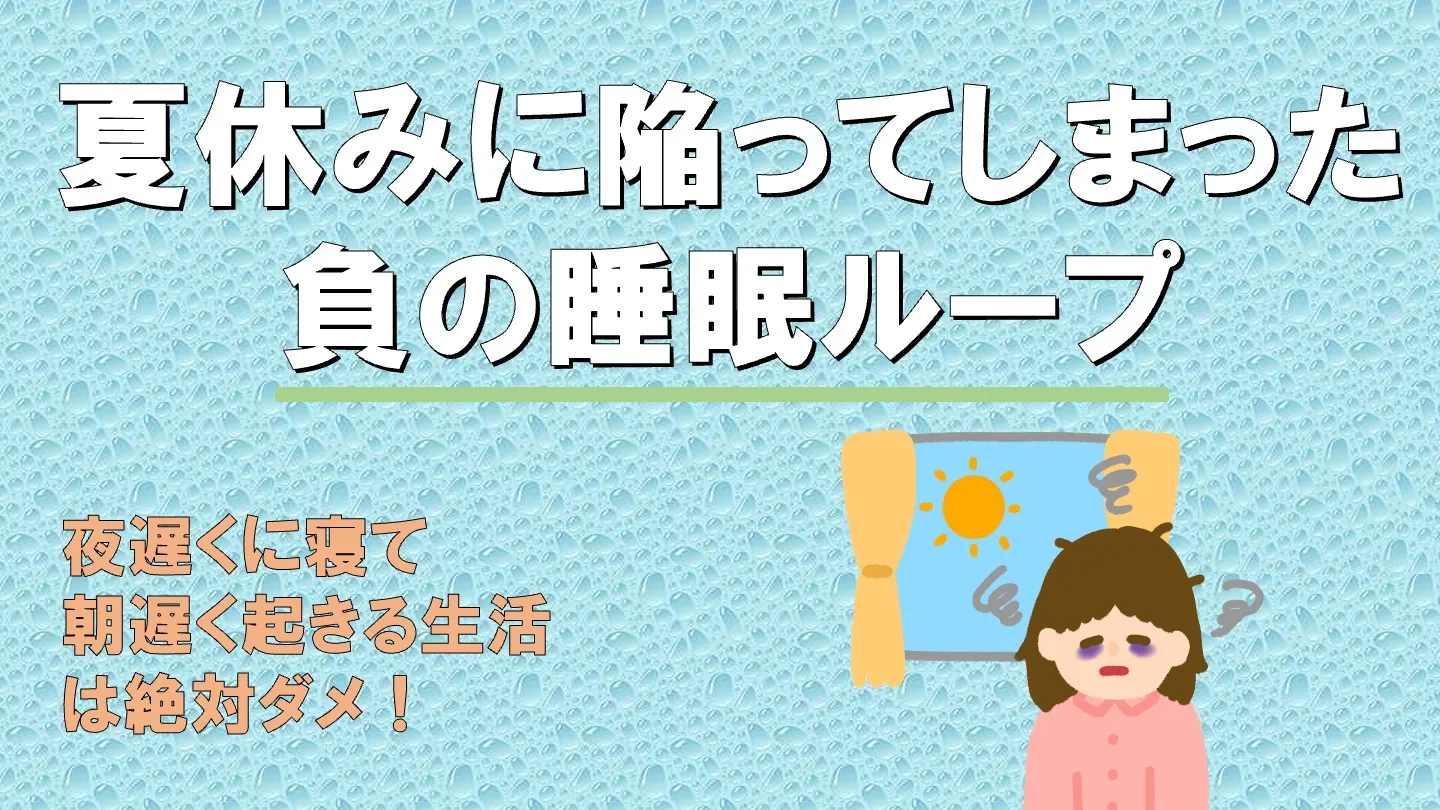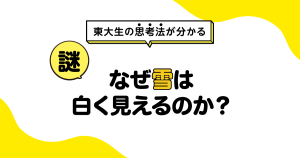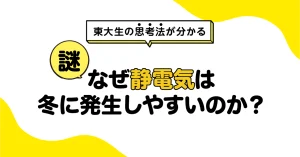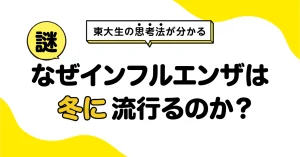長期休暇である夏休み。このまとまった時間をうまく活用できれば、他の人と大きく差をつけることができます。みなさんそれぞれの勉強方法やスケジュールがあると思いますが、どのようなスタイルであっても生活リズムを崩さないことが最も重要です。
この記事では、私が受験期に「夜遅くに寝て、朝遅くに起きる生活」をしていた結果、勉強が思うように進まなくなってしまった経験と、そこからどう抜け出したかというエピソードを通じて、生活リズムの整え方や立て直しのポイントを解説します。
夏休みの過ごし方を考える際の参考になれば幸いです。

「夜遅くに寝て、朝遅くに起きる生活」をした結果…
当時の私は、夏休みを利用してしっかり勉強しようと決意していました。朝が苦手だった私は、「夜のほうが集中できる」と考えて、深夜2時に寝て午前10時に起きる生活を試してみたのです。
しかし、結果は思うようにいきませんでした。勉強時間を確保することを優先した結果、だんだんと就寝時間が遅くなり、ひどいときには午前11時や正午に起きることもありました。
体内時計が乱れたことで、頭痛やだるさを感じたり、「もう半日が終わってしまった」という罪悪感に襲われたりし、勉強に集中できなくなってしまいました。
このような状態になった原因は、明確なスケジュールを立てていなかったことにあります。
生活リズムの崩れがもたらす影響
学校がある期間中は、1限の時間に合わせて自然と起床・就寝のリズムが整いますが、夏休みは意識してスケジュールを立てなければ、あっという間に乱れてしまいます。
特に注意したいのが自律神経の乱れです。自律神経とは、呼吸や体温調整、消化などの無意識の身体活動を司る神経系で、これが乱れると集中力低下や慢性的な倦怠感が現れます。
この状態は、毎日同じ時間に食事をとる、三食しっかり食べる、湯船に浸かるなどの規則的な生活習慣によって改善することができます。したがって、勉強のスケジュールだけでなく、生活そのものの時間割を意識的に組むことが大切です。

流石に7時起きに変更!
このままではまずいと思い、私は思い切って生活習慣を見直すことにしました。目標は、夜12時就寝・朝7時起床のリズムです。
ただ、自力で習慣を変えるのは簡単ではありません。そこで私は、友人に協力してもらい朝に一緒に勉強する時間を作ったり、塾の夏期講習の時間を朝に変更したりして、強制的に朝型に切り替える工夫をしました。
また、8時間睡眠を7時間に短縮するかわりに、昼食後に15分程度の昼寝を取り入れ、体調を整えました。こうした工夫のおかげで生活リズムを取り戻すことができ、勉強にも集中できるようになりました。
生活習慣の改善は、自分一人でやろうとせず、人の助けを借りることも重要です。そして、一度に全てを変えようとせず、少しずつ変化させていく「スモールステップ方式」で取り組むことが成功の鍵です。
まとめ:夏休みだからこそ「生活リズム」を整えよう
夏休みは、自由に使える時間が多いぶん、生活習慣が乱れがちになります。私自身、夜型の生活に切り替えたことで一時的に勉強時間を増やせたと思ったものの、体調を崩し集中力も落ちてしまいました。その経験を通じて、「夜に寝て朝に起きる」という当たり前の生活リズムの大切さを痛感しました。
朝から活動できる習慣を身につけることは、自律神経を整え、心身の調子を保つうえでもとても重要です。そして、それを実現するためには、無理のないスケジュール作成と、周囲の人の力を借りる工夫が有効でした。
これから夏休みに入る皆さんには、受験勉強を頑張るのと同じくらい、自分の生活リズムを整えることにも意識を向けてほしいと思います。規則正しい生活が、勉強への集中力や効率を大きく高めてくれますよ。
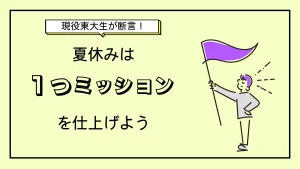
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。