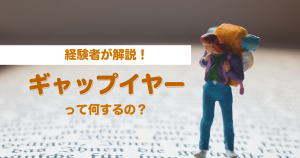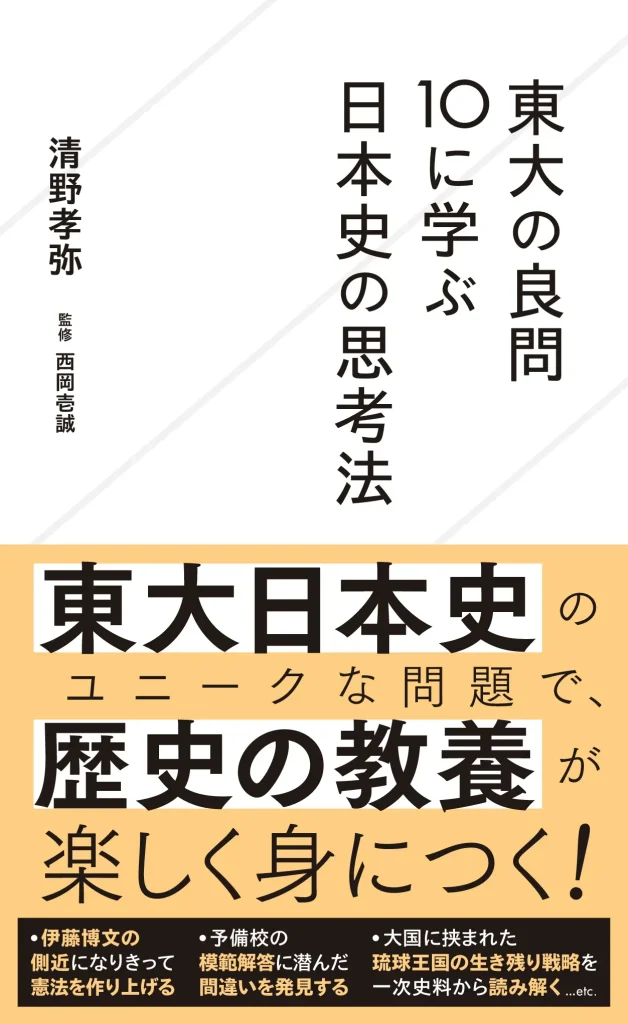日本では小学校から英語教育が行われ、学習時間も決して短くありません。それにもかかわらず、「英語が話せない」という課題は長年解消されないままです。
なぜ日本の英語教育では、これだけの時間と労力をかけても、英語でコミュニケーションを取れる力が育ちにくいのでしょうか。
この記事では、現役東大教育学部生の碓氷明日香が、指導法や学習姿勢といった表面的な問題にとどまらず、日本の英語教育が変わらない背景にある構造的な壁を、海外との比較も交えながら整理します。
日本の英語教育が抱えてきた永遠の課題とは?
日本の英語教育は長年改善が繰り返されてきました。つい最近も、学習指導要領が変わり、小学3年生から英語の授業が行われるようになっています。
しかし、どれだけ教材や授業時間が増えても、英語が話せる人があまり増えていないのが現状です。
データで見てもそれは明らかです。2025年版の「EF英語能力指数(EF EPI)」で日本は123か国・地域中96位。
つまり、日本の英語運用能力は、いまだ相対的に非常に低い位置にあるのです。
英語は単なる試験科目ではなく、他者と意思疎通し、情報を受け取り、自分の考えを伝えるための道具です。その本質を忘れ、話せるようにならない現状の教育を続けるのは、英語学習の意義を十分に果たしているとは言えません。

なぜ日本の英語教育では話せるようにならないのか
では、なぜ日本の英語教育では、英語が話せるようにならないのでしょうか。ここでは、特徴を踏まえた英語教育の問題点を4つに分けて説明します。
受験対策が重視されすぎている
日本の英語教育では、入試や定期テストで点数を取ることが最優先とされ、その結果、学習の中心が「読解」に偏ってきました。
単語や文法を正確に理解する力は非常に細かく鍛えられる一方で、それらを瞬時に組み合わせて使うスピーキング練習はほとんど行われていません。知識としては身についていても、それを実際のコミュニケーションで運用する訓練が圧倒的に不足しているのが現状です。
さらに、日本の英語教育では「和訳」を通じて英文を理解する姿勢が強く求められます。しかし、日本語と英語は語順が大きく異なるため、和訳を前提とすると、どうしても文末からさかのぼって読む癖がついてしまうのです。
本来、言語は前から順に意味をとらえていくものです。きれいな日本語に訳すことをゴールにしていては、その感覚は身につきません。
理解の正確さを追い求める受験英語の延長線上では、英語を話せるようにならないのです。
英語を使う機会が極端に少ない
日本の英語の授業では、英語を使って「何かを伝える」場面が十分に用意されていません。
最近ではそのような場面も増えてきてはいるようですが、授業の中心は依然として、教師の説明を聞き、教科書を読み、問題を解く詰め込み型の学習です。
発話の機会があったとしても、原稿を準備する余裕があったり、例文の音読や決まったやり取りにとどまっていたり、自分の考えをその場で英語に組み立て伝える経験は限られているのです。
加えて、日本社会では日常生活のほとんどが日本語で完結しており、英語を使わなければならない場面は基本的にありません。進学や就職においても、英語は「できれば評価されるが、できなくても困らない」技能として扱われがちです。
だからこそ、本来は学校が意図的に英語を使う環境をつくる必要がありますが、その役割を十分に果たせていないのが現状です。
間違いを許容する学習環境がない
上述の通り、テストで正解することが強く求められる日本の英語教育では、間違いは「避けるべき失敗」として扱われがちです。その結果、学校現場には、試しに発言してみたり、不完全な英語を口にしたりすることが歓迎されにくい空気が生まれています。
言語学習において本来不可欠な「間違いながら修正する」というプロセスが、軽視されているのです。
こうした環境で育った子どもたちは、次第に間違いを避ける行動を取るようになります。笑われる、注意されるといった経験が積み重なることで、「間違えるくらいなら話さないほうがいい」という意識が根づいてしまうのです。
実際、教師が近づいてきただけで自分の解答をすべて決してしまう生徒もいると言われています。
話すためには、不完全な表現を口に出す勇気が必要ですが、その勇気を育てる土壌が整っていないのです。
本質的な学習の時間が不足している
一般に、言語を実用レベルで習得するには1000〜3000時間程度の学習が必要だと言われています。
どれほど効率的な学習法を用いたとしても、一定量の時間をかけて繰り返し触れ、使う経験を積まなければ、言語は身につきません。この前提に立てば、英語学習は本質的に「長期戦」であり、短期間で成果を求めるものではないことが分かります。
一方、学習指導要領の改訂により、高校卒業までに合計約1000時間前後の英語の授業が設けられるようになりました。
しかし、その多くは前述の通り、読解や文法理解を中心とした学習であり、英語を実際に使う経験は限られています。
前から順番に意味を捉え、話し、伝える訓練が十分でないまま時間だけが消費されているため、結果として1000時間という限られた枠の中では英語運用能力に到達しにくいのが現実です。
せっかくの学習時間が本質から外れた形で使われてきたことが、英語が身につかない大きな要因と言えるでしょう。
海外の英語教育に学ぶ——日本との決定的な違い
さて、ここまで日本の英語教育の限界を見てきましたが、バイリンガルが多い海外では、どのような英語教育が行われているのでしょうか。以下では、オランダ、フィンランド、韓国、そして中国の4カ国の英語教育を詳しく見ていきます。
バイリンガルが多いオランダ
オランダでは、義務教育が始まる4〜5歳の段階から英語教育が行われ、早い時期から英語に触れる環境が整えられています。
また、国が細かい学習指導要領を定めていないため、指導方法や教材は各学校に委ねられているのも大きな特徴です。その結果、生徒の興味を引く内容や実践的な活動が取り入れられやすくなっています。
こうした教育環境を背景に、オランダでは英語を自在に使える人が非常に多く、15歳以上の国民の約94%がバイリンガルとなっています。
実際、2025年版のEF英語能力指数でもオランダが世界1位を維持しており、その英語運用能力の高さは国際的にも際立っています。
テストが重視されていないフィンランド
フィンランドでは英語教育は小学3年生から始まりますが、学習はテスト中心ではありません。そもそも入学試験が存在せず、学ぶことは他人と比べるためではなく「自分のため」という考え方が社会に根づいています。
そのため、間違いを過度に恐れることなく、主体的に学習に取り組める環境が整っているのです。
一方で、教える側には高い専門性が求められます。
そもそもフィンランドで教師になるためには、修士号を取得し、厳しい選抜を経て資格を得なければなりません。そのため、生徒は質の高い指導を受けることができるのです。こうした環境のもと、EF英語能力指数は12位と、安定して高い英語力を維持しています。
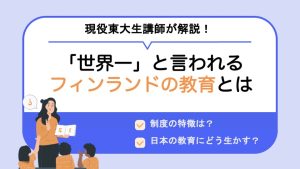
コミュニケーションに焦点を当てた韓国
アジア圏も見ていきましょう。韓国では1997年以降、小学3年生から英語教育が義務化され、早い段階から英語に触れる環境が整えられています。特徴的なのは、知識としての英語よりも「使うための英語」を重視している点です。
授業ではディベートやプレゼンテーションなど、実践的な活動を通して英語を使う機会が多く設けられています。
さらに、授業外でも英語を必要とする場面を意図的につくり、日常的に英語に触れる工夫がなされているのです。
こうした取り組みにより、EF英語能力指数は48位と、日本より好成績を収めています。
学習時間を確保した中国
中国では、一般的に小学3年生から英語教育が始まりますが、北京や上海などの一部都市では小学1年生から導入されるケースもあります。特徴は、文法や読解だけでなく、「話す」ことを含めた実用的な英語力の育成が重視されている点です。
さらに、中国の英語教育は学習時間の多さが際立っています。
週4回以上の英語の授業が行われるのが一般的で、これは日本の授業時間数の2倍以上です。
EF英語能力指数では86位と決して上位ではないものの、日本より高い水準にあります。
日本の英語教育の改革を阻む構造的な壁とは?
では、海外の英語教育を真似すれば日本人も英語を話せるようになるのではないか。そう思った方も多いことでしょう。
しかし、実際はそう簡単には行かないのです。
ここでは、日本の英語教育の改革を阻んでいる、構造的な問題を2つに分けて説明します。
学歴社会と入試制度が英語教育の方向性を固定
日本では、学校や学歴による序列が社会全体に強く根づいており、「よい高校からよい大学へ、そしてよい企業へ」という進路モデルがいまなお大きな影響力を持っています。
この構造のもとでは、大学受験が教育の最終目標になりやすく、英語学習も「入試で点を取るための勉強」に収斂(しゅうれん)していきます。
その結果、入試で評価しやすい読解中心の学習が主流となり、英語を使って伝える力は後回しにされがちです。
リスニングもペーパーテスト向けに形式化され、日常的なコミュニケーション能力を測るものにはなりにくいのが実情です。かつて大学入学共通テストにスピーキングテストを導入する案が公平性の問題から見送られたように、入試制度自体が「話す英語」を評価しづらい仕組みであることも大きな要因です。
いくら授業時間を増やしても、入試制度と学歴社会という枠組みが変わらない限り、英語教育の方向性が根本的に転換されることは難しいでしょう。
「話せるようになる英語教育」を実現するためには、学習内容だけでなく、それを縛っている社会の仕組みそのものを見直す必要があるのです。
詰め込み型カリキュラムが実践的英語を圧迫
日本では長年、学歴社会と入試制度を背景に、英語に限らず、ペーパーテスト向けの知識詰め込み型学習が中心となってきました。
近年は「思考力」や「生きる力」を重視する流れから、新しい教育内容や総合的な学習が導入されましたが、学力低下への懸念もあり、従来の詰め込み型が大きく見直されることはありませんでした。
その結果、古い学習内容に新しいカリキュラムが上乗せされ、教育現場がカリキュラム・オーバーロード状態に陥っています。
時間的余裕がないため、英語でも実践的な活動に十分な時間を割けず、学習時間をこれ以上増やすことも困難です。これは個々の学校や教員の工夫で解決できる問題ではなく、教育制度そのものが抱える構造的な問題だと言えるでしょう。
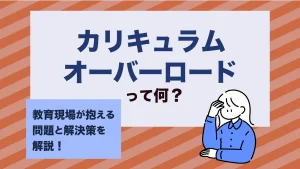
まとめ
日本の英語教育が長年抱えてきた課題は、個々の授業内容や指導法の問題というより、学歴社会やカリキュラム設計といった制度や社会的枠組みそのものに深く根ざしています。
英語を「使うための言語」として捉え直そうとする動きは繰り返し起きてきましたが、大学入試を頂点とする評価の仕組みが変わらない限り、教育の方向性も大きくは変わりません。
その結果、「話せる英語教育」を目指しながらも、実際には読解と知識習得に偏った学びが続いてきたのです。
今後、日本の英語教育が本当に変わるとすれば、それは評価や進路選択のあり方そのものが問い直されるときでしょう。
英語を学ぶことが点数や序列のためではなく、人とつながり、世界を広げるための営みとして位置づけ直される——そんな未来のために、教育を縛ってきた構造が根底からひっくり返る日が来ることを願わずにはいられません。
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。