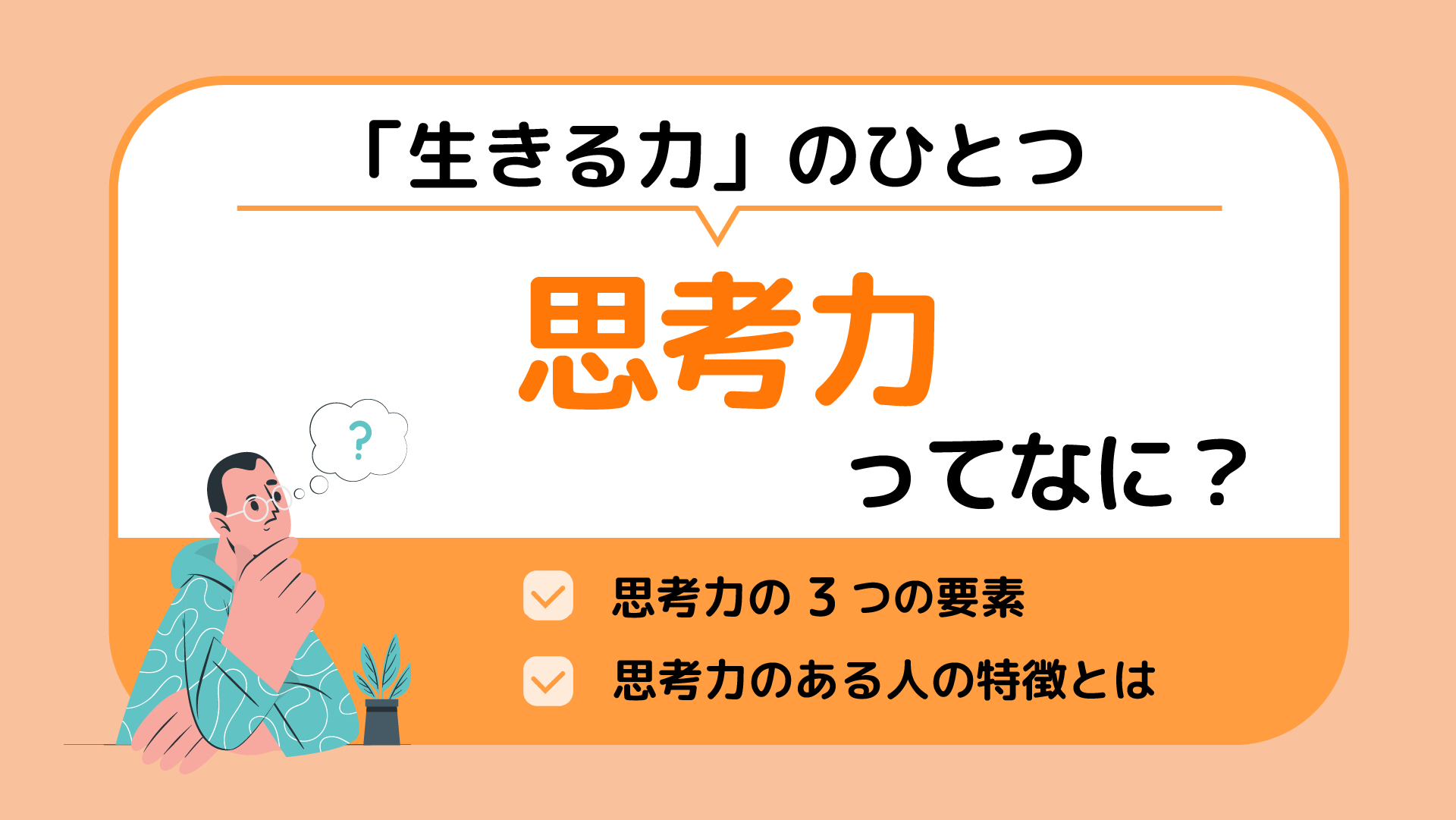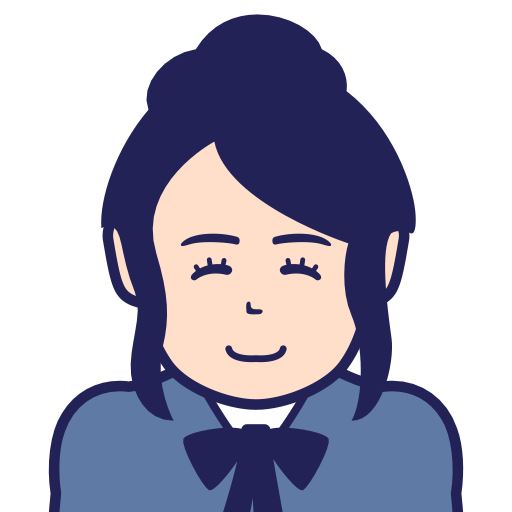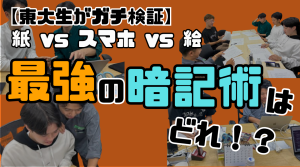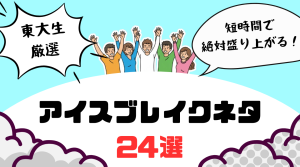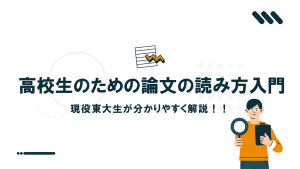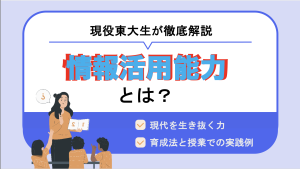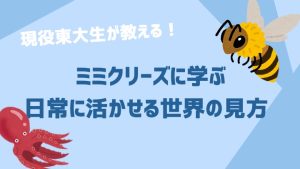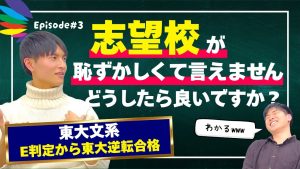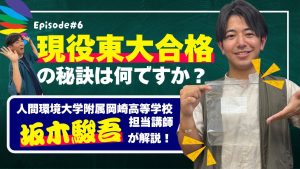現在、教育現場でも重要視されるようになってきた子どもの思考力。文部科学省の新しい学習指導要領に掲げられている3つの「生きる力」のひとつにあげられています。思考力は、現代を生きる子どもたちが未知の状況に対応するために欠かせない力の一つといえるでしょう。地球温暖化、ウイルス蔓延、経済問題など、激動の時代を生きる今の子どもたち。本記事では、これから生きる子どもたちに必要な思考力とその育て方について、具体的に解説していきます。【2025.9.30更新】
思考力は生きる力!?
思考力がなぜ「生きる力」となるのか。ここでは、思考力とは具体的にどのような力であり、子どもが成長する過程で将来的にどのような場面でいかされるのかについて、具体的な事例を織り交ぜながら紹介していきます。
そもそも思考力とは何か
そもそも思考力とは何でしょう。思考力は、一言で説明すると「考える力」。しかし、実はこの「考える力」にはさまざまな種類の力が含まれるのです。
東京大学の西成教授は、思考力を7つの考える力に分類しており、これらはどれも問題や困難に対処する力に繋がるものだといいます。その中でも、子どもたちが優先的に鍛えるべき代表的な3つの思考力を紹介します。
*詳しくはこちら
→「思考力」は鍛えられる!東大・西成教授が教える7つの思考習慣トレーニング
論理的思考力(ロジカルシンキング)
論理的思考力とは、物事を体系的に捉えて筋道を立てて考える力であり、あらゆる思考力の礎(いしずえ)ともいえるものです。別名、ロジカルシンキングとも呼ばれ、「どうしてこうなるのか」「次は何をすべきか」を冷静に考える力です。
具体的には、計画を立てたり問題を解決をしたり、さらには大きな決断をするときに大いに役立ちます。物事を正確に把握して論理的に考えることができるようになると、先のことや未知の問題についてもあらゆる状況を想定して場合分けし、最適な答えを導くことができるようになるのです。
批判的思考力(クリティカルシンキング)
現代世界は、さまざまな情報や選択肢であふれています。玉石混合の情報を取捨選択することは、とても容易ではありません。そこで重要となるのが、批判的思考力。英語で、クリティカルシンキングと呼ばれるものです。
情報や意見をそのまま受け入れず、「本当にそうだろうか?」と一度立ち止まって客観的に考える力、物事を疑って確かめる力が必要なのです。
なぜ、物事を「疑う」ことが大切なのでしょうか。疑うことは、判断を下す前に一度立ち止まって考えるきっかけを与えてくれるのです。あらゆる情報を鵜呑み(うのみ)にすることなく自分の力で判断することで、情報に振り回されたり予想外の不利益を被ることがなくなります。さらに、批判的思考力が身につくと客観的にものごとを捉える習慣がつき、周囲だけでなく自分自身を客観的にみつめて研磨することができるようになるのです。
インターネット社会の現代では、便利になった反面、真偽のわからない情報で溢れています。そんな現代にこそこの批判的思考力は重要です。
多面的思考力
多面的思考力とは、物事を多面的に捉えて考える思考力です。主観的な立場から考えるのではなく、自分とは異なる視野や視点に切り替えて考えるために用いられます。
多面的思考力が高い人は思考の多様性に富んでおり、幅広い価値観に寛容的です。自分の視点以外に、「他の人からはどう見えるか」を想像することで、1つのことから幅広い発見や気づきを得られます。多面的思考力の育成では、物事の見えていない部分にも視野を広げるための想像力・洞察力なども鍛えられるでしょう。
日常で思考力を使う場面
思考力には大きく分けて三つの主要な要素があることを説明しました。そのような思考力は私たちの日常生活でどのように役立つのでしょうか。
情報の取捨選択
情報の選別に関してよく耳にするのが、インターネット上の情報ではないでしょうか。しかし、私たちが日常生活において情報に触れる機会は、インターネットを利用しているときに限りません。人と会って話すとき、会話の一定割合は情報交換が占めています。
私たちは、生活のあらゆる場面で無意識のうちにさまざまな情報に接しているのです。しかし、思考力を働かせず一方的に情報を吸収してしまうと、混乱して正しい判断ができなくなってしまいます。そのような事態を防ぐためにも、先に述べた批判的思考力を最大限に活用して客観的に物事を評価する力が必要となるのです。
予想外なことへの対応
2020年以降のコロナウイルスの流行は、ほとんど誰も予測ができなかった出来事の一つでしょう。世の中が予期せぬ出来事に直面する中、真っ先にオンライン授業を導入したのが東大でした。その成功の秘訣として、迅速な環境整備やシステム問題の評価、学生に向けた理解しやすい情報発信などが指摘されていますが*、どの対応をとっても入念な準備と思考が欠かせません。
また、大学に限らず世の中にはパンデミックの状況を逆手に取って、新しいことに挑戦したりビジネスを拡大したりすることに成功した人もいます。こうした人々は、不測の事態を経験したときこそ、自らの思考力を最大限活用して機転を利かせることができるのです。
*詳しくはこちら
→各校つまずくコロナ禍でのオンライン授業、東大が「異例の速さ」で始められたわけ
夢や目標を実現するため
夢や大きな目標を実現するためには、計画性をもって行動することが不可欠です。しかし、目標を達成することはもちろん、そのための計画を立てることも簡単なことではありません。実現したいことから逆算して、与えられた時間や環境の中でいかに工夫するか論理的な道筋を立てなければなりません。
また、計画の内容自体が実現困難なものとなってしまっては元も子もありません。計画を実行する際に、途中で立ち止まって自分の状況や計画の実現可能性を客観的に評価する力こそが、目標達成には不可欠です。
戦略的に目標を実現する方法について詳しく知りたい方は、相生晶吾氏の著書『東大式 目標達成思考』をぜひ手に取ってみてください。

思考力のない人の特徴
思考力が何か、なぜ必要かは分かったけれど、自分に思考力があるかわからない。そんな人も多いかもしれません。
思考力がない、伸びない人には共通する特徴があります。この特徴に当てはまるからといって単純な思考に偏ってしまうわけではありませんが、当てはまる箇所はないか参考にしてみてください。
よく考えずにすぐ調べてしまう
インターネットが普及したおかげで、世の中は便利な時代になりました。何か疑問に思うことや気になることがあれば、思いついた単語で検索するとすぐに何かしらの情報が手に入ります。しかし、すぐに検索してしまうことは危険です。
なぜ問題なのでしょう。
ポイントは、「すぐに」調べてしまうということにあります。自分で立ち止まって解決策を考えることなく、携帯やパソコンに自分の問いをすぐに投げかけてしまっては、どうしても考える力が身につかなくなってしまいます。どんな問題でも、解決策は十人十色です。問題解決のファーストステップは、自分のおかれた状況や求めていることを捉えて自力で解決策を考えてみることなのです。
周りに影響されやすい
私たちは、日常生活において常にさまざまな物事を見たり聞いたりしています。しかし、受け取る情報の全てが自分にとって必要かつ有用な情報とは限りません。すなわち、自分が見聞きするものを、全て自分自身の中に取り込む必要はないのです。
そんな中、思考力のない人は自分の見聞きしたものから有用なものを見極めることができません。その結果、あらゆるものをそのまま吸収してしまい、周囲の影響をうけやすいのです。人間はみな多少なりとも周囲の影響を受けるものですが、常に周囲に振り回されては自分の軸を見失いかねず、結果的に人々から信頼されにくくなってしまうかもしれません。
不安になりやすい
思考力のない人は、自分で考えることなく他人から得た情報を鵜呑みにしたり筋道が不確かなまま判断してしまったりする傾向があります。そのため、決断にいたる道筋が不明確となってしまい、自分の行動や決断に自信が持てないことがときどきみられます。さらに、自分の不安に対処するために、自分の行動や決定を考察したり改めたりすることができず、なかなか不安を払拭できない状態に陥ることもあるでしょう。
人生は行動と決断の連続です。筋道立てて物事を考えたり客観的に自分の行動を考察する力は、自信をもって生きていくことに直結するのです。
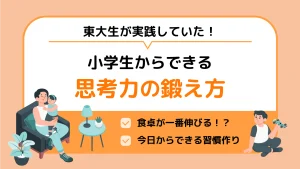
思考力のある人の特徴
ここからは実際に思考力がある人の特徴を詳しくみていきます。自分が思考力を鍛える際は以下のポイントを伸ばすことを参考にしてみてください。
判断力がある
自分で考えることが得意な人の特徴の一つに、判断力があることがあげられます。
論理的に物事を考えることが得意な人は、比較的短時間でさまざまな情報を整理して筋の通った考えを構築することができます。また、自分の状況などを客観的に捉えるスキルにも長けているため、考えが閉塞的になりにくく視野を広く保つことができるのです。
冷静で何事にも動揺しにくい
思考力は、未知の状況に対応する力です。
日常的に考える習慣のある人は、不利な状況や不測の事態に陥った場合でも、アンテナを張って情報を取集し、そこから解決策を編み出すことができるのです。また、普段から考える習慣のある人は、どんな状況でも自分の力で改善することできることを自身の経験からわかっています。結果的に、多少予想外のことが起こっても、冷静に物事を判断することができます。
話に説得力がある
頭の中が整理されている人は、自分が伝えたい内容も容易に整理しやすくなります。そのため、相手にわかりやすく魅力的に説明することが得意なのです。
また、視点を変えて聞き手の立場から内容を捉えることもできるため、どうすれば相手の意識を惹きつけることができるかを想像することができます。思考力があると、人々を説得する力も自然と身につくのです。
計画性がある
思考力のある人は、頭の中を整理することが得意です。整理することとは、雑多なものの秩序を整えて、不要なものを取り除くことを意味します。それと同じようなことを自分の頭の中で行うのです。
具体的には、やるべきこととそうでないことを分類し、やるべきことに優先順位をつけます。その結果、計画性が生まれて物事が遂行しやすくなるのです。
思考力を高めて、予測困難な現代を生き抜こう!
これまで見てきたように、思考力は、予測困難な時代を生き抜くための羅針盤ともいえる重要な「生きる力」です。物事を筋道立てて考える論理的思考力、情報を鵜呑みにしない批判的思考力、そして多様な視点を持つ多面的思考力は、日々の選択や問題解決、そして夢の実現に至るまで、あらゆる場面で私たちを支えてくれます。
思考力を磨くことは、単に知識を増やすこととは異なります。それは、情報や変化の波に流されることなく、自らの意思で判断し、自信を持って未来を切り拓くための「軸」を育てることです。これからの時代をより豊かに、そして自分らしく生きていくために、思考力は最も信頼できるパートナーとなるでしょう。
監修者
西岡壱誠(にしおか・いっせい)
1996年生まれ。偏差値35から東大を目指すも、現役・一浪と2年連続で不合格。崖っぷちの状況で開発した勉強法により、偏差値70、東大模試で全国4位になり、東大合格を果たす。そのノウハウを全国の学生や学校の教師たちに伝えるため、在学中の2020年に株式会社カルペ・ディエムを設立、代表に就任。全国の高校で「リアルドラゴン桜プロジェクト」を実施、高校生に思考法・勉強法を教えているほか、教師には指導法のコンサルティングを行っている。テレビ番組『100%!アピールちゃん』(TBS系)では、タレントの小倉優子氏の早稲田大学受験をサポート。著書『「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく 東大読書』はシリーズ累計40万部のベストセラー。
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。