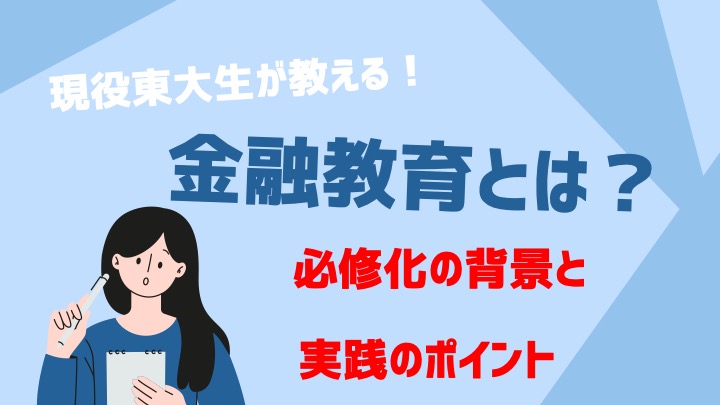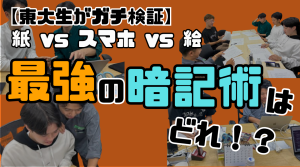2022年4月から必修化された「金融教育」。言葉としては分かりますが、これだけではふわりとしていますね。
金融教育とは一体どのような教育・学習なのでしょうか。また、なぜ必修化されたのでしょうか?
この記事では、金融教育の内容や実践のポイント、海外の金融教育の事例などを、東大教育学部生の碓氷明日香が徹底解説します!
金融教育とは?
そもそも、金融教育とはどのようなものなのでしょうか。ここでは、概要とその重要性を説明します。
金融教育の概要
金融教育とは、単にお金や金融商品の扱い方を教えることではありません。
貯金や投資といった資産形成だけでなく、収入と支出のバランスを考えたり、必要に応じてローンや保険といった制度を理解したりする力を育てる教育のことを指します。
お金を通じて、社会で生活するために必要な知識や判断力を身につけるための教育、というわけです。
学校現場では、家庭科や社会科、数学など、複数の教科と関連させながら実践できるのが特徴です。
金融教育の重要性
現代社会では、キャッシュレス決済やネットバンキング、投資アプリなどが次々と世に出て、お金の扱い方がどんどん変化しています。
その中で、金融リテラシーを持たずに大人になると、消費者トラブルや多重債務に巻き込まれてしまうかもしれません。
早くから金融教育を受けていれば、「お金=単なる消費手段」ではなく「人生を設計するための資源」と捉えることができ、そうしたトラブルを回避できる上、将来のキャリアやライフプランを主体的に考えられるように育ちます。
現代社会を生きる子どもたちのために、金融教育は欠かせないのです。
必修化の背景
2022年4月より学習指導要領の改訂に伴い、金融教育が必修化されました。
この節ではなぜ必修化に至ったのか、その背景をより詳しく見ていきましょう。
社会経済環境の変化
かつては「銀行に預けておけば利息で資産が増える」時代もありました。
しかし、近年は長引く低金利の影響で、預貯金だけでは資産の成長を見込むことが難しくなっています。
さらに、終身雇用や年功序列といった従来の働き方は崩れ、転職や副業をする人も増加しています。
定年退職後に十分な退職金を得て老後を安泰に過ごせるとは限らない時代になりました。
こうした背景から、若いうちから資産運用やライフプランニングの基礎を学ぶ必要性が高まっているのです。
金融トラブルの低年齢化
金融商品が多様化し、インターネットを通じて誰でも簡単に投資や契約ができるようになった一方で、若者の金融トラブルも増加しています。
特にSNSをきっかけとした投資詐欺や、オンラインゲームに関連した課金トラブルなどは、中高生にも身近な問題です。
さらに、2022年の成人年齢引き下げにより、18歳からクレジットカードやローンの契約が可能になりました。
自己責任で契約を結べる一方で、知識不足のまま判断してしまうリスクも高まっており、早い段階からの金融教育が不可欠とされているのです。
海外と比較した教育の遅れ
日本の金融教育は、他国と比較すると進んでいません。
2022年の金融リテラシー調査によると、世界共通の金融リテラシー正誤問題における日本の正答率は、米国、英国、ドイツ、フランスのそれを下回っています。
また、「金融知識に自信がある人」の割合は米国が71%なのに対して、日本は12%しかいませんでした。
こうした金融教育の遅れを、必修化によって取り戻す狙いがあると考えられます。
出典:https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/literacy_chosa/2022/pdf/22literacyr.pdf
金融教育で学ぶこと・身につく力
では、金融教育では具体的にどのようなことを学ぶのでしょうか。
金融広報中央委員会が作成した「金融教育プログラム」によると、その内容は主に4つの分野に分類することができます。
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
生活設計・家計管理に関する分野
この分野で学ぶことはさらに「資金管理と意思決定」「貯蓄の意義と資産運用」「生活設計」「事故・災害・病気などへの備え」の4つに分けられます。
それぞれの詳しい内容は以下の表の通りです。
| 資金管理と意思決定 | 財の有限性を理解し、予算の中でよりよい生活を築くための意思決定を実践する技能・態度を身につける。 |
| 貯蓄の意義と資産運用 | 長期的・継続的に貯蓄・運用に取り組む態度、リスクとリターンの関係を踏まえ、自己責任で金融商品の運用を行う態度を養う。 |
| 生活設計 | 計画的にお金を使い、自分の価値観に基づいて将来を展望しながら生活設計を立てられるようにする。 |
| 事故・災害・病気などへの備え | 日常生活におけるリスクを理解し、安全な行動を心掛けるとともに、不測の事態に備える方法としての貯蓄と保険の機能について理解する。 |
お金の生活に密接に関わっている側面について詳しく学ぶイメージですね。
「計画的にお金を管理する力」「ライフステージに応じて資金を見積もる力」などが身につきます。
金融や経済の仕組みに関する分野
この分野は「お金や金融の働き」「経済把握」「経済変動と経済政策」「経済社会の諸課題」の4つに分かれています。
| お金や金融の働き | 金融機関や中央銀行の機能、金利の働きと変動について理解する。 |
| 経済把握 | 家計・企業・政府等の役割、市場の働きや機能、市場経済の意義や海外経済との関係を学ぶ。 |
| 経済変動と経済政策 | 景気の変動と影響、経済政策や金融政策について理解する。 |
| 経済社会の諸課題 | 経済社会が抱える問題に関心を持ち、合理的・主体的に考える態度を身につける。 |
社会全体におけるお金の動きについて広い視野を持って学ぶイメージです。
「社会の仕組みを理解し、主体的に意思決定できる力」や「数字やデータを根拠に考える力」が身につきます。
消費生活・金融トラブル防止に関する分野
この分野は「自立した消費者」「金融トラブル・多重債務」の2つに分かれています。
| 自立した消費者 | 消費者の権利と責任を理解し、消費生活に関する情報を収集し適切に活用できる技能を身につける。 |
| 金融トラブル・多重債務 | 消費者問題の背景を理解し、金融トラブルや多重債務などに巻き込まれない態度を身につけ、事態に対処できる知識と技能を学ぶ。 |
ひとりの消費者として消費生活に潜む危険を知り、トラブルを未然に防いだり、仮に巻き込まれてしまった際の対応を学ぶイメージです。
「情報を批判的に吟味する力」や「安易に契約や取引に巻き込まれない判断力」を身につけることができます。
キャリア教育に関する分野
この分野は「働く意義と職業選択」「生きる意欲と活力」「社会への感謝と貢献」の3つに分かれています。
| 働く意義と職業選択 | 勤労の意義と収入の価値を理解し、職業選択について主体的に考える態度、労働者の権利と義務を生かす態度を身につける。 |
| 生きる意欲と活力 | 経済社会発展の原動力を理解し、自らの夢を実現する方法を考え、実践する態度を身につける。 |
| 社会への感謝と貢献 | よりよい社会を築くために他者と協働することの大切さを学ぶ。 |
社会構成員のひとりとして、自分の役割をつきとめ、他者と協力しながらよりよい社会を作ることの大切さを学ぶイメージです。
「自分のキャリアと人生設計をお金の観点から考える力」「長期的な視野で意思決定する力」「他者と協働し、問題を解決していく力」を育てることができます。
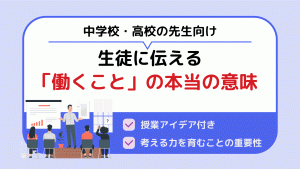
授業に金融教育を取り入れる方法
金融教育はひとつの科目になったわけではなく、教科横断的な形で少しずつ学びます。
では、どのように授業に金融教育を取り入れれば、最大限の効果を発揮できるのでしょうか。
ここでは2つの具体的な実践方法を挙げていきます。
日常生活の例を教材化する
金融教育は「机上の知識」ではなく、日常生活の中にある具体的な事例を扱うことで、生徒にとって実感を伴う学びになります。
例えば、コンビニでのキャッシュレス決済と現金払いそれぞれのメリットとデメリットの両方を考えさせる授業なら、経験を活かした気づきが得られるはずです。
また、修学旅行や文化祭などの学校行事の予算を題材にして、「どこにどれだけお金を配分するか」を話し合うことも効果的でしょう。
こうした題材を通じて、生徒は限られた予算の中でどうやりくりすればよいかを体感し、主体的に選択できるようになるはずです。
ゲームやシミュレーションを使う
お金の流れをリアルに体験できるのがゲームやシミュレーションの強みです。最近では、授業で使えるように設計されたシミュレーションゲームも増えてきています。
ゲームやシミュレーションは生徒が楽しみながら金融知識を身につけることができる、おすすめの方法です。
例えば、職業や収入の異なる架空の人物の家計データを提示し、「この人はどうやって生活を維持していくべきか」をグループでシミュレーションしてみると家計のやりくりの大変さを理解し、資産を運用する意欲を育てることが可能です。
また、株式学習ゲームという授業用の株式の模擬売買シミュレーション教材も存在します。
これは、3〜4人のチームに分かれた生徒たちが、仮想所持金1,000万円をもとに、東京証券取引所に上場している銘柄を売買しながら、最終的な所持金を争うゲームです。
実際の株価をもとにして計算するため、かなり現実に近い学びを得ることができます。
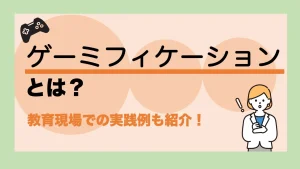
海外の事例から学ぶ
上述の通り、日本の金融教育は他国に比べて遅れを取っているわけですが、他国ではどのような教育が行われているのでしょうか。金融教育先進国の事例を紹介します。
参考:https://www.miraive.co.jp/examples-of-countries-with-advanced-financial-education/
アメリカ
アメリカでは、学校教育の方針は州ごとに異なっていて、金融教育に関しても同様です。
しかし、パーソナル・ファイナンスに関しては、普及活動が進められ、多くの教育現場で採用されています。
10歳の時点で、「投資をする理由を説明する」「単利・複利で得られる利益をそれぞれ計算する」「単利よりも複利のほうがリターンが多く、有利である理由を説明する」ことがゴールとなっていて、高校卒業までに「富を築き、ファイナンシャル・ゴールを達成するにはどうすればよいか説明できる」ように教えられるようです。
日本と比べて、早い段階できちんとした金融知識が身につくようにカリキュラムが組まれていることがわかるでしょう。
イギリス
イギリスでは、2014年に公立学校のカリキュラムに金融教育が導入されました。
小学校を卒業するまでに金融と経済について学び、お金と社会構造の理解を目指すことが目標になっています。
「お金の管理の仕方」「批判的な思考のできる消費者になる」「リスク管理と感情」「金融が人々の生活に果たす役割」の4つの軸を中心に、お金の計算や資産形成だけではなく、社会的責任を果たす能力を育成するカリキュラムになっているようです。
日本の金融教育はイギリスのそれを参考にしているのでしょうか。
フィンランド
フィンランドの義務教育は7歳から18歳までの11年間での基礎教育により行われます。金融リテラシーの育成は、学齢期の児童・生徒を主なターゲットに取り組まれているようです。
しかし、金融リテラシーは常に変化する社会・経済状況により陳腐化していくため、生涯学習で最新の知識に更新することが必要という考えもあります。
学校、就労期、退職後に分けて生涯学び続ける金融教育のシステムの整備が進んでいます。
まとめ
金融教育について詳しく解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
金融教育は、単にお金の知識を伝えるものではなく、子どもたちが未来を主体的に切り拓くための力を育てる教育です。
日常の選択一つひとつが将来を形づくることを理解させるのは、教師の重要な役割のひとつと言えます。授業の中に小さな工夫を取り入れるだけでも、生徒たちは自分の人生を設計する力を少しずつ育んでいきます。
次代を生きる子どもたちのために、金融教育をより効果的なものにする方法を考えてみてください。
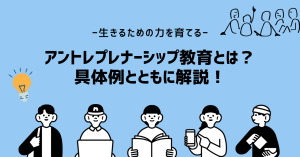
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。