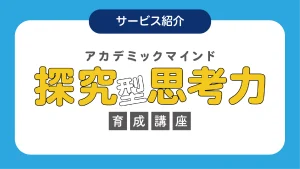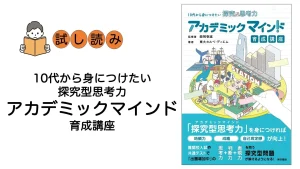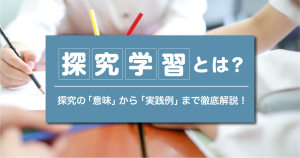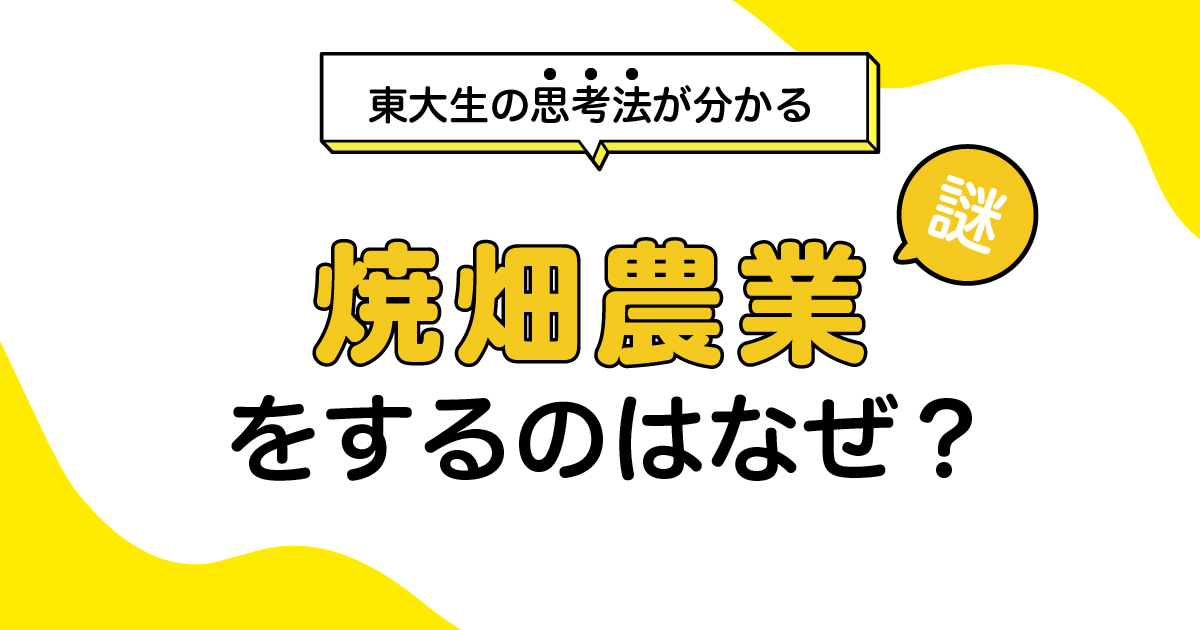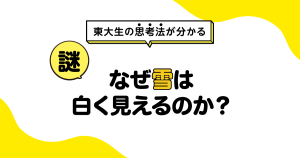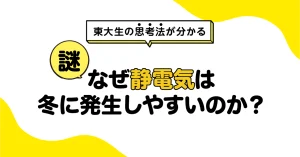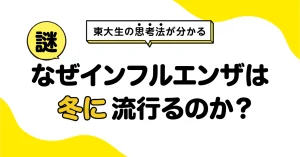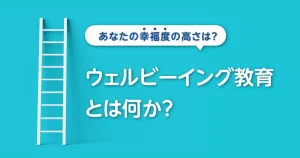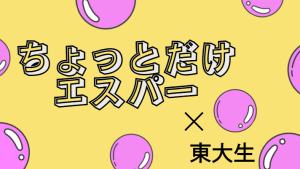焼畑農業と聞くと、「森を壊して環境に悪そう…」というイメージを持つ人が多いのではないでしょうか? 焼畑農業はなぜ世界中で長い間行われているのか、アカデミックマインドを使って解き明かしましょう。
問いを分解してみよう!
この疑問も、いくつかの小さな問いに分けて考えていくと、ぐっと分かりやすくなります。
<例>
・森を焼くと何が起きるんだろう?
・なぜ火を使う必要があったのかな?
・どんな地域や時代で役立ったのだろう?
なぜ森を焼くんだろう?
森を焼くことで出てくる灰には、カリウムやナトリウム、リンといった天然の肥料が含まれています。これが土に混ざることで、肥料が少ない土地でも作物が育ちやすくなります。
さらに火を入れることで、雑草の種や害虫を一掃できるという効果もあります。
農薬や化学肥料がなかった時代には、とても合理的な方法だったのです。
どんな地域・時代で行われていたの?
焼畑は、日本では古代から昭和初期まで山間部で行われ、アワ・ヒエ・ソバなどが栽培されました。
世界に目を向けると、東南アジアの山岳地帯、アフリカの熱帯地域、アマゾンの森林、さらには北欧の寒冷地でも実践されています。
いずれも共通するのは、肥料が乏しく、人口が少なかった時代や地域であったことです。
土地を数年使ったら休ませ、森が回復するのを待ってから再び利用する。このようなサイクルなら、持続可能だったのです。
まとめ
焼畑農業が行われてきたのは、
・灰による肥料効果がある
・害虫や雑草を減らせる
・痩せた土地でも作物が育つ
といった理由からでした。
一方で、人口が増えて土地を休ませる時間がなくなると、森が回復できず環境破壊につながります。
だからこそ現代では「環境に悪い」と言われることもあるのです。
ここまで考えると、さらにいくつかの新しい問いも浮かんできます。
・現代の技術であれば「持続可能な焼畑」は可能なのか?
・現代の農業問題(農薬・化学肥料・森林伐採)と比べたとき、焼畑は本当に不利なのか?
・焼畑で育てられる作物と、普通の畑で育てられる作物にはどんな違いがあるのか?
こうした「さらに問いを立てる姿勢」こそが、東大生が大切にしている「アカデミックマインド」の第一歩です。
アカデミックマインドとは
このように、1つの問いを「分解」し、「仮説」「検証」する一連の思考法を、「アカデミックマインド」と呼んでいます。
AIなどさまざまな技術が発達する中、これからの世代に求められるのが「思考力」です。共通テストや大学入試でも「自分で考える力」が試されるようになっています。
カルぺ・ディエムでは、現役東大生と一緒に「身の回りにあふれる疑問」と「五教科の勉強」を結びつけた課題に取り組み、自ら問いを立て、仮説を作り、検証する一連の思考法「アカデミックマインド」の獲得を目指す講座「アカデミックマインド育成講座」を実施中です。