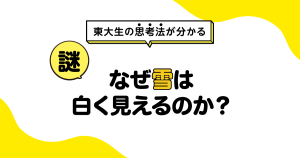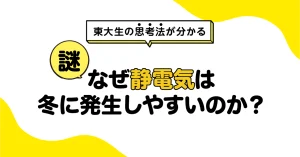近年、注目されつつある「チャイルドペナルティー」。実際、この言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この言葉は、子どもを持つことによって、男女間で雇用格差が生まれ、女性の賃金が低くなったり、社会に復帰することが難しくなったりすることを指しています。
今回は、東京大学教育学部の碓氷明日香が、この「チャイルドペナルティー」とは何なのか、その実態に迫ります。原因と影響、そして解決策を詳しく解説していきます!
チャイルドペナルティーとは?
そもそも、チャイルドペナルティーとは、「子どもを持つことで生じる、社会的・経済的に不利な状況」のことを言います。本来、男女ともにその状態に陥る可能性があるはずなのですが、現状、男性よりも女性の方が陥りやすいことから、「マザーフッドペナルティー」とも呼ばれています。
子どもを産むことによって、その前と比べて収入が下がってしまうことがあります。みなさんの周りにも、出産を期に退職したり、育児休暇を取ったり、時短勤務にしたり、雇用形態を非正規に変えたりといった選択を迫られている人がいるのではないでしょうか。また、収入が減るだけではなく、そもそも社会に復帰すること自体が難しくなってしまうというケースもあるようです。
このように、子どもを作ることで、社会的にも経済的にも「損をしてしまう」のがチャイルドペナルティー、というわけですね。
世界と比べた日本の現状
チャイルドペナルティーは世界各国で起きている現象ですが、その中でも、日本はその程度が大きいのが現状です。
このグラフは、日本、アメリカ、ドイツ、デンマークの4カ国における、出産前後の収入の推移を示したものです。横軸が第1子出産の年を0として出産前をマイナス、出産後をプラスで表した、時間軸。そして、縦軸は出産前年(-1年)の収入を基準とした、各年の収入の割合を示しています。
出産後の収入の変化は、日本とドイツが似たような形になっていて、アメリカとデンマークと比べると大きく変化していると言えます。そして、出産直前の収入の落ち込み具合は、日本が最も顕著と言えるでしょう。
この原因として考えられるのは、出産だけでなく、結婚や妊娠をきっかけに退職したり労働条件を変えたりする日本特有の文化でしょう。例えば結婚を期に会社を辞めることは「寿退社」と言われ、祝われるものです。しかし、この現状を見ると、手放しに喜べる状態ではないのかもしれません。
チャイルドペナルティーの原因
では、チャイルドペナルティー、そしてマザーフッドペナルティーの背景には何があるのでしょうか。原因は、決して女性個人によるものではありません。社会の価値観がそうさせているのです。
男女の賃金の差
まず1つ目は、男女の賃金の差です。男女共同参画社会が実現されつつある中、それでもやはり、一部の会社では男性の方が賃金が高く、女性の方が低いという格差が存在します。その結果、男性が外で働いて賃金を得て、女性が育児を担う、という役割分担をした方が、「効率的」であり、その選択をする家庭が多くなってしまうのです。
そして、すでに述べたような、収入の減少や社会からの孤立が、女性を中心に起こってしまう、というわけです。
「育児は女性がするもの」という固定観念
そして2つ目は、「育児は女性がするもの」という固定観念です。これも時代とともに薄れてきている価値観ではありますが、未だ根強く残っている世代、地域もあるようです。
この考え方のもと、夫婦間で育児分担がうまくいかず、女性が仕事を辞めたり減らしたりせざるを得ない家庭があります。
夫婦間の問題に加えて、そこに会社の問題が加わってくることも。女性は育児に時間を割くだろうから、もしかしたら会社を早退する機会が増えるかもしれないし、途中で辞められてしまうかもしれませんね。それを踏まえて、会社は給料を上げるのを渋ったり、昇進をさせないという考え方をするかもしれません。これは出産前も同様です。そして、女性側は女性側で、その会社の意図をくんで、頑張っても昇進できない、とやる気を失ってしまうかもしれないし、また、子どもの発熱などでしょっちゅう早退していては、周りに対して引け目を感じてしまうかもしれないですよね。結果として、会社を辞める選択をすることになるでしょう。
これらは全て、「育児は女性がするもの」という考えから始まっています。この固定観念がなくならない限り、夫婦間での役割分担も、会社での待遇も改善しないのです。
チャイルドペナルティーが及ぼす影響
チャイルドペナルティーが起こると、誰にどのような影響が及ぶのでしょうか。個人、社会それぞれの視点で考えてみます。
個人への影響:女性の仕事への意欲が下がる
出産がきっかけで、仕事と家庭の両立に悩むことになる女性が多くいる中、そんな女性を見て、それなら最初から働かない方がいいのではないか、真面目に働くだけ無駄なのではないかと考える女性もいることでしょう。就業意欲が下がってしまうのです。
それは、本来なら頭の中で描いていたキャリアを形成できたかもしれないのに、そのチャンスを失ってしまうことを意味します。これでは、平等とは言えませんね。
社会への影響(1):出生率が低下する
子どもを産むことによって、社会的に孤立したり、収入が減って自由に生きることが難しくなってしまうのなら、そもそも産まない方がいい、と考える人も増えるでしょう。チャイルドペナルティーが存在することと、子どもを産まない選択をすることの間に因果関係があることは明白です。
また、実際に、相関関係も示されています。
これは、チャイルドペナルティーの度合いを横軸、出生率の高さを縦軸に取り、8カ国におけるこれらの数値の相関関係をグラフにしたものです。強い負の相関があることが見て取れるでしょう。
出生率が低下すれば、少子化がさらに進み、社会保障への現役世代の負担の増大など、さまざまな問題に発展することが考えられます。
社会への影響(2):組織・国が成長できない
1つ目に書きましたが、チャイルドペナルティーの存在は労働意欲の低下につながります。そうなれば、労働生産性は明らかに落ちるでしょう。また、仕事を辞める人が増えれば、労働力の確保も難しくなります。そこに少子化が重なってくるのです。結果として、組織や国として成長するスピードが低下することが予想されます。
チャイルドペナルティーの解決方法
では、どうすればチャイルドペナルティーを解決することができるのでしょうか。もちろん、夫婦間で話し合って育児分担をすることは解決策として言うまでもありませんが、それだけでは根本的解決にはなりません。社会として、考え方を変えていく必要があるのです。
労働時間より労働生産性を重視する
日本には長時間労働をよしとする文化があります。定時を過ぎても長く会社に残って仕事をする人が偉い、という風潮ですね。でも、本当に大切なのは時間よりも生産性ではないでしょうか。
本当に評価されるべきは、長い時間働いている人ではなく、短い時間で成果を上げている人ですよね。そういう人が評価される仕組みを作っていく必要があります。そうすれば、子どもが生まれて長時間働けないから、という理由で離職する人は減るでしょう。短時間でも結果を残せば評価されるのですから。
また、労働生産性を重視することは、チャイルドペナルティーの解決につながるだけではなく、残業代の削減、採用力強化など、企業にとってもメリットがあります。
男性の育児参加を世の中に浸透させる
これは近年少しずつ浸透してきていますが、まだまだ十分とは言えません。育児休暇を取りづらかったり、早退を言い出しにくかったりという、男性の育児参加を阻む要因はまだそこら中にあるようです。
企業は社会の流れに乗って、男性社員が積極的に育児に参加できる雰囲気、制度作りをすることが今後重要になってきそうです。そうすれば、出産後も女性は職場に残りやすくなるでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。チャイルドペナルティーは、当人だけの問題ではありません。企業、そして国が対策を考えなくてはならない問題です。
染み付いている固定観念を引き剥がし、時代の流れに乗って考え方をアップデートしていくことで、子どもを産むことが決して損にならない社会を作っていく必要があります。まずは身近なところから、考え方を変えられるところはないか、探してみましょう。
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。