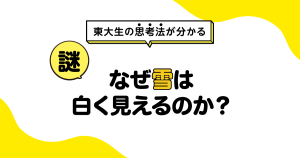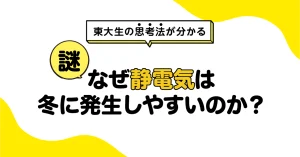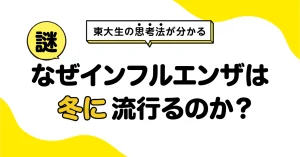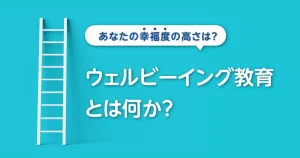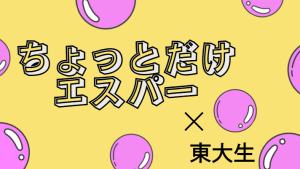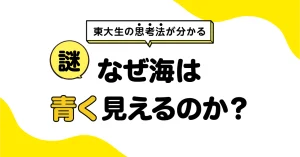こんにちは、選挙マニアの東大生です。
この記事では2025年の参議院選挙を”楽しむ”ためのポイントを紹介します。選挙は国民の民意を反映し我が国の行く方向を決める大切な機会であると同時に、戦略や駆け引きといった要素も含まれた一種のレースであると感じています。この記事では主にその側面を楽しむために知っておくべきことを、2025年7月20日に投開票が行われる選挙を参考に紹介します。どこに注目すれば良いのかなどを紹介していきますのでぜひ最後までご覧ください。
参議院選挙と衆議院選挙の違い
国政選挙には、今回行われる参議院選挙の他に衆議院選挙があります。参議院選挙と衆議院選挙の違いはどこにあるのでしょうか。
選出する議員数の違い
衆議院の定数は465議席、参議院の定数は248議席です。衆議院選挙では1回の選挙で465人全員を選挙するのに対し、参議院選挙は一回の選挙で半分の124議席を入れ替えます。そのため、衆議院は総選挙と呼ばれることがありますが、参議院では総選挙という呼び方はせず、通常選挙と呼ばれます。
選挙制度の違い
衆議院
衆議院選挙においては小選挙区比例代表並立制が導入されています。小選挙区制については289の小選挙区が全国に設置され、その中の一位の候補者のみが選出されます。残りの176人については比例代表で選出されます。全国に比例代表の選挙区(通常はブロックと呼ばれる)が11個設置され、それぞれのブロックに人口に合わせて割り振られた6〜28の議席を巡って争い、有権者は投票用紙に政党名を記載します。衆議院選挙の比例代表は政党が当選順位を指定することができる(拘束名簿式)ので、小規模政党では党首を比例名簿の一位に設置している事例があります。なお国政政党(後述)に限り、小選挙区と比例代表の両方に出馬することができ、小選挙区で落選した場合に、所属政党が比例代表で議席を獲得していた場合は復活当選の可能性があります。一方小選挙区の供託金没収点(有効票数の10%以下の投票)を下回ると復活できない、比例名簿は同じ順位に複数の候補者を記載することができるなど、細かいルールがたくさんあります。
参議院
参議院選挙においては選挙区選挙と比例代表選挙が独立して存在します。選挙区選挙では都道府県ごとに選挙区が設定され、人口規模に応じて1〜6の定数が割り振られています。なお島根と鳥取、徳島と高知については人口が少ないため、2県合わせて1議席が割り振られています(合区)。比例代表選挙においては、衆議院と異なり全国が1つの選挙区となっており、当選順位も政党は原則指定することができません(非拘束名簿式)。そのため参議院選挙では政党内での当選順位を指定する手段として、比例代表においても個人名での投票を認めています。個人名で投票した場合、その候補者が所属する政党に一票が割り振られると同時に政党内での順位争いへの一票も投じることになります。ただし2018年から特定枠の制度ができ、政党側が当選者をあらかじめ指定することができるようになりました。なお定数は選挙区が74議席、比例代表が50議席です。
参議院選挙の特徴
国政政党成りが多い
国政政党とは
近年の参議院選挙では単なる政治団体から国政政党にグレードアップする事例が多くなっています。国政政党になると、得票数と議員数に応じた政党助成金を得ることができる他、衆議院選挙での扱いが有利になります。国政政党でなければ、衆議院の小選挙区は定数の20%以上の候補者を擁立しなければならない、小選挙区の政見放送ができない、重複立候補ができないなど、不利な扱いを受けることになるので、国政に進出する政治団体は基本的に国政政党になるための「政党要件」を満たすことを目指します。
政党要件を満たすために
政党要件を満たすためには、国会議員が合計5人以上所属していること、もしくは前2回の参議院選挙か直近の衆議院選挙のいずれかで最低での2%の得票を得ていること(政党助成法においては2%の得票に加えて一人の国会議員が所属していること)が求められます。
この2%の得票は小選挙区、選挙区、比例代表のいずれかで、全国を通算して2%以上獲得できていれば良いことになっています。
政党要件を満たすためにかかるお金の違い
参議院選挙
参議院では国政政党以外の場合、立候補者が党の合計で10人以上いれば比例代表に出馬できることになっています。比例10人でも、選挙区7と比例3でもOKです。参議院の選挙区の供託金は1人300万円、比例は1人600万円なので、最安だと比例1人+選挙区9人で3300万円です(今回もこの出し方をしている政党があります)。比例代表は50議席あるので、約2%を獲得すれば1議席を得ることができ、政党助成法上の政党要件を満たすこともできるのです。ちなみに45の選挙区全てに候補者を擁立し2%を目指すのであれば、300万円×45人=1億3500万円ですね。
衆議院選挙
衆議院の比例代表は11ブロックあるので、全国で2%を取るために全ての比例ブロックで候補者を擁立する場合、先ほどの定数の20%以上擁立させなければならないという規定を踏まえて最低でも1人600万円×43人=2億5800万円の供託金を納める必要があります。全国で2%を獲得すれば良いので人口が少ないブロックや得票が見込めないブロックには候補者を擁立しないという方法もあります。2024年の衆議院選挙では日本保守党が国政政党になりましたが、この時も東北や九州などのブロックには候補者を擁立していませんでした。小選挙区で2%を獲得しようと思えばさらに大変です。1人300万円×289人=8億6700万円もかかってしまいます。
これらの情報からわかる通り、参議院選挙においては、衆議院選挙よりもお得に国政政党になることができるのです。仮に比例か選挙区のどちらかで2%を超えることができ、どこかで最低1人当選すれば、1年間で約1億6000万円、6年間で約9億6000万円の政党助成金を得ることができます。供託金が全く返金されなかったとしても、選挙を通してかなり儲けることができるのです。
なお近年では2019年参議院通常選挙で「NHKから国民を守る党」(現NHK党・みんなでつくる党)と「れいわ新選組」が、2022年参議院通常選挙で「参政党」がそれぞれ国政政党になりました。今回の選挙では新たな政治団体として「無所属連合」「チームみらい」「日本誠真会」「日本改革党」「再生の道」「NHK党(政党要件を途中で失った)」が国政政党ではない政治団体として比例代表に立候補しています。なお政党は原則届出順に掲載しています。
参議院選挙2025 注目ポイント1
国政政党ではない政治団体が政党要件を満たし国政政党になるのかどうか。
(無所属連合、チームみらい、日本誠真会、日本改革党、再生の道、NHK党)
また現在国政政党である政党が2%を満たさずに国政政党の要件を失うかどうか。
(特に現有議席が少ない社会民主党など)
有名人の出馬が多い
参議院選挙は特に有名人の出馬が多いと言われています。これは先述の非拘束名簿式により、個人名での投票が認められていることが関係しているとされます。仮におべん党から「有名アスリートのAさん」が出馬したとします。AさんのファンやAさんを知っている人がその人に投票する可能性が高いと思われます。するとAさんの当選確率が上がると同時に、おべん党への票も加算される仕組みになっているのです。有名人が出馬すれば政党の票を積み増しできるために、有名人出馬が多いと言われているのです。
比例代表の投票台には、2025年通常選挙においては172人の候補者の名前と16の政党の名前がずらりと並んでいるので、知っている名前はより際立って見えるという側面もあると思います。
またアスリートやタレントといった有名人のみならず、支持母体の組織内候補が比例代表に出馬する事例も多いです。自由民主党へは日本医師会やJAグループといった団体から、立憲民主党へは日本教職員組合(日教組)や自治労などの労働組合、国民民主党へは自動車総連や電力総連などの労働組合からそれぞれ組織内候補が出馬しているとされます。いわゆる組織票に直結すると考えられる部分でもあります。
参議院選挙2025 注目ポイント2
自民・立憲・国民から出馬している組織内候補が比例代表の個人名でどれくらい得票するのか。特に前回も出馬した組織内候補の得票がどれくらい増減するのか。
参議院選挙2025 注目ポイント3
比例代表で出馬している著名人がどれくらいの得票を得るのか。例としてはマネーの虎などで知られる南原竜樹氏(維新)、弁護士の北村晴男氏(保守)、元格闘家の須藤元気氏(国民)、タレントのラサール石井氏(社民)、元アスリートの橋本聖子氏(自民)など。
参議院は全国比例である
参議院選挙は全国を1の選挙区とした比例代表で、政党の得票数をもとにドント式という計算方式によって議席を配分します。定数が50議席なので、およそ2%を得票すれば1議席を得ることができます。対して衆議院選挙は比例区の定数が176議席と、3倍もあるにもかかわらず、当選に必要な最低得票率は最小でも約3.6%、最大約17%となっています。これは衆議院の比例代表選挙が11のブロックに分かれていることが原因であり、1ブロックあたりの定数が最大28、最小6となっているのです。6番までしか当選しない衆議院と、50番まで当選する参議院という対比ができます。
得票率を切り口として観察するとこのようになるのですが、当選に必要な絶対票数はブロック制の方が少なくなるほか、日本維新の会などの支持者分布に地域的な偏りがある政党にとってはブロック制の方が議席を取りやすいといった側面もあります。
2025年参議院議員通常選挙 個人的注目ポイント4~12
ここからは2025年の参議院選挙で上で紹介した以外で、個人的に注目しているポイントをご紹介します。
参議院選挙2025 注目ポイント4
自由民主党と公明党を足した与党の議席数が、非改選を含めて過半数に達するかどうか。今回の選挙で50議席を獲得すれば半数を確保できることになっています。衆議院で半数を下回っているため、参議院でも下回った場合、法案を通す難易度が上がります。これまで、前の与党が参議院で大敗し政権運営に行き詰まったあとに行われる衆議院選挙で政権交代が起こっていることから、今回の結果が向こう数年の政治情勢に影響する可能性があります。
参議院選挙2025 注目ポイント5
東京都議会議員選挙で議席数を伸ばした国民民主党、参政党などがどれくらい議席を獲得するかどうか。特にインターネット上で支持が広まっていると言われており、その影響力拡大にも注目したいと思います。また一方、ワンイシュー味の強いアピールを重視している党も多いように感じるので、国民がどれくらい公約を見て投票しているのかにも注目したいです。
参議院選挙2025 注目ポイント6
日本維新の会を離党した議員が別の党から立候補している事例が数件あります。足立康史氏(国民)、鈴木宗男氏(自民)、梅村みずほ氏(参政)など。いずれも維新で処分を受けて離党した人ですが、他党での立候補となっており、当落を含めて注目したいと思います。なお日本維新の会の改選前勢力が5議席であると報道されていますが、2019年選挙で当選した人数は本来10人で、衆議院選挙や知事選挙出馬、離党により減っています。今回の選挙での勢力分析においては5人という数字ではなく、この10人という数字を参考にしたいと考えています。
参議院選挙2025 注目ポイント7
東京選挙区は、東京都知事選に出馬するために蓮舫氏が自動失職した影響で、今回の選挙では通常の6議席に加え、補欠の1議席を加えた7人が当選します。ただし7位の候補者の任期は蓮舫氏の任期を引き継ぐため3年間となります。この定数7を巡って32人が立候補しています。自民、立憲、国民からそれぞれ2人ずつ立候補しており、共倒れや票の大きな偏りが発生するかなどに注目したいです。またその他の政党からも多くの候補者が出馬しており、新興勢力が票を獲得するのか、現職が当選できるのかといった点にも注目しています。
参議院選挙2025 注目ポイント8
大阪選挙区は4議席を争います。前3回の選挙は自民、公明、維新2人で固定でしたが、今回の情勢調査では参政党・国民民主党などを交えた接戦となっているようです。大阪は公明党が強い地域であると言われていますが、前回の衆議院選挙で公明党が4小選挙区全てで議席を失ったこともあり、その勢力変化も注目ポイントです。また、元維新の梅村氏が参政党候補の応援に回っていることも混戦の原因となっているようです。
参議院選挙2025 注目ポイント9
和歌山選挙区は1人区となっていますが、保守分裂選挙となっています。元自民党幹事長を父にもつ二階氏が自民党の公認を勝ち取りましたが、自民党の公認に外れた望月氏が無所属で出馬しました。かつて和歌山選出の参議院議員で、前の衆議院選挙で二階氏に勝利した自民党の世耕氏が望月氏を応援し、自民党本部が二階氏を応援するという展開となっており、1人区で自民vs自民が観察できる状態となっています。
参議院選挙2025 注目ポイント10
32ある1人区(1人のみ選出される選挙区)は、一般的に与野党のどちらかが議席を得ることになり、合計数は選挙全体の結果を大きく左右します。今回の選挙では接戦となっている選挙区が多く、特に自民党が強いとされる西日本でも多くが接戦に持ち込まれているという情勢調査が多いです。
参議院選挙2025 注目ポイント11
兵庫選挙区は定数が3回前に2から3に増えました。これまで3回にわたって自民、公明、維新の3党が議席を獲得していましたが、今回は情勢が全く異なっています。元明石市長の泉房穂氏が立憲民主党推薦の無所属で出馬しており、情勢調査では優勢とされています。そして残り2議席を、自民、維新、N党、国民、公明、参政の6人が激しく競り合っているという報道があります。情勢によってはかなり意外性のある当選者が並ぶ可能性があり、注目しています。
参議院選挙2025 注目ポイント12
今回の選挙はインターネット上で注目されていることなどもあり、投票率がどれくらい増えるのか注目したいです。またアメリカ合衆国の大統領が選挙期間にも関税交渉をおこなってきている点も踏まえ、それらの選挙への影響も興味深いです。
いかがでしたでしょうか。参議院選挙の特徴や今回の選挙の注目ポイントと注目選挙区を紹介してきました。選挙はこのような複雑なルールと外部環境の中で実施されているのです。誰が当選するのかわからない選挙区は特にゲームのようなワクワク感があります。ぜひ選挙に参加し、20日の20時からの開票特番を見ながら、スポーツの試合を観戦するような気持ちで注目選挙区の当落を観察してみましょう!ありがとうございました。