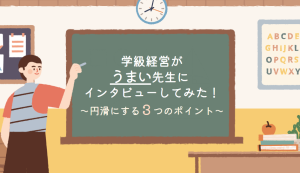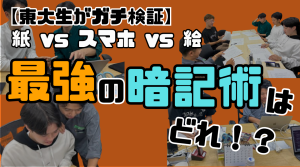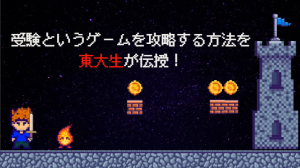みなさんの学生時代、「面白い先生」はいましたか?また、その先生はどんなところが面白かったのでしょうか。
教員として働くのなら、児童生徒に「面白い先生」「すてきな先生」と思ってもらいたいですよね。そこで、今回は面白い先生になるために必要な要素を、東大教育学部生の碓氷明日香が抽出してみたいと思います!
面白い先生とは?
児童生徒から「面白い先生」と思われる先生は、どのような先生なのでしょうか。どんなところに対して「面白い」と言われているのでしょう?ここでは2つに分けて考えてみます。
人柄が面白い
まず、「人柄が面白い」場合に注目してみましょう。その言動やキャラクター自体に魅力があり、授業関係なく、会話をしているときに楽しませてくれたり、時に奇抜な行動を取って児童生徒を笑わせてくれたりする、そんな先生が面白いと言われるのです。
ユーモアのセンスにあふれていたり、話し方やリアクションが個性的だったりと、まるで「学校のエンターテイナー」のような存在。普段は冗談ばかり言っているのに、いざという時には誰よりも真剣に生徒と向き合ってくれる。その温かいギャップに惹きつけられ、生徒から慕われる先生は、どこの学校にもいますよね。生徒との距離感が絶妙な点が、人柄が面白い先生の魅力です。
授業が面白い
一方で、「授業が面白い」ことで「面白い先生」と人気を勝ち取る先生もいるようです。そして、「授業が面白い先生」とは、単に笑わせてくれるというよりも、「分かりやすく、興味が湧く」授業を展開し、生徒の学習意欲を高めてくれる先生のことです。難しい内容でも、身近な例を使ったり、テンポよく話を進めたりして、生徒の集中力を途切れさせません。
雑学や時事ネタを絡めて、飽きさせない工夫をする、教科書に留まらない「リアル」を見せる……。授業の細かいところで生徒の様子を見て、臨機応変に話す内容を変えることで、眠くならない面白い授業ができるのです。
カルぺ・ディエムの中の人に聞いてみた!あなたが出会った「面白い先生」は?
とはいえ、実例がないとイメージしづらいでしょう。そこで、カルぺ・ディエムの中の人に実際に出会ったことのある「面白い先生」について聞いてみました。
共通していたことは、人柄も面白かったはずなのに、印象的なのが授業のシーンであるため、その面白さの言語化が難しいということでした。きっと人柄も授業も両方とも面白かったのでしょうね。
Kさん
高校の現代社会の先生が面白かったです。授業では、教科書はほとんど使わず、社会の価値観やルールの曖昧さについて議論をしたり、大学での学問の自由について語ってくれたり、とにかくテキストに留まらない社会の実情を見せてくれました。人柄も授業も独特なのですが、単に奇抜なだけではなく、生徒の将来のことを考え、自律的に考える仕掛けをたくさん用意してくれた先生でした。
Yさん
まず、中高の数学の先生が印象に残っています。「関数というのは、上から数字(X)を入れた時に、下に数字(Y)を落としてくれる箱のこと。このYを落とすのが大事で、Yの中身はなんでも良く、一見Xに関係のないものでもいい」と説明された時、電撃が走ったような衝撃を受けました。授業の説明がわかりやすいだけでなく、生徒のことを真剣に考えて普通の先生ではしないような行動を取ってくれる、親身な先生でした。
また、現代文の先生も面白かったです。「センス」や「ごまかし」で片付けず、論理的に全てを説明してくれたことが、とても印象に残っています。
私が面白いと思う先生は、自分の科目のことが好きな人が多いような気がします。そしてみんな、子どもに混ざって全力で楽しめるような子ども心の持ち主でした。
Tさん
高3の時の化学の先生が面白かったです。無機化学の授業の際、教科書に載っている実験を全て実演してくれました。そのおかげで各物質の色や反応式が定着したのだと思います。また、実験の時に度々ふざけたリアクションを示すため、それが面白く、生徒人気が高かったです。一方で、受験直前の二次対策授業はメリハリをつけて真面目に授業をしてくれました。
Uさん
高校の化学の先生がとても印象的です。授業中、生徒が寝かけているとその人の席までダッシュで突撃し、問題に答えさせていました。これだけ書くと嫌な先生のようですが、全くそんなことはなく、とても陽気で、起こされた生徒も笑いながら答えることがほとんど。おかげで、化学の授業は楽しみながら受けることができました。
また、生徒のことをよく見ている先生だったような気がします。私が高2から高3に進級するタイミングで離任されたのですが、離任式の時挨拶に伺ったところ、「君は東大、受かりますよ」と声をかけてくださり、あの先生の言葉を実現したい、と非常に燃えました。きっと私の性格を踏まえてそう言ってくださったのだと思います。
面白い先生になるために
では、面白い先生になるためには、どんなポイントを意識すればいいのでしょうか。ここでは、中の人から集めた「面白い先生」の要素を抽出して、3つ挙げていきます。
生徒と同じ目線で学校生活を楽しむ
まず、「生徒と同じ目線で学校生活を楽しむ」こと。一緒になって楽しんでくれる先生は、児童生徒からしてみれば、話しかけやすいですし、もっと話したくなる相手でしょう。
教師は職業ですし、給料をもらってやる仕事ではありますが、そう考えてしまうと学校生活を楽しむ視点は失われてしまうのではないでしょうか。職員室に生徒がやってきた時、仕事モードで対応していませんか?そういう時も授業と同じテンションで笑顔を向けてあげる。それだけで、生徒は安心し、すてきな先生だと思ってくれるものです。仕事だからと割り切りすぎず、生徒の側に立って楽しむ、騒ぐ時は一緒になって全力で騒ぐ。それこそが、教師という仕事の本当のやりがいであるはずです。
生徒に親身に寄り添う
2つ目は「生徒に親身に寄り添う」こと。「生徒」と一括りにしてしまうとわからなくなってしまいがちですが、ひとりひとりは性格も趣味嗜好(しこう)も全く異なる人間です。そのそれぞれに寄り添うこと。気遣いを感じさせないようにさらっと気遣うこと。生徒の相談に真剣に悩むこと。そうやってひとりひとりに親身に寄り添うことで、魅力的な先生として映るのです。ただ「ジョークが面白い」だけでは、対人関係は築けませんからね。
授業の質を保ったまま、面白いものに
人柄は個人に備わっている性格なのですから、簡単には変えられないかもしれません。ですが、「授業」は変えられます。上述の通り、多くの人は印象的な授業を卒業後も覚えているものです。
ギャグを連発することで笑いを取ろうとするのではなく、授業の質を保ったまま、興味深いと生徒に思わせることが大切です。なぜ自分はその科目が好きなのか、それを教えようと思ったのか。原点に立ち返って考えてみるとヒントが見つかるかもしれません。
まとめ
生徒から見た「面白い先生」の要素を抽出してみましたが、いかがでしたでしょうか。面白い先生と思ってもらうためには、生徒との会話、授業などのさまざまなタイミングで工夫が必要なのです。全てを実現するのは大変なことでしょう。ですが、卒業後も生徒の心に残り続ける先生でありたいという思いは無視できないはずです。明日から、少しずつでも実践に取り入れてみませんか?
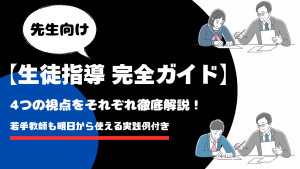

公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。