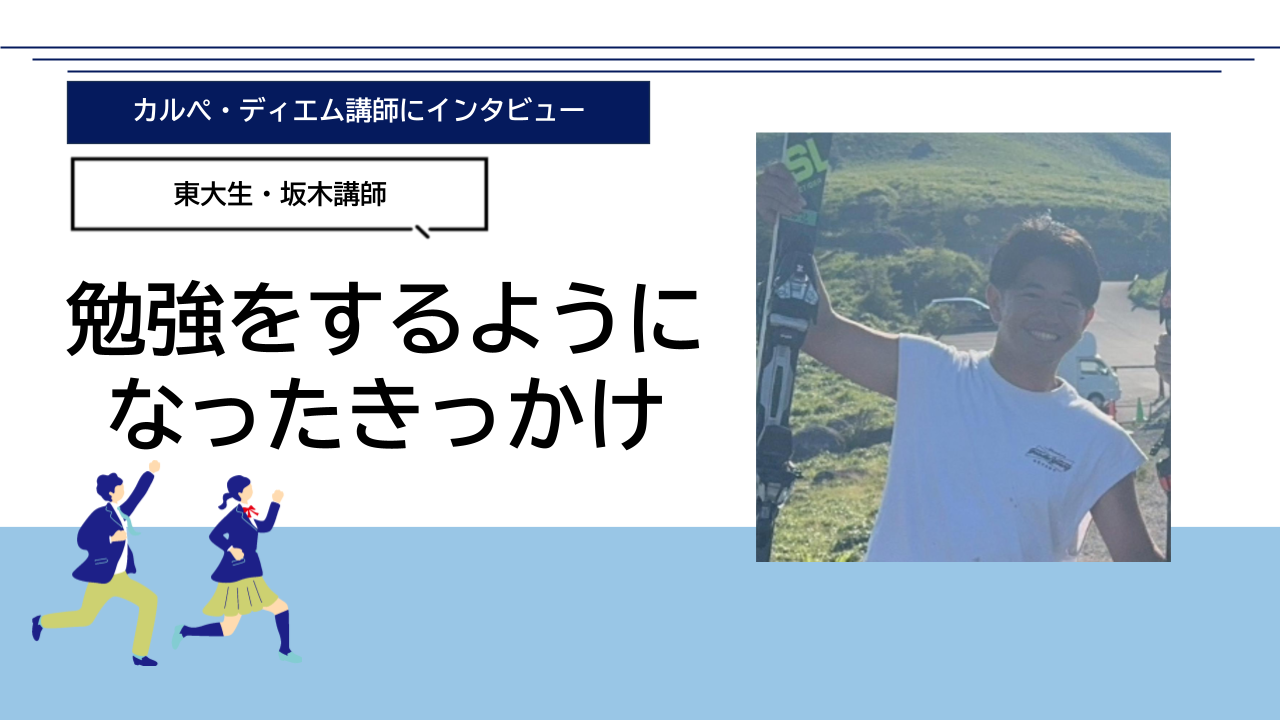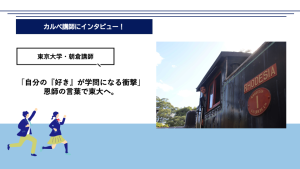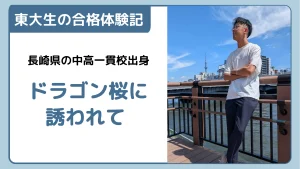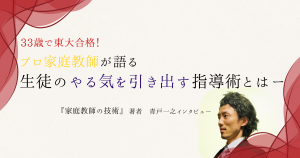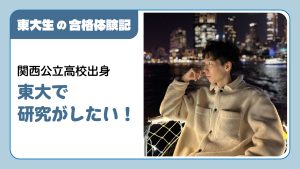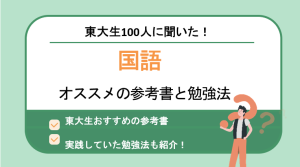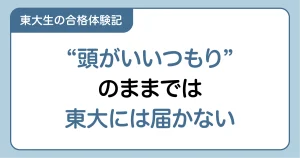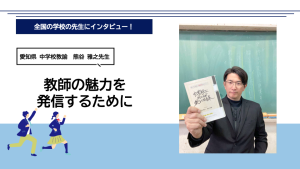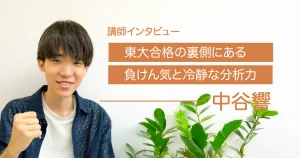なぜ東大を志望したのか
私は、小さいころから宇宙の仕組みと海の生物に興味がありました。両親に買ってもらった図鑑を熱心に読んでいたからかもしれません。ただ、どちらの分野に絞るべきか、どうしても決めきれませんでした。これとは別に、大学の偏差値帯については、漠然と「どうせ大学を目指すなら、トップでしょ!」と思っていました。大学のトップといえば、やはり偏差値一覧表の一番上にある東京大学が浮かぶ。東大には、「進学振り分け」といって、三年次から志望学部・志望学科に進学する仕組みがあります。逆を言えば、最初の二年間は、色々なことを勉強して、志望学部を選べるということでもある。迷っている自分に最適だとわかれば、なおさら東大に行くしかありませんよね。しかし、なかなか勉強に精が出ない。「どうしようかなぁ」なんて考えながら受けた高1のある模試で共通テスト化学が30点しか取れませんでした。東大志望なのに、共テの化学すら3割って……なかなかまずいじゃないですか。ここから本格的に火が付きました。
高2の冬・春休みと勉強を重ねた結果、幸いにも成績が急上昇。それをきっかけに、できることが増えていくことの楽しさに気づき、勉強にのめりこむようになりました。
なぜ勉強が楽しいと思えるようになったのか
私は中学校の時から学年の最下位争いの常連でした。仲の良かった友人と「勉強はつまらない」といいながらずっと勉強を避けてきました。しかし、その友人が中学3年生のある日、突然勉強をするようになったんです。休み時間に単語帳を開いたり、授業後に先生に質問をしにいくようになったり。私はそんな彼を見ながらも、「そんなことで成績が伸びるわけがない」と思っていました。しかしほんの1ヶ月で彼と私の学力差は大きく開いていたのです。あんなに勉強が嫌いだといっていた彼に、クラスのみんなが質問にいくようになったり。この出来事をきっかけに自分も「何かを一生懸命やってみたい」と思うようになりました。そこで最初に選んだのが「物理」でした。最初は物理基礎の公式もままなりませんでしたが、やっていくにつれて意外に慣れてくるものです。一番苦手だった物理は、いつしか得意科目になっていました。
私はこのように、中学3年生以降だんだん勉強をするようになってきましたが、高校1年生くらいまで、「周りがこれくらい勉強しているから自分もやらなければ」という動機が中心でした。物理以外の科目の勉強もやるようになったのは、クラスの雰囲気がきっかけであったことは間違いない。しかし、このような受動的な動機による勉強は自分で考えるという観点が抜けがちで、なにしろ楽しくありませんでした。また周りと同じペースで成長するので、偏差値はほとんど上がりません。本来大切なのは、努力の目的を明確にすることだったと、今になって気づかされます。
早めに始めた物理は高1くらいには自分の中での得意科目になっていました。仲間から物理に関する質問をされ、その対応をすることもしばしば。しかし自分が得意だと思っていた科目・分野がいざとなるとうまく説明できないという事態が頻発しました。論述問題が多く問われる東大を目指す人にとって、言語化ができないのはかなり痛手ですし、なにより「知っているつもり」になっていたことが悔しかった。そこで「言語化ができるようになる」という自分なりの目的を立て、疑問に思ったところをふかぼってみたりノートにまとめてみたりしました。すると仲間に教えるのも得意になり、かつ成績もよくなっていきました。できるようになるというのは楽しいことです。物理ができるようになれば、その楽しみは他の教科へも波及していき、受験勉強全体へのやる気が向上してきました。
試行錯誤と根気
もちろん何事もうまく行ったわけではありません。自分なりに何十パターンも勉強法を試行錯誤しながら、一つ一つ壁を乗り越えてきました。そして乗り越えるごとに楽しみを感じる好循環に入ることができました。
例えばスケジュール。講義で見ていると、やることリストをつくる人や、分刻みで予定を立てる人などいろいろいます。私もいろいろなものを試しましたが、自分にとっては休憩も含めて分刻みで予定を立てる方が向いていたようです。もちろん予定通り進むことばかりではありませんが、うまく進んだときの喜びは大きいです。
勉強をする上で、近道はありません。何よりも先に基礎を作らなければなりません。私は今でこそ物理が得意科目ではありますが、もともと苦手科目でした。苦手を克服するために基礎問題集はそれぞれ5周くらいしました。問題を解く際は時間を測り、目標時間に対してどれくらいかかったのかということを意識していました。試験の場というのを常に念頭に勉強していましたね。5周もすると、思考の型が身につくようになってきました。
共通テスト後に1週間寝込んだ!
私の受験の日、とうとう共通テストです。準備は万全だと思っていました。ところが大事件が。2日目の数学Aで大問1から全然うまくいかずに、同じ問題で立ち往生。そんな間にも時間は過ぎていき、焦りもあり結局全ての問題を解ききれずに、点数は7割ほどに。数学では必ず9割以上、目標は満点をとることだった自分にとって大打撃でした。このミスを何処かで取り返さなきゃ、と焦ってしまい残る数2Bでも本調子を出せずに終了。さて、全てが終わり帰宅後に自己採点をするとなんと模試より遥か低い8割ほどの得点率。過去の東大の合格最低点(足切り)の推移を見るが、自分の点数で足切りを突破しているのは掲載年度のうち20%ほど。どうするかとても悩みました。元々漠然と「宇宙をやりたい」と思い理科1類を志望していましたが、このまま挑戦して足切りを突破できなかったらどうしよう、と悩む日々。学校や塾の先生、親にも相談しながら毎日苦しんでいました。「どうしてあの問題を解けなかったのか」「もう一度チャンスがあればやり直したい。」そんな思いがありました。共通テストが終わってから、東大の出願締切まで時間があったので最後の最後まで悩み、土俵に立てなかったら意味がないと思い理科2類に出願することに。(点数開示の後、自分の点数で足切りを喰らうことはないと判明しました)最後の後押しは母親の「私は受験はあまりよくわからないけど、君ならどこでもやっていけるよ。自分を信じて。悩んでる時間は勿体無い」という言葉でした。
そんなこんなで1週間ほど寝込み、勉強が手につきませんでした。
しかし、決意を固めてからふっきれて、「やってやろう。難しかったのはみんな同じ。こんなに頑張ってきたのだから。」と。
そして2次試験までは同じ過ちは繰り返さないように、何通りかの得点パターンを用意。どこでしくじる可能性があるのか、逆にどこで絶対取りたいのか、などを考えながら勉強に明け暮れました。
そして、2次試験で最後の科目である英語を解いた際に、手応えが途中までなく「これでは落ちてしまうかも」という不安が脳内を巡りました。しかし、自分が今までにやってきたこと、今できることを考え、「やるしかない」という気持ちに。恩師の「最後の1秒まで諦めるな。そこで得点が変わってくる」という言葉が脳裏を駆け巡り、鉛筆を動かし続けました。
その甲斐もあり合格を果たしました。今思うと、あの英語で諦めていたら落ちていたかもしれません。
共通テストで大きく挫折した見返りに、頑張り続ける決心という強い武器を手に入れました。
皆さんには同じ轍を踏んでほしくないので、是非とも次のことを意識してください。本番は練習どおりにはいかないことなんてしょっちゅうあります。そこで落ち込まないために、何個も自分の中で得点パターンを考えておくように。そして、手応えがなくどれだけ自信が消え失せようと、試合は終わっていません。最後の1分、1秒まで鉛筆を動かし続けてください!
受験生にかける言葉
私は「これが正しい勉強法である」というつもりはありません。人それぞれに最適な勉強法ややり方があるのです。
しかし、全員に共通して言えることは、努力するきっかけは身の回りにいくらでもあり、いつでも自分を変えられるということです。私の場合はそれは突然勉強を始めたあの友人でした。大切なのは、挑戦してみよう、という気持ちなのです。
学生のみなさんには、何事も前のめりに挑戦してほしいと思っています。そして私は学生のみなさんとの出会いの中で、そのきっかけを提供したいと思っています。