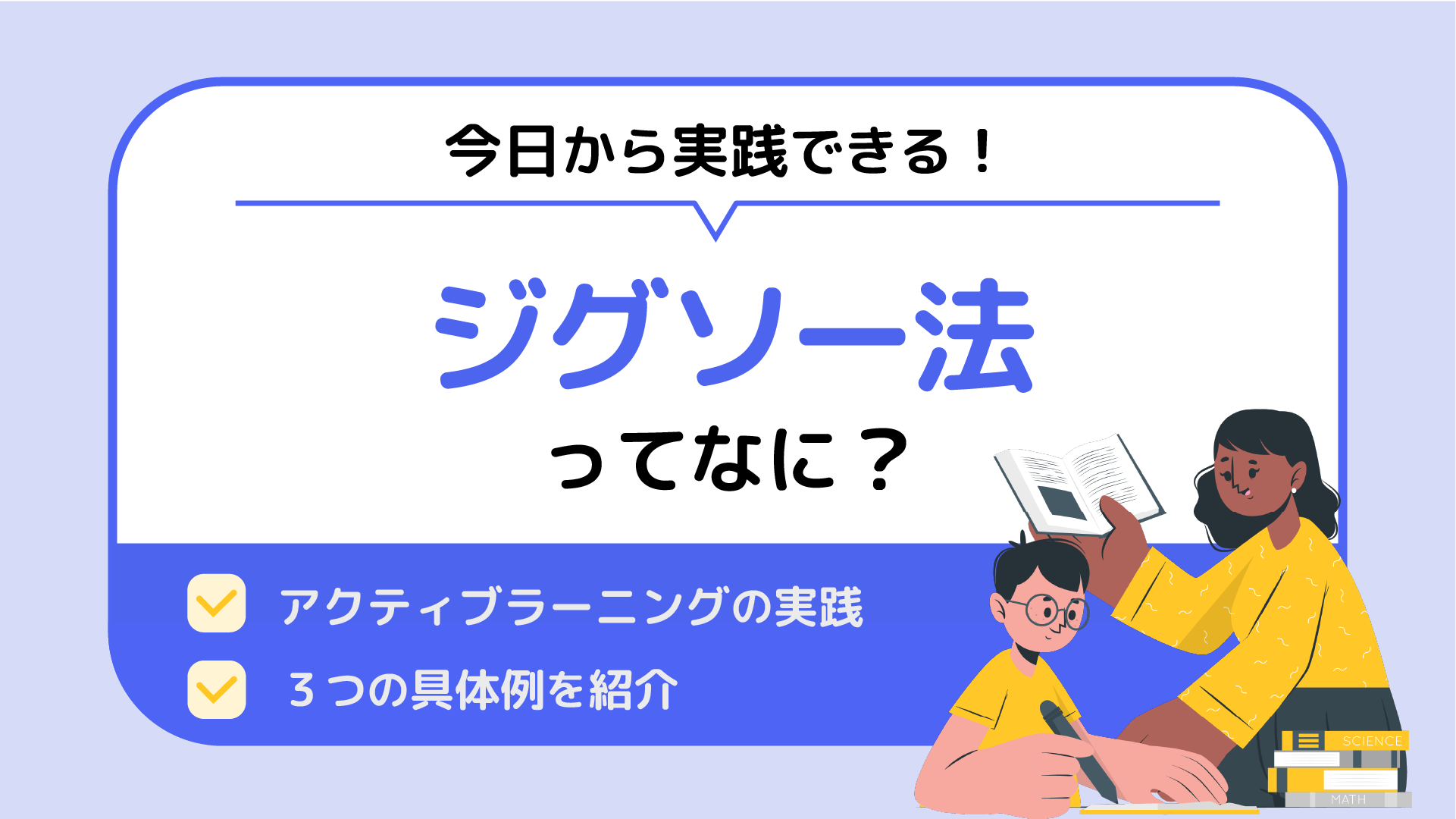現在、多くの学校現場で注目され、実践が進められているのが、文部科学省が提唱する「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指した授業づくりです。教育現場に携わる先生方であれば、一度は耳にしたことがある言葉ではないでしょうか。
今回は、そんな教育界のホットワード「主体的・対話的で深い学び」を後押しする授業づくりの工夫 『ジグソー法』について、詳しく解説していきます!
アクティブラーニングの一つであるジグソー法とは
ジグソー法とは、学習全体の内容を小さく分けて、それぞれの生徒が「その分野の専門家」となり、仲間内でそれぞれの生徒が持ち寄った内容を教え合うことでグループで全体の内容を理解する学習手法のことです。
ジグソー法の名前はジグソーパズルの「ジグソー」からきており、その名の通り、それぞれの生徒のパズル知識のピースを組み合わせて完成させるイメージになっています。この方法は、生徒一人一人にグループの仲間に教える分野が任されているので、生徒は必然的に「自分がいなければグループの学習が成立しない」という状況になります。また、生徒たちが教えあっていく中で自然と会話が生まれてきます。
まさにジグソー法は、全国の学校で実践が進められている“主体的・対話的で深い学び”を体現しているといえます。

なぜジグソー法が効果的なのか?
ヴィゴツキ―の教育心理学の理論では発達は社会や文化、他者との相互作用によって進むと言われています。
また、自力で問題解決を達成できることと他者に援助により問題解決を達成できる2つの水準のずれの範囲を「発達の最近接領域」といい、これらによってはじめて発達潜在的可能性が捉えられると指摘されています。ジグソー法が教育に効果的だとされているのにもちゃんと論理的な裏付けがあるんですね。
ジグソー法の具体的な活用例について
それでは、実際にジグソー法がどのように小学校や中学校の授業の中で活用されているのか、いくつかの具体例をご紹介していきます!
実践例①福岡県飯塚市立飯塚小学校(小学6年生 社会科)
活動内容:「東京オリンピックから戦後の日本を考える」
小学6年生の社会科で知識構成型のジグソー法が用いられた授業が行われました。
課題を提示された後、児童は同じ資料やテーマを担当する生徒が集まって深く学び合う小グループである「エキスパートグループ」で同じ資料を読み合って、理解を深めます。その後、「ジグソー法」で違う資料を読んだ人が一人ずついる班に組み替えてエキスパート活動で分かってきた内容を班のメンバーに向けて説明していきます。そして「クロストーク」として各班の考えをクラス間で共有していきます。
授業の流れとしては同じテーマを理解するエキスパートグループ→異なるテーマを生徒間で共有するジグソー法→各班のまとめを発表するクロストークとなっています。
(出典:先生のための教育時点EDUPEDIA, 「東京オリンピックから戦後の日本を考える」社会科でジグソー学習, https://edupedia.jp/archives/22540)
実践例②熊本県立八代市立東陽中学校(中学1年生 社会科)
活動内容:ICT教育×ジグソー法 「モンゴル襲来後の社会変化」
中学1年生の社会科でICTとジグソー法が併用されて用いられました。
生徒はベネッセの「eライブラリ」で前回までの授業内容を確認した後、ジグソー法で班分けされ、それぞれのテーマに沿って調べたことを協働ソフトにまとめて鎌倉幕府の崩壊要因を分析しました。
前回の授業内容を振り返ってからスタートすることでつまずきをなくしてから授業に入ることができ、またタブレット端末を活用することで、資料へのアクセスや意見の共有が効率化され、協働的で深い学びが実現されています。
(出典:ベネッセ教育情報サイト, 生徒が主体的の授業と学びの見取り~知識構成型ジグソー法にeライブラリを活用~, https://www.education.jp/introduction_list/detail/76)
実践例③台中日本人学校(小学6年生 算数)
海外の日本人学校でもジグソー法は活用されています。台中日本人学校(台湾)では、小学6年の算数「全体を求める問題」において、タブレット端末とロイロノート・スクールを活用しながら、ジグソー形式で授業が行われました。
まず、児童は学習内容を把握してから個人で問題に取り組む時間を持ちます。その後、児童はそれぞれ資料A・B・Cを受け取り、問題を分析し、エキスパートグループで話し合った後、元の班に戻ってジグソー法で説明します。問題は資料A・B・Cを組み合わせて解く構造になっており、グループの児童全員が責任をもって主体的に取り組まなければいけない構造になっています。最終的には、クロストークで他グループとも学びを共有する時間を設け、解決方法の違いや共通点を確認しました。
(出典:ロイロノート・スクール, 『台中日本人学校 算数 全体を求めて』, https://n.loilo.tv/ja/LNScase156)
上記の例のように、総合的な学習の時間以外の普段の授業でもジグソー法は使用することができます。特に3つ目の台中日本人学校の例は、調べ学習ではない問題解決型の算数の授業でジグソー法が用いられています。また資料A・B・Cを組み合わせないと解けないようになっていて、児童は「自分は必要な存在だ」と自覚してそれぞれ割り当てられた資料をしっかり理解しグループ活動に取り組んで、責任感や主体性を持つことができます。
ジグソー法を取り入れるときのコツ
次に、ジグソー法を上手に取り入れるコツをご紹介します。
テーマはバランスよく分ける
担当する内容に偏りがあったり、量が多すぎたり少なすぎたりすると、担当者の負担が変わってしまいます。そうすると生徒間でグループへの貢献度に差が出てきてしまったり、生徒間で負担が違うことで対等ではなくなり、生徒のモチベーションが下がったりしてしまいます。すべての生徒が対等に自信をもってグループ活動に取り組むことができるように、テーマの量はグループ間でバランスよく分けていきましょう。
「みんながちゃんと役割を持てて、教えるのに十分な量」を意識して分けるのが成功のポイントです。
「説明→質問→補足」の流れを大事にする
ジグソー法で注意することは、ただ調べてきた分野の説明会になってしまわないことです。理想的なのは、聞いている人が質問したり意見を出したりと〝対話が活発になること〟です。
ただの発表会になってしまわないよう、質問タイムを設けたり、「発表者の話を受けて一言コメントする」などの軽い役割を与えたりすると効果的です。
時間管理を正確に
グループワークは楽しい反面、時間が足りなくなったりダラダラしがち。タイマーを使ったり、教員やファシリテーターが声かけしたりして、ペースをしっかり管理していきましょう。
最後は必ず振り返りを入れる
教え合いが終わったら、「どんなことに気づいたか」「どこが難しかったか」など、振り返りの時間を作るのが効果的。振り返りを書く時間を設けたり、簡単な発表をしたりすると、学びがグッと定着します。
まとめ
いかがでしたか。
「ジグソー法」では生徒の主体性や協調性を育むことができ、まさに〝主体的で協働的な深い学び〝を体現するのにふさわしい授業の手法です。
最近授業が一方通行になってしまっている…、生徒のやる気を感じない…。そんなふうに感じたら生徒に役割を与えてグループ間で話し合いをさせるジグソー法を授業の中に少しでも取り入れてみてください。ジグソー法では生徒が進んで学び、教え合いで理解を深めていくことができます。この記事が先生方のお役に立てれば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。