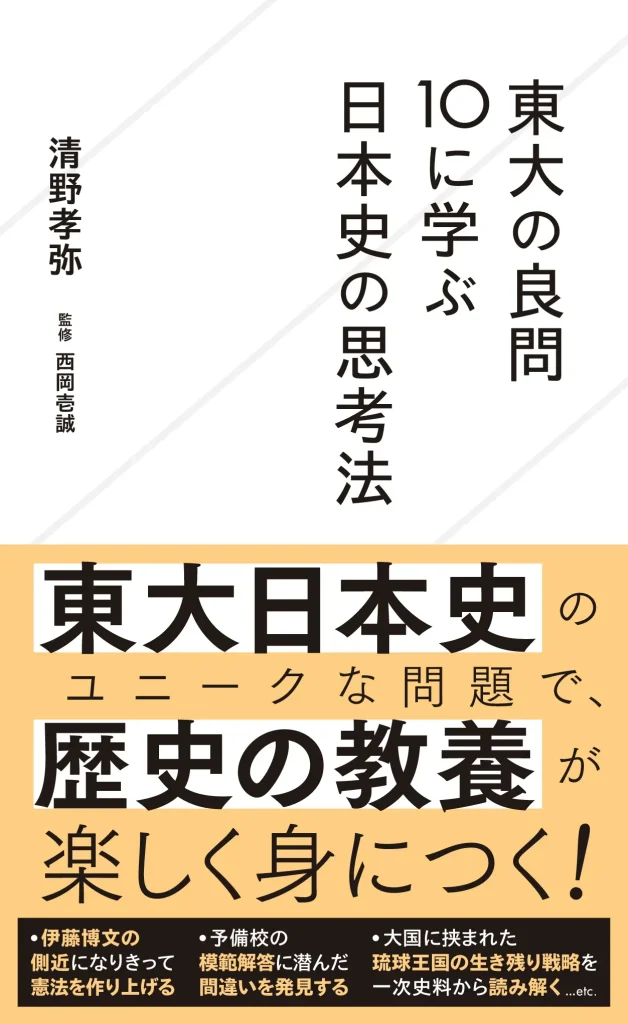おばあちゃん家
英語には、”chosen family”という言葉がある。
最近よく使われるようになったいわゆる新語で、意味の解釈はさまざまだが、血縁関係はないが家族のような心のつながりをもつ人間関係のことをいう。
今回は、私の「chosen おばあちゃん」のお話をしようと思う。
第1話を読んでいればご存じの通り、私は両親の故郷インドからは遠く離れた日本で生まれ育った。おばあちゃんの家にいくには、数十万円を払って数時間飛行機に乗らなければ到底たどり着けない。長期休みにひょいとおばあちゃん家行ってくる、なんてことはとてもできるものではないのである。
実際、私は4歳のとき以来、一度もインドのおばあちゃんの家に行ったことがない。地元の公立学校の忙しさや震災など、さまざま要因が重なって、気づけば最後にインドを訪れたときから20年近くの月日が経ってしまっていた。4歳以来ほとんど会っていないのだから、当然顔も全く思い出せない。悲しいけれど、道端ですれ違っても、きっと互いに気づかずに通り過ぎてしまうだろう。
だから、友達がお盆休みや年末年始が近づくと、「おばあちゃん家行くんだ」と話すのを聞いて、正直少しうらやましかった。自分の知らない幸せな世界に、みんなは休みのたびに行っているのだなと、なんだか1人取り残されたような気持ちになりながら考えていた。私の頭の中で、「おばあちゃん家」は、いわゆるジブリ映画に出てくるのどかな世界として描きあげられていた。
しかし、そんなのどかで幸せな風景は、実は自分のすぐ隣に存在していたのである。私が生まれ育った町は、昔ながらの民家が連なっており、かすかに昭和の名残を残したようなあたたかい近所づき合いが続いている。近所の住人は、高齢な人が多いが、何十年も紡がれてきた人間関係が、町を守っているように感じられるところだった。
そして、私もそんな近所に守られて育った人の1人だ。冬の日、あたり一面が雪に覆われた朝には、互いの家の周りを雪かきし、親戚などからたくさんのお中元をもらった夏は、余った菓子や食べきれない果物を互いに分け合う。そんなことが当たり前の日々だった。
とくに、すぐ隣に住んでいた2人のおばあちゃんは、私にとって特別な存在であった。近所で会うたびに、決まって「あらぁ、大きくなったねぇ。めんこいこと~。」とにこにこと話しかけてくれ、まるで本当の孫のように接してきてくれた。温泉好きのおばあちゃんで、温泉旅行に行った帰りには、必ずおいしいお菓子を家に持ってきてくれたし、小学生のころは、年が明けると小さなかわいい封筒に入ったお年玉をくれることさえもあった。
2人のおばあちゃんとの思い出はたくさんあるが、特に忘れられないのが、高校3年生の夏と大学1年生の夏である。
高校3年生の夏、大学受験に向けて、自分の部屋で受験勉強に没頭していると、コンコンと窓を叩く音が聞こえてきた。ベッドに立って、窓を除き込んでみると、裏のおばあちゃんが手にジュースと桃をいくつか持って立っている。
「これ、家にたくさんあったから、食べて。これ持てる?」
と言ってこちらを見上げながら、果物を抱えた両腕を伸ばしている。
網戸を開けて受け取ると、にこにこしながら、
「勉強してるの?」
と尋ねてきた。
「はい。」
と苦笑いして答えると、
「いつも頑張ってること。ママによろしくね。」
といって、同じ笑顔で手を振って家に戻っていった。
あのとき、部屋から見たピンク色の夏の夕焼け空は、なぜかまだくっきりと脳裏に焼き付いている。受験勉強でくたびれた自分の心身に、それだけおばあちゃんのあたたかみが染みたのだろう。
時が経ち大学生になり、大学1年生の夏休み、久々に地元に戻ってきた。帰省したものの、とくにやることがなく時間を持て余していたので、おしゃべりをしに隣のおばあちゃんの家に遊びにいくことにした。おばあちゃんは、いつものように喜んで居間に迎え入れてくれた。せっかくなので、おばあちゃんの小さい時の話が聞きたいと言うと、あきれたように笑って、冷凍庫から取り出したアイスを私に渡してから、ゆっくりと話し始めた。戦争を生き抜き、子どもを育て、今こうして1人で生きている彼女の口から出る言葉には、なんとも言えない確かさがあった。一通り話し終えると、「80越えて、1人好きに生きている今が、人生の中で一番幸せ。」と言い、いたずらっぽく笑っていた。
2人のおばあちゃんは、私が生まれたときからずっと、なにものにも変えがたいぬくもりを私に与え続けてきてくれた。私は、確かに血縁的なおばあちゃんとは縁がなかったが、決して「おばあちゃん」という存在と縁がなかったわけではない。
世の中には、おばあちゃんに限らず、何らかの事情で血縁的な家族とは縁がなかったり心のつながりが持てなかったりする人が少なからずいる。しかし、自分の人生に欠けていると思っていたその絆は、実はあなたのすぐ隣に、もうすでに存在しているのかもしれない。人との絆に、血筋は関係ないのだ。