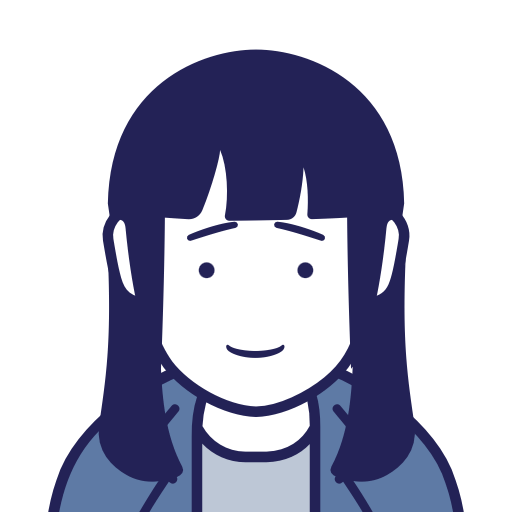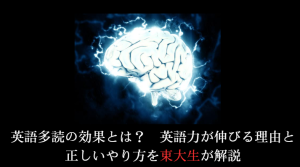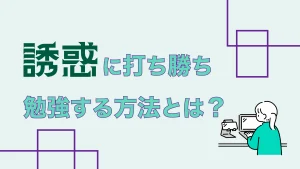みなさんは「授業」と聞いて、どのような景色が思い浮かびますか?きっと多くの方がイメージするのは、40人ほどの生徒が前を向き、教壇で解説する先生の話を聞いている姿だと思います。本記事で紹介する「学び合い」という授業形式は、一般的な授業のイメージとは大きく異なります。どのような授業方法なのか?どんな教育効果があるのか?普段の授業を学び合い形式で実施している、静岡サレジオ高等学校の鈴木庸介先生に教えていただきました!
学び合いとは?
学術的に証明されている
学び合いは、単なるメソッドではなく、学術的に証明された学習理論に基づく教育実践です。そのため、先生自身の感覚でアレンジを加えるのではなく、正しい方法で実践する必要があります。正しく実践すれば、理論通りの結果が出ることが証明されているのです。学び合いの理論は、西川純さんのホームページから学び始めることができます。
理念
みなさんは、先生の授業が理解できずに、置いていかれるような気持ちになって、焦りを感じたことがありませんか?学び合いの根底にある願いは「1人も見捨てない社会の実現」です。この願いのもと、学校観、生徒観、授業観という3つの考え方が軸とされています。
学校観 学校は、多様な人と折り合いをつけて自らの課題を達成する経験を通して、その有効性を実感し、より多くの人が自分の同僚であることを学ぶ場である。
生徒観 子どもたちは有能である。
授業観 教師の仕事は、目標の設定、評価、環境の整備で、教授(子どもたちから見た学習)は子どもたちに任せるべきだ。
この3つの考え方に基づいて教育を実践している学校や先生はまだ少ないように思いますが、学び合いの非常に重要な考え方です。
具体的にどのような授業?授業の進め方
学び合いの授業は次の手順で行なわれます。
1.目標共有
まずはじめに、担当する先生が、その授業の目標を告げる。クラス全員が課題を達成することを目標とする。1人でも達成できていなければ、その日の学びは完成しない。
2.学び合い活動
目標に至る学習活動は生徒に委ねる。誰と相談するかも、席を離れるのも自由。分からないことがあれば、生徒同士で教え合う。先生は教えるのではなく、教室を周りながら、生徒の学習を「みとる」。
3.まとめ
最後に先生が授業の振り返りをする。学習内容自体の復習ではなく、「全員が課題を達成できたか」の確認。
このように、従来の先生が一方的に教える授業ではなく、活動の大部分を生徒に任せます。学び合いは、コミュニケーション力など、学力以外の資質・能力も育成します。最初はもちろん、なかなか動き出さない生徒や話さない生徒もいます。ただ、学び合いを続けていくうちに生徒たちは、「目標達成のためにアウトプットした方が良い」と気づきます。今まで机に座って話を聞くのが常識だった分、気づくのに時間はかかりますが、動いた方が自分にとって「得」だと理解すれば、自然と動けるようになるそうです。
なぜ学び合いをするのか?
なぜ、一斉型の授業に対し、このような学び合いの授業が広がっているのでしょう。
共栄
学び合いの考え方に、自栄と共栄というものがあります。学び合いが目指すのは、自栄ではなく共栄です。今、日本は、世界で戦うために、日本人同士で争うのではなく、力を合わせて立ち向かっていかなければいけないフェーズに入っています。地球規模でも同じことが言えます。だからこそ、日本人さらには世界の人と共存し、共栄というスタイルを目指すのだという考え方が、学び合いの先にはあります。従来の学校教育や受験では、競争的な面が根強いのに対し、学び合いの前提にはこうした背景があるのです。
多様性へのアプローチ
鈴木先生は「(クラスに)40人の生徒がいれば、40通りの学び方がある」と言います。それぞれの生徒が分からないポイントは、同じではありませんよね。学び合いの授業は、生徒同士が分からないところを教え合うので、全ての内容を網羅的に説明しなければいけない一斉型の授業よりも、効率が良いのです。
専門家の言葉は分かりにくい
学び合いの前提に、「専門家の言葉は分かりにくい」という考えがあります。たとえば専門の人が書いた高校教科書と、友達から聞く解説では、友達の方が分かりやすいと思います。自分より圧倒的に知識のある人の話には、知らない言葉がたくさん使われます。生徒同士で教え合うと、自分と同じか少しだけ上のレベルの人から教わることができるので、生徒にとって1番理解しやすい方法なのです。
先生の役割
学び合いの時間、先生たちは何もやっていないかのような誤解をされることがありますが、違います。先生の役割は、生徒の学習活動を見取り、環境をつくることです。生徒の「学び方」を評価して、適切な声かけをします。生徒の有能性を信じ、学習を委ねることも大切です。1人で学ぶ生徒がいる場合は、周りの生徒がサポートするよう促します。
教育効果・メリット
友達に勉強を教えているうちに、自分の頭も整理されたという経験が、みなさんにもあると思います。学び合いは、教えられる側だけでなく、教える側にも、自身の考えを整理して深い理解ができるというメリットがあります。また、学び合いで育んだ協働力は、社会に出てもきっと役に立つことでしょう。一斉型授業に比べて、個別最適な学びが実現できるとも言えます。さらに、学び合いの活動の中で、自分の強みや得意なことの発見も期待できます。
デメリット
ここまで、いいことづくめに思える学び合いですが、デメリットはあるのでしょうか。
まず、生徒にとって、学び合いのスタイルに慣れるまで、時間がかかる場合があります。先生にとっても、従来の授業からの転換に時間と学習が必要です。これは学び合いに限らず、新しいことを始めるときには起こり得ることですよね。
また、集団によって成熟度が異なる場合もあります。学級には特色があるので、活動の雰囲気も異なるそうです。これは、同じ集団でも言えることです。たとえば、クラス替えしたばかりの4月と、約1年を共にした2月では、同じ仲間であっても活動の様子は全く違います。
終わりに
今回は、「学び合い」という教育について解説しました。気になった先生は、ぜひ理論を学び、授業に取り入れてみてはいかがでしょうか。
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。