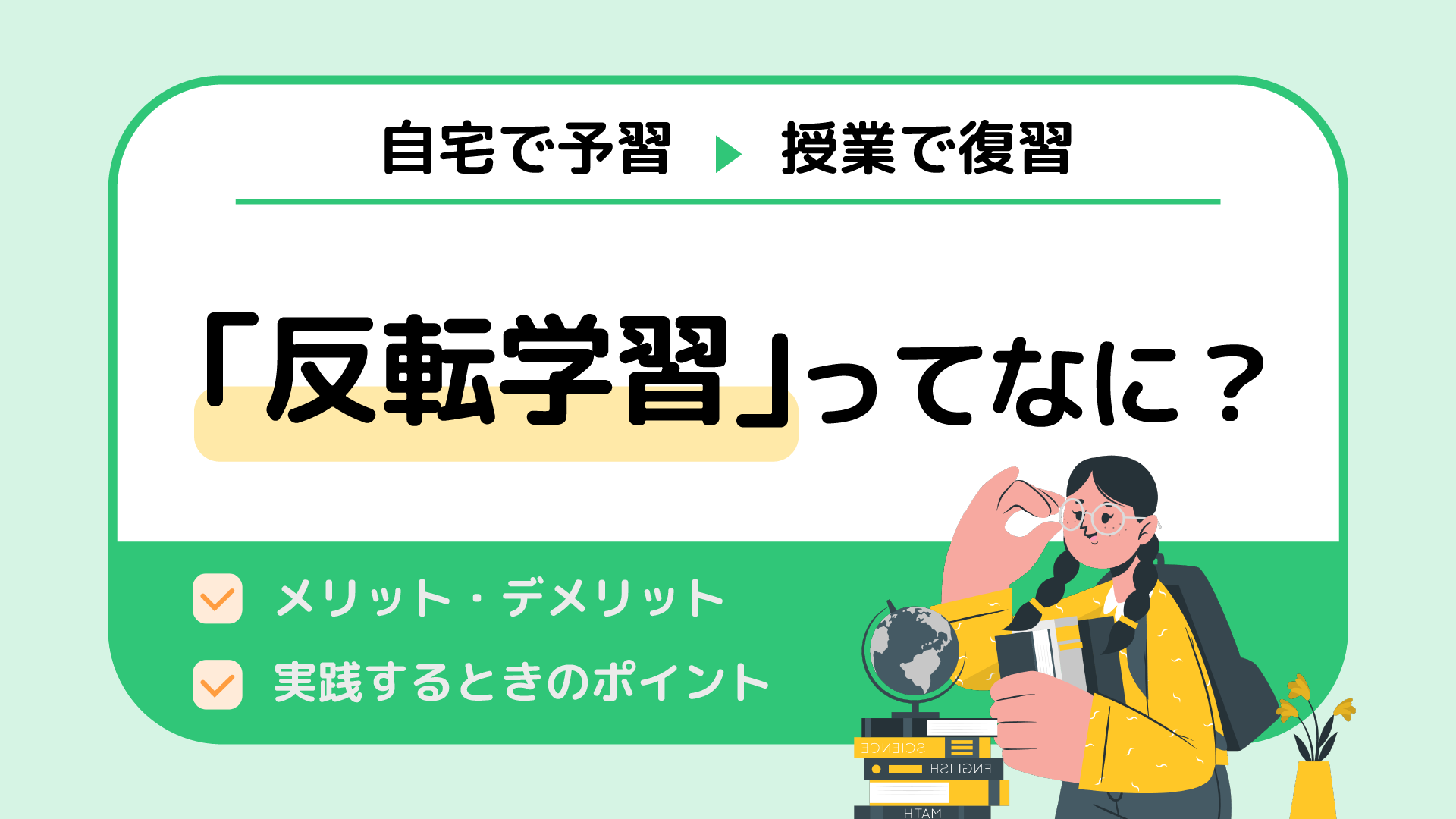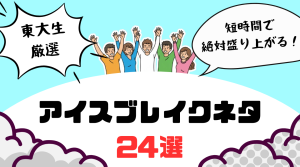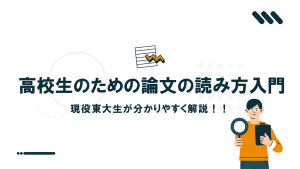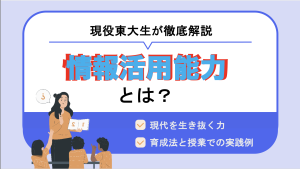「反転学習」もしくは「反転授業」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。一言で説明するならば、自宅で予習し、授業で復習する学習スタイルです。
最近、従来の授業形式とは180度順番を反転させたこの授業が注目されています。
今回は、なぜ反転学習が普及しつつあるのか、その背景とメリットやデメリット、実際の教育現場での導入例などをまとめて、東大教育学部生の碓氷明日香が徹底解説します!
反転学習とは
まず、そもそも反転学習とはどのような学習方法なのでしょうか? 概要と普及の背景を説明します。
反転学習の方法
従来の授業は「授業で学習し、自宅で復習する」という形が主流ですよね。そのため、授業内容は基本的に先生が教壇に立って説明し、生徒はそれをノートに書き写す形式で行われます。
一方で、「反転学習」はその順番をひっくり返して、「自宅で予習し、授業で復習する」学習方法のことです。家庭学習の一環として、学習内容の説明動画を見てもらい、学校の授業で予習の時点ではわからなかったことや疑問点を生徒同士で共有します。つまり、授業の中身はディスカッションやアウトプットが中心であり、これまでの先生が一方的に説明する時間はほとんどありません。
学びのインプットとアウトプットの場を逆転させることから「反転」の名前を付けられているというわけですね。
普及した背景
「反転学習」はもともとアメリカで始まった学習方法です。2000年代にアメリカの研究で反転学習の効果が明らかになり、少しずつ広がり始めました。国内では東京大学が先陣を切って導入し、最近では各地の小中高で取り入れられています。
反転学習の必要性が一気に高まったきっかけが、コロナウイルスのパンデミックです。全国の一斉休校により、オンラインで教育を行わなくてはならなくなりました。そんなコロナ禍でも、感染予防を行いながら学習機会を充実させるために、各地で提案されたのが「反転学習」だったのです。
最近では、GIGAスクール構想などにより、さらなるICT教育の充実が目指されています。これから先、さらに反転学習の重要性が高まることでしょう。
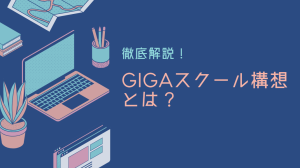
反転学習のメリット
では、反転学習のメリットはどこにあるのでしょうか。ここでは、生徒•先生の双方に関わるメリットを4つ挙げていきます。
個人のペースで学習が可能
まず、予習を生徒個人に任せることになるので、それぞれのペースに合わせた学習が可能です。事前に授業動画を見て予習をする場合は、動画を途中で停止したり、わからないところに戻ったり、何度も繰り返し再生したりできます。教員のリアルタイムの説明だと、どうしても生徒一人ひとりの理解度に合わせて繰り返すのが難しいですが、反転学習だとそれが可能になるのです。
また、学習内容の呑み込みが早い生徒は、動画を倍速で見ることもできます。すでにわかっていることの学習に時間をかける必要がないため、学習の効率化を図ることもできるのです。
最近は、文部科学省の主導で「学習の個別最適化」が求められてきています。反転学習はまさに個別最適な学習のための手法といえるでしょう。
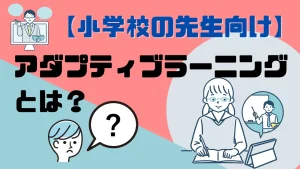
より深い学習になる
次に、予習を踏まえて、授業はディスカッションや質疑応答、アウトプット形式で進めていくので、一方的に説明を聞くだけの受け身の授業形式に比べて、深い学習になります。自分のわからなかったところや疑問に思った部分に焦点を当てて質問し、お互いに学び合えるため、授業内容を効率的に満遍なく理解できるのです。
そして、残った時間はさらにその内容の深掘りに充てることができます。その際、すでにある知識を活用して何について話し合うか、自律的に考える必要が出てくるため、生徒は主体的に授業を受けるようになるでしょう。すなわち、近年重要性が増してきている「アクティブラーニング」にもつながるのです。
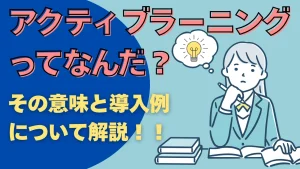
問題解決能力・コミュニケーション能力が身に付く
ディスカッションテーマを自分たちで決めて、それについて話し合い、深掘りするのが反転学習の授業の特徴です。そのため、これからの社会を生き抜くために必要な「問題解決能力」が身につきます。
変動が大きく、予測が難しい社会を生きていく人材を育てるには、自ら問題を発見し、その解決方法を他者と協力しながら見出していくことが必須です。しかし、その力を身につけるのは容易ではありません。授業を通して能力を育てられるのなら、それに越したことはないと思いませんか?
また、自分の考えを他者に伝えたり、他者に配慮をしながらその意見を聞き、理解するコミュニケーション能力も、社会に出た時に必ず求められますよね。ディスカッションの授業が増えれば、この能力もまた、身につけることが可能です。
このように、反転学習を通して、生徒たちがいずれ使うことになるであろうさまざまな力の育成が見込めます。
教員が個人の理解度を把握できる
最後は教員にとってのメリットです。反転学習では、各班のディスカッションを見回って確認すれば、各生徒が何に疑問を抱いて、授業内容をどれくらい理解しているのかが一目瞭然。そのため、個人の習得度に合わせてサポートができます。
従来の授業では、テストをやってみるまで個人の理解度・習得度はわかりづらいですが、反転学習では毎回の授業で誰が積極的に議論に参加できているのか明確なので、的確なフィードバックがしやすいのです。これも個別最適な学習につながります。
反転学習のデメリット
一方、反転学習には注意すべき点も複数あります。ここでは3つのデメリットを挙げていきましょう。
予習の出来に差が出る
まず、反転学習では、予習を個人に任せることになるので、その出来には必ず差が出てしまいます。真面目な生徒はきっちり何度も繰り返し動画を見てくるのに対し、不真面目な生徒は適当に動画を見たり、そもそも何も予習しなかったりするでしょう。しっかり予習に取り組んでも、自力では理解が不十分な生徒もいるかもしれません。
そうなれば、授業のディスカッションで積極的に発言できる生徒とそうでない生徒が出てしまい、理解度の高い生徒だけがさらに理解を深め、浅い理解のまま授業に臨んだ生徒は議論についていくことができなくなってしまいます。結果、理解度に大きな差がつくうえ、不真面目な生徒ややっても理解できなかった生徒はモチベーションを失ってしまう危険もあるのです。
家庭環境による格差が広がる
また、家庭環境による格差が広がる可能性も。オンラインの教材で予習をしてこなければならないとなれば、家庭のインターネット環境が大きく関係してきます。相対的貧困で回線を整備できない家庭の生徒は予習がままならず、授業のディスカッションに主体的に参加することが難しくなるかもしれません。
そして、近年問題視されつつあるいわゆる「ヤングケアラー」も、事前に予習の時間を確保することが難しく、これまで以上に授業についていけない可能性があります。
家庭環境にどこまで配慮すべきか、どのような配慮が可能か、まだまだ議論の余地があります。
教員の負担が増える
そして、教員の負担が増えるというデメリットもあります。反転学習を導入すれば、予習のための教材を準備する必要がありますし、授業の進め方も大きく変わるので、トライアンドエラーを繰り返しながら、より良い方法を模索しなければならないのです。
教員の業務過多が問題視されている現代において、どのようにその負担を減らすのかが課題となります。予習用の動画を外注する、既存の教材を使う、ディスカッションの進め方はすでに成功している反転学習の事例を参考にするなどの方法で、効率的に導入する必要がありそうですね。
教育現場に取り入れる際の3つのポイント
では、教育現場に取り入れる際、どのようなポイントを意識すれば、反転学習の効果を最大限発揮できるのでしょうか?3つのポイントを解説します。
事前にポイントと疑問点をまとめてもらう
予習の段階で大切なのは、生徒一人ひとりに予習を通して理解したことと理解できなかったことを挙げてもらうことです。ただ動画を見るだけでは、主体的に考える癖は身につきません。
内容をきちんと理解するためには、わかったことを自分の言葉でまとめるのが一番効果的。なぜなら、そのためには聞いたことを咀嚼し、要点を抽出して、もう一度言語化する必要があるからです。この流れを通して初めて、深い理解が可能になります。
また、授業のディスカッションで周りの生徒に質問する内容を用意しておけば、授業の進行も楽になります。そのために事前に疑問点をまとめてもらうのです。
授業後にもう一度まとめてもらう
そして、授業が終わったら、今度は授業を通して理解したこと、まだわからないところを再度挙げてもらいます。授業前と授業後を比べてもらうことで、何を学んだか(もしくは何も学べなかったか)、生徒ひとりひとりが考えることになり、毎回のディスカッションの質が高まるのです。
まだわからないところがあるのであれば、そこは教員の出番。授業を終えてもなおわからない部分は、上述の個別のサポートが必要な部分なので、教員が解説してあげましょう。
個別にフィードバックを行う
大切なのは、授業が終わったあと、放置しないこと。ひとりひとりに何を学んだか、まだわからないところはないか分析してもらったら、それに対して教員がフィードバックをすると、反転学習のメリットを最大限引き出すことができます。
ディスカッションのよかった点や改善点を伝え、さらには最終的にわからない点に対して解説をする。ここまでやって初めて、生徒はその単元を完璧に理解することができます。このフィードバックをいかに丁寧に的確に行うかが重要なのです。
反転学習の中高における実践例
ここでは、実際に反転学習を取り入れている学校を紹介します。
兵庫県篠山市立篠山東中学校
兵庫県篠山市立篠山東中学校では、2014年度から全校で反転学習を導入。事前動画は5〜10分程度の短いものを使い、分かったことと分からなかったことを確認してもらいます。授業は最初の5分程度を内容の確認に使い、余った時間はほとんど問題演習やディスカッションに充てるそうです。生徒からは「動画を止めたり戻したりできるのでわかりやすい」「演習の時間が多く取れてよかった」等の声が挙がっています。
参考:ベネッセView Next Online「予習を前提とした「反転授業」で授業理解度と教員の授業力が向上 兵庫県 篠山市立篠山東中学」,https://view-next.benesse.jp/view_section/view-junior/article27251/
近畿大学附属高等学校
近畿大学附属高等学校では、2013年から新1年生全員にiPadを導入し、数学と英語で反転授業(反転学習と同じ意味で使われる)を開始。英語の授業はオールイングリッシュで、コミュニケーションとアウトプットを意識して行われています。一方、数学の授業はジグソー法を用いて演習問題の解説を生徒同士でさせる形式です。生徒からは「自宅学習の習慣がついた」「積極的に取り組めば理解が深まる」「自分が理解できているのか、どこが分からないのかを授業で確認できるから良い」といった声が挙がっています。
参考:リクルート進学総研「「生きる力」を育む反転授業/近畿大学附属高等学校」, https://souken.shingakunet.com/higher/2016/09/jirei0078.html
まとめ
反転学習の方法と普及の背景、メリット・デメリット、そして実践例を解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
「自学の中で予習をし、授業を復習にする」という考え方は、東大生の勉強法でもよく出てきます。つまり、実際に効果のある学習方法なのです。ですが、それを教育現場に取り入れ、生徒全員にやらせるとなると、やり方を検討する必要が出てきます。反転学習のメリットを存分に活かし、デメリットを解消できる導入方法が今後出てくることを期待したいですね。
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。