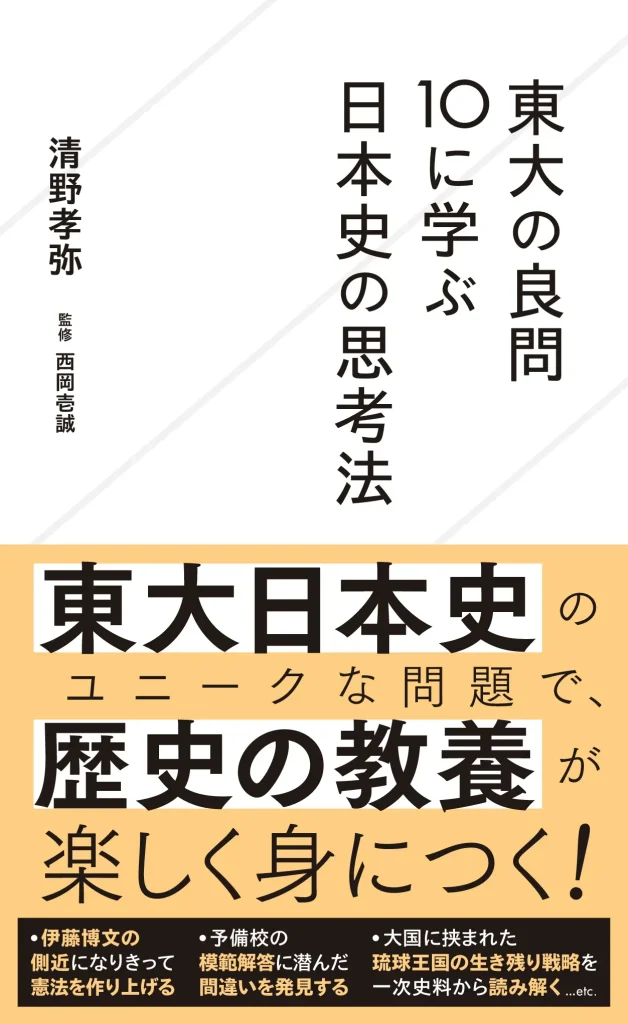おもてなし
東京オリンピック招致のときに話題になった「おもてなし」。日本が五輪招致に成功するきっかけとなった言葉だが、おもてなしという概念は形を変えて世界のさまざまな場所で存在している。
先月久しぶりに帰国したときにも、おもてなしを受けた。
飛行機を2本乗り継いで、ようやく到着したインドの南の小さな町。夜中に国際空港に到着してから、空港の椅子でうたた寝を繰り返していた身体は重く、身体全体で疲労感を感じていた。明け方に食べたカロリーメイトはとっくに消化され、空腹感だけが押し寄せてくる。車窓の前を通り過ぎていく見慣れない景色をぼんやり眺めながら、つい「お腹すいたぁ」と日本語でこぼす。
助手席に座っていた父親が、それを聞いて、運転手にお昼ご飯を食べるところに連れて行ってほしいと頼んだ。腕のよい運転手は、英語もヒンディー語もあまり得意でないようである。驚いたように父親のほうを見ると、小さくうなずき、人と車であふれた道を縫うように無言で運転を続ける。
しばらくしてから、車はありふれた狭い道の端に停まった。降りてみると、目の前は地元の人でにぎわう小さな食堂のようなレストランだった。店には、その土地の言語が飛び交い、外に置かれたメニューの看板は見知らぬ文字で書かれている。運転手が、店の人となにか話している。米を使った料理はないかと母親がいうと、店の人が笑顔でうなずき食堂の奥へ消えていった。
アルミのテーブルの前で、そわそわしながら待っていると、しばらくしてから両手に大きな容器を持った料理人たちが、3人ほど出てきた。皿のかわりとなるバナナの葉を人数分テーブルに並べ、その上にたんたんとご飯や七色の副菜をのせていく。一品並べるたびに、こちらを見ては「もう少しいる?」と確かめる。副菜を手に持った男性は、わたしたちが食べ始めてからも、ときどきわたしたちのテーブルのそばに来ては、「もっと何か必要なものはない?おかわりは大丈夫?」と声をかける。「これがおいしい」と言うと、すかさず手元の容器から一すくいし、鮮やかな緑の葉の上にのせてくれた。わたしたちが満足に食事ができているかと、まるで自分の親戚や友人が訪れたかのように、ずっと気にかけてくれている。
このお店だけではなかった。旅の途中で訪れたどのレストランでも、店員たちは同じように食事は足りているか必要なものはないかと、常に客であるわたしたちを気にかけている。おかわりをしても、もちろん追加で料金を取られることなどない。食べ放題さながらの状況である。客が満足して食事ができるように尽くすことが店員たちの使命であるかのようだった。
食べ物というのは、人間が生きていく上で欠かせないものだ。私が訪れた先の人々は、食事を通して、わたしたちを歓迎した。次々とよそわれた食事は、旅で疲れた体を生き返らせ、心も温めた。