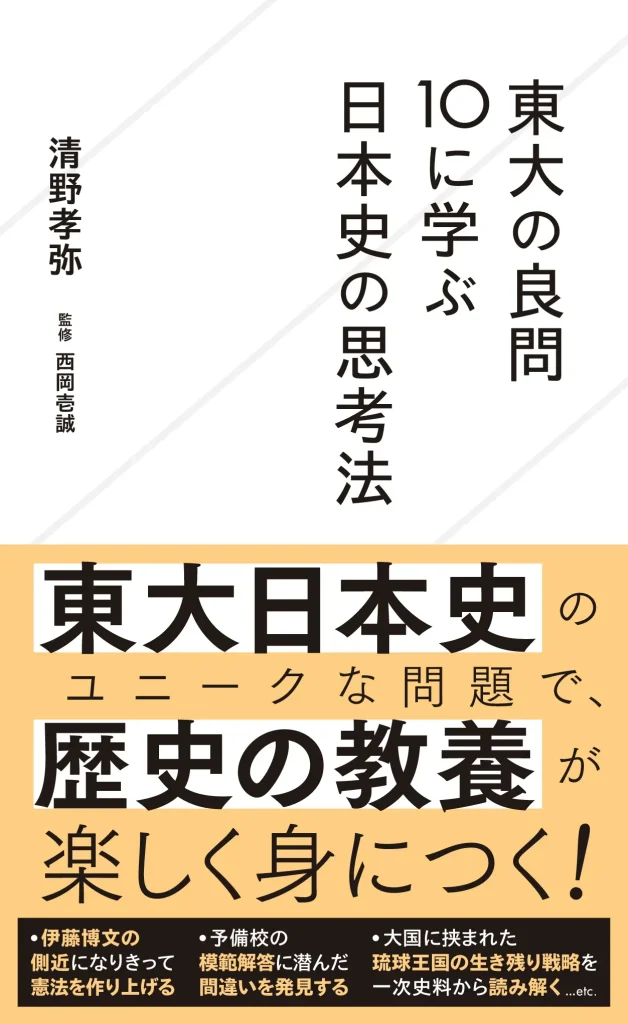なじめそうでなじめない心地よさ
8月半ばに家族でインドに行った。実に十数年ぶりである。里帰りをするのかと、行く前によく聞かれたが、そうでもない。ただ気まぐれで観光に行っただけである。
インドは地域ごとにさまざまな言語があり、私は東インドの西ベンガル州で話されているベンガル語しか話せない。今回はその対極にある南の地域を旅したので、言語も文字も全くわからないところだった。むろん両親も一言も理解できない。意外とヒンディー語もそこまで浸透しておらず、終止英語でコミュニケーションを取っていた。
民族も違うので、人々の顔立ちや体格もわたしたち家族とだいぶ違う。母国に帰ったはずなのに、外国さながらの気分である。挙句の果てに、洋服やボディーランゲージが現地の人と違うのか、道端を歩いていると何かと目だってしまう。インド人らしい目鼻立ちなのに、どこかインド人らしくないのだろう。街中にあふれる外国人観光客よりも、見慣れない奇妙なものとしてひとびとの目にうつったのかもしれない。
ただあまりそれが憂わしいとも思わなかった。むしろ、生まれてこのかた外見上どこかになじんだ経験がほとんどないため、完全に溶け込めないことのほうが自分にとっては自然な感覚なのだろう。中途半端になじむのが、一番心地がいい。
結果、10日間の南インドの旅は、とても心地のいいものだった。結局インド人であることにかわりはないので、その国の一員としてどこでも温かく迎え入れられた。泊った民泊でも、言葉を交わしたひとびとからも、どこか懐かしいような安心感があった。でも、どこかしっくりこない。なんだか、通じない。なんだか、わからない。
言語とかではない。もっと漠然としたその国の空気といえばいいのだろうか。文化や価値観と世の中はいうのだろうが、そういう型にはまったものでもないような気がする。見たことはあるけれど食べたことのない果物を、初めて食べたような感覚である。わかるような、想像していたような、でも経験したことのないような。
考えてみれば、日本にいるときと真逆の感覚であった。日本では、なにもかもなじみがある。ひとびとの行動も言動も見慣れたものだから、予想がつくし日々の生活の中で新鮮さはない。自分の立ち振る舞いも、完全に周囲と一致する。でも、どこか受け入れられていないような感覚がある。周りの目に触れた瞬間、なんだか自分だけ異質のもののような感じがする。
でも、どこにも完全になじむことができないというのは、そんなに悪いことでもない気がする。どこにも強い帰属意識をもっていないため、深く感情移入することもない。自分をどこかの国と重ねることがないのだ。そのため、感情の起伏も少ない。ずっと、母国が出場していないワールドカップを観戦しているような感覚である。いつも適度な距離を保ちながら、観察したり批評したりできる。実に宙ぶらりんで心もとないし、それがゆえの不安感や虚無感もないことはないが、案外気楽でいいものである。
結局、自分はどこにもなじめきれないのである。まだまだ長い人生が残っているはずだから、この先いつか完全に溶け込める国や地域がみつかるかもしれないが、当分はなじめそうでなじめない感覚を味わおうと思っている。もしかしたら、どこにも属しきれないことからくる心地よさに一生浸り続けることになるかもしれないけれど。
インド旅行中のこまかなエピソードは、また次のお話で書こうと思う。